問題提起
「民家にクマが出没した模様です!!」
ニュース番組で、郊外の住宅街にクマが出没したのだとレポーターが声を荒げる。
するとSNSでは、コンビニの前に立つイノシシの動画がシェアされて嬉々としたコメントが飛び交う。
そして、遠い山間部の農家が、猿の群れに畑を荒らされ、途方に暮れる姿がテレビの特集で報じられる。
人間と野生の境界線、それは決して遠い世界のものではありません。
あなたが住む都市のわずかな緑地帯、通勤途中に見える森林、週末に家族と訪れる郊外のレジャー施設。
そのすぐ隣、あるいは目と鼻の先で、私たちとは異なる「命」が蠢いています。
「彼らは、古くからの掟に従い、ひっそりと、しかし確実にその生息域を広げ、私たちの生活圏へと足を踏み入れている。」
想像してみてください。
もし、あなたが朝、ゴミ出しに出たときに、ゴミ箱を漁るイノシシと鉢合わせしたら?
もし、子どもの通学路に、親子のクマが現れたとしたら?
私たちは「自然」と「文明」の間に、分厚い壁を築いたつもりでいました。
しかし、その壁は今、ひび割れ、音もなく崩れ去ろうとしています。
この現象は、単なる「獣害」という言葉で片付けられるような、表層的な問題ではありません。
私たちは、人間として、社会として、どこへ向かおうとしているのでしょうか?
それは、あなたの日常のすぐ隣に潜む、壮大で、しかしどこか物悲しい「野生の物語」です。
背景考察
「消えた「里山」と増えゆく「隣人」の足音。」
なぜ、これほどまでに野生動物が人里に近づき、被害が深刻化しているのか。
その背景には、戦後の日本の劇的な社会変化が深く関わっています。
農林水産省のデータによれば、2021年度の野生動物による農作物被害額は、なんと約155億円に上ります。
これは主にイノシシ、シカ、サルによるものですが、被害の報告件数は年々増加の一途を辿っています。
また、環境省の発表では、2023年4月から11月にかけてのクマによる人身被害が193件、うち死亡者が6人と、過去最多を記録しました。
これらの数字は、もはや「地方の一部の問題」とは言えない切迫した状況を示しています。
では、なぜこのような事態になったのでしょうか?
その答えは、かつて日本の農村に存在した「里山」という概念に深く関係しています。
「里山は、人里と森の間に広がる緩衝地帯であり、人々はそこで薪や炭を得るために木々を手入れし、山菜を採り、適度な明るさと多様な植生を維持してきた。」
それは、まるで「となりのトトロ」の世界に描かれるような、人と自然が優しく共存し、お互いの領域を尊重しあう風景でした。
しかし、高度経済成長期を経て、私たちの生活は一変します。
エネルギー革命が起こり、薪や炭は石油やガスに取って代わられました。
経済的な価値を失った里山は、手入れされることなく放置され、荒れ放題の「奥山」と化していきました。
そして荒れた里山は、野生動物にとって隠れ家となり、同時に、人間との境界線が曖昧になっていきました。
「イノシシたちは何もかも壊してしまうんです。それに育てているミカンも、落ちた果物や栗も片っぱしから食べてしまいます。じゃがいも畑は全滅です。」
ある農家の方は疲れた声でため息混じりに語ります。
彼らにとって、野生動物はもはや「可愛い動物」ではなく、生活を脅かす「害獣」に他なりません。
加えて、この状況を加速させたのが、野生動物の個体数を調整する役割を担っていた「猟師」たちの激減です。
1975年には約51万人いた全国の猟師が、2021年には約19万人へと3分の1以下に減少。
平均年齢も70歳代とも言われ、後継者不足は深刻です。
担い手のいなくなった山で、野生動物の個体数は増え続ける。
彼らは安全な場所と魅力的な餌を求めて、ますます人里へと接近してくると。
私たちは知らず知らずのうちに、自らの手で「野生の隣人」を増やす環境を整えて人里へと誘い込んでしまっていたのかもしれませんね。
彼らは、ただ生きるために、私たちの生活圏へと足を踏み入れているだけなのですから。
伏線
「「食べる」という哲学が日本人の精神基盤でもある。」
ここで一つの興味深い動きがあります。
それが「ジビエ」ブームです。
獣害対策で捕獲されたイノシシやシカの肉を有効活用しようというこの動き。
それは「命を無駄にしない」という倫理的な側面や、「安全で健康的な食」という価値観と結びついています。
フレンチレストランで提供される高級なジビエ料理だけではありません。
最近では、地域の道の駅やスーパーでも手軽にジビエ肉が手に入るようになりました。
あなたは、このジビエという食文化に、どのような感情をお持ちになりますか?
「可愛そうな動物を食べるのは…」という感情でしょうか?
それとも、「命をいただくことへの感謝」を感じるでしょうか?
この「食べる」という行為には、実は非常に深い哲学が隠されています。
かつてマタギは、捕らえた熊を「山の神からの贈り物」と見なし、その命を余すことなく使い切ることで感謝を示しました。
彼らにとって、狩猟は単なる殺生ではなく、自然との循環の一部であり、精神的な営みだったのです。
しかし、現代の私たちはどうでしょう?
都会で暮らす私たちは、食べ物がどのように生産され、食卓に届くのか、その過程を知らないことも多い。
加工された肉を何の感情も抱かずに消費する一方で、野生の動物が駆除されるニュースには感情的に反発する。
この「感情的な動物愛護」と「現実的な食の消費」という矛盾が、私たちの中に静かに横たわっています。
テクノロジーの進化が、私たちを自然から遠ざけ、感情的な摩耗をもたらしているのかもしれませんね。
解説
「かつて、日本の里山は、人間と野生の間の緩衝地帯として機能していた。」
そこには、マタギのような人々が、山の神を敬い、命を「いただく」という行為に深い哲学を見出していました。
彼らにとって、狩猟は単なる殺生ではありません。
自然の循環の一部として、自らもその恩恵を受け、責任を負うという、まさに「共生種」としての関係性でした。
そう、つまり、彼らは、人間が自然を完全に支配するのではなく、共に生きる「伴侶」として向き合っていたのです。
しかし、近代化の中で私たちは、この身体的な知恵や、自然への敬意を忘れていきました。
私たちは「進歩」に目が眩み夢中になり、都市を拡張し、地方の里山を置き去りにしました。
その結果、手入れされなくなった森は野生動物の生息域を広げ、同時に、彼らの餌資源を人里へと向かわせる引き金となったのです。
そして、その現象は、SNSの普及によって、都市に住む人々の感情を直接揺さぶるようになりました。
動物の可愛らしさに心を奪われ、駆除に反対する声。
これは、遠隔化された自然に対する「ロマンティシズム」と、生命への純粋な愛着の現れです。
しかし、その感情は、実際に獣害に苦しむ人々の「現実的な恐怖」と衝突し、社会に分断を生み出してしまいました。
結論
この長い物語を通して、あなたは「野生」というものが、どれほど私たちの生活、社会、そして心の奥底にまで深く根ざしているかを垣間見たことでしょう。
それは、単なる「獣害」という言葉では片付けられない、壮大で複雑な「人間の物語」でもあります。
私たちは、かつて自分たちが築いたはずの「境界線」が、音もなく溶け出していく時代を生きています。
その中で、動物たちもまた、私たちと同じように生きるために適応しようとしています。
「私たちは、野生とどう向き合うのか?」
この答えは、誰か一人の人間が出せるものではありません。
それでも、この世界が、昨日とは少し違って見えたら良いなと思いました。
用語解説
■ 里山(さとやま):
人間が定期的に手入れをしてきた、森と人の生活圏が隣接する場所。昔は薪や山菜を採るなどして、人と自然が共存する緩衝地帯だったが、今は手入れされず荒れている場所が多い。
■ マタギ(matagi):
東北地方などの山間部に伝わる、伝統的な狩猟を生業とする人々のこと。山の神を信仰し、厳しい掟と共存の知恵を持って狩りを行ってきた。
■ ジビエ(gibier):
フランス語で「狩猟によって得られた野生動物の肉」を指す。日本では、増えすぎたイノシシやシカによる獣害対策として、捕獲された動物の肉を有効活用する食文化として注目されている。
■ ロマンティシズム(romanticism):
現実よりも理想や感情、自然の美しさなどを重視する考え方。野生動物に対し「可愛い」「守りたい」といった感情を抱く背景にあることが多い。
■ 共生種(companion species):
人間と他の生物種が、単に同じ場所で生きるだけでなく、お互いに深く関わり合い、共に進化してきた関係性(例:人間と犬)。

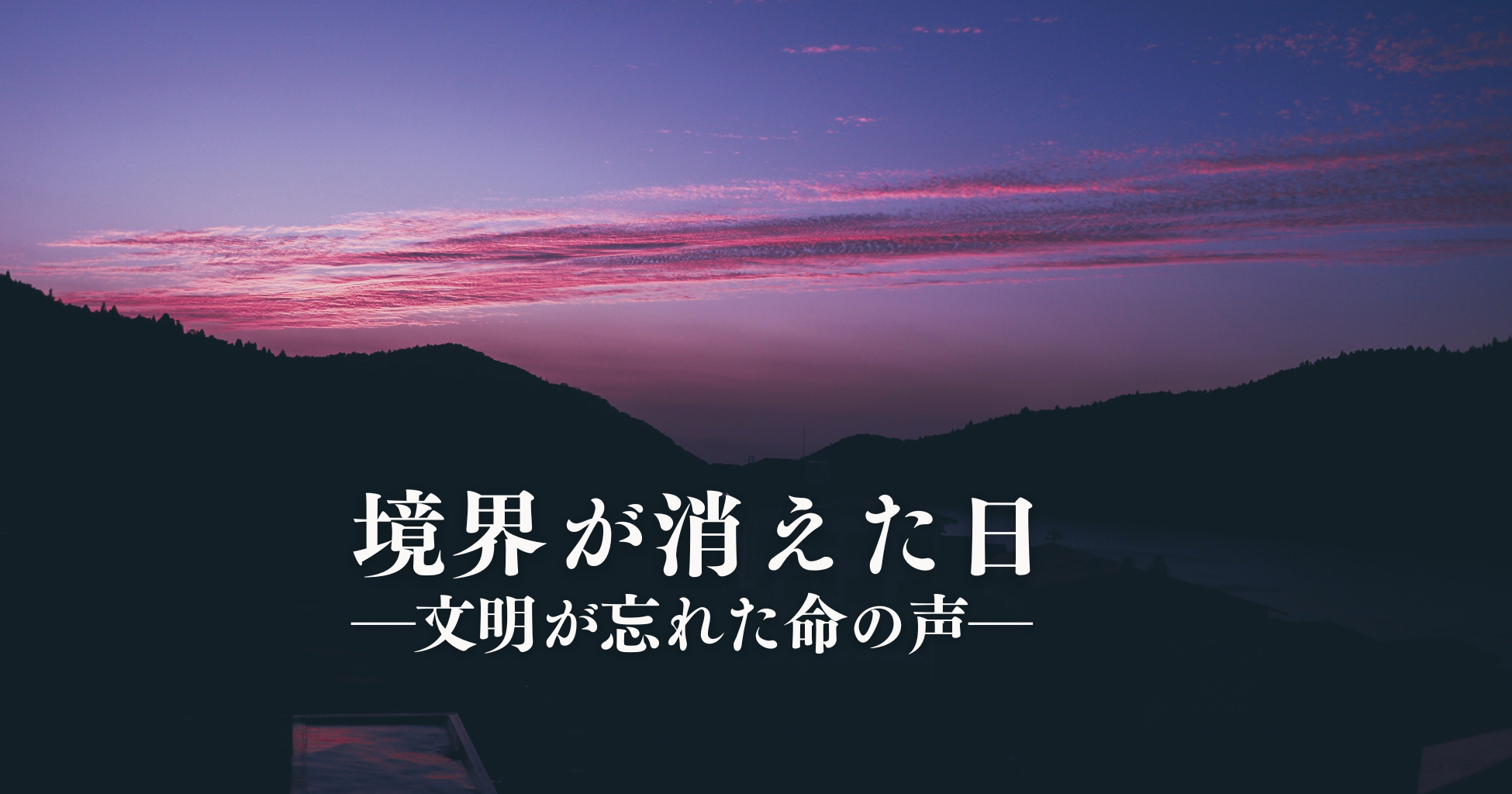
人間が開発し、作った都市という理想郷。
その理想郷の崩壊を示唆する出来事が動物たちの侵入?干渉?であると感じた
人間はこの世界に存在する絶対強者として思うがままに生活圏を広げてきた
先住者がいようが関係なしに自分たちにいいように開発し、現在に至る
種を増やし続けることが種の繁栄であるなら人類の繁栄はそろそろピークに達する
日本や先進国だけでなく、近い将来世界全体の人口も減少に転じると予想されているからだ
思うがままに開発した都市もそれにより衰退していく
現に今もインフラの維持、管理に支障をきたすようになっており、これから先、今の生活圏を維持するのは困難になり、人口減少に対応するため、計画的に居住区を狭め、過疎地域は「放棄」されるようになると予想する
これは悪いことではなく、人口減少にいかに対応するか?というひとつの策で、拡大一辺倒から「いかによく縮むか?」へのパラダイムシフトである
放棄された地は新たな居住者が住み着くであろう。そしてそこは住むものに住みやすい環境に変わっていく。都市化したものが再び自然に還っていく
動物が人間の生活圏に入ってきている現象はこの「予行演習」の気がしてならない
彼らは人間の衰退を敏感に見越して、人間の作った都市の一部をどうやって再び自分たちの理想郷にしていくか?模索しているのかもしれない
自然は誰の物でもない
あたかも自分たちの物であると誤認している私たちはそれが間違いであったと思い知ることになるような気がしてならない