問題提起
「SNSで繋がっている友達は山ほどいるけれど、心の底から『いいね!』を送り合える関係って、どれだけあるんだろう…。」
先日、ある若いビジネスパーソンが、少し寂しげにそう語ってくれました。
彼の言葉は、現代社会が抱える根源的な問いを突きつけているように思えました。
私たちは今、情報で満たされながらも、どこか「心の飢え」を感じているのかもしれません。
もし、あなたの日常から、「やさしくあたたかい共感」が失われたとしたならば。
それはどのような状態を想像するでしょうか。
かつて、私たちは目の前の大切な人との間に、言葉を超えた「何か」を感じ取り、喜びや悲しみを分かち合っていました。
それは、季節の移ろいを共に感じ、食卓を囲み、互いの心を慮る、ごく自然な営みの中に息づいていました。
しかし、携帯電話に始まり、スマホが普及し始めた頃から何かが変わっていきました。
その結果、何が起きたのか。
そう、私たちは、言葉によるコミュニケーションこそが、「コミュニケーション」だと思い込み始めているのではないでしょうか。
そんな現代において、もしも、我々の心の奥底に眠る「共感」を呼び覚ます鍵があるとしたら。
しかもそれが、「和菓子」にヒントがあるのだとしたら。
本日はそんな可能性について一緒に考えていきたいと思います。
背景考察
考えてみれば、私たちの祖先は、遥か昔から「何か」を通じて心を繋いできました。
縄文時代の土偶に始まり、遥か時代を下って、茶道と和菓子の関係を紐解いてみましょう。
室町時代に端を発し、千利休によって大成された茶道。
それは単なるお茶を飲む儀式ではありませんでした。
そこには、「一期一会」という、二度とない瞬間を大切にする精神が宿っていました。
そして、その「もてなし」の心と深く結びついていたのが、和菓子です。
想像してみてください。
亭主から差し出された一服の抹茶と、添えられた一皿の和菓子を手に取ります。
その和菓子は、まるで雪の結晶のように繊細で、淡い色合いの中にも凛とした美しさを湛えています。
口に含めば、ほのかな甘みが広がり、その瞬間‥
あなたは亭主がこの日のために、いかに心を砕いて準備したかを感じ取るのです。
外の寒さを忘れさせるような、その温かな心遣いに、言葉にならない「共感」が生まれるのです。
これは、決して物語の中だけの話ではありません。
実際に、江戸時代、京都だけで100軒以上の和菓子専門店が存在していたそうです。
また、現代においても、茶道教室の約95%で和菓子が提供され、茶会用和菓子が市場の約30%を占めています。
それは、和菓子が「もてなし」と「共感」の文化装置として、いかに深く根付いていたかを物語っています。
「和菓子が季節と心を伝える橋になる。」
――とある表千家の茶道講師は語ります。
そう、和菓子の意匠は、「見て味わう」美学であり、まさに「言葉のない対話の媒体」なのです。
春の桜、夏の金魚、秋の紅葉、冬の椿。
季節ごとの和菓子の形や色は、単なるデザインではありません。
まさに、茶会の雰囲気そのものを構成する重要な要素として機能してきたのです。
さて、ここで一つの奇妙な矛盾が浮かび上がってきます。
和菓子は、控えめに言っても「美的価値」「文化的地位」「芸術性」を極めた格式高い文化です。
事実、UNESCO無形文化遺産「和食」の構成要素として世界に誇る存在でもあります。
海外のミシュラン店でその意匠が模倣され、和菓子職人の技能が国家資格として制度化されていることからも、その卓越性は明らかです。
しかし、その一方で、近年の和菓子は若年層の茶道離れとともにその象徴性が減退しています。
そして、意匠重視のあまり味の革新が停滞するリスクさえ指摘されています。
なぜこれほどまでに洗練され、心を揺さぶる力を持つ和菓子がそのような状態に陥っているのでしょうか。
そこには、私たちが時代の変遷と共に忘れてしまった何かがあります。
そう、それは、「和菓子は食品ではなく、“共感記号”として消費されて来た」という実態です。
私たちは今まで、和菓子の表面的な「味」や「形」に囚われすぎて、その奥に隠された「心の味覚」を見落としていたのかもしれません。
まるで、目の前の絵画の色や筆致ばかりを分析し、その絵が描かれた「理由」や「画家が伝えたかった感情」に気づかずにいたかのように。
結論
和菓子は、単なる甘味ではありません。
人々が互いの心を慮り、季節の美しさを分かち合い、そして「二度とない瞬間」を慈しむための、見えない「共感の糸」を紡いできました。
だとするならば、今こそ和菓子とは何かを再定義する時が来ているのかもしれません。
そう、単なる食べ物ではなく、季節・気候・場面と連動した「感情の装置」として。
もしそうであるならば、私たちは、和菓子を通じて、どのような感情を創造し、共有できるのでしょうか?
そして、デジタルが支配する現代において、「共感」と「感動」はどう変わっていくのでしょうか。
続きは中長期経営計画を一緒に作る会で、お話をさせて頂きます・・!!
用語解説
■ 一期一会(いちごいちえ):
「一生に一度きりの出会い」という意味で、茶道で特に大切にされる精神。今日の茶会は二度と繰り返されることはないから、亭主も客人も心を尽くすべきだ、という教え。
■ もてなし:
客人を心から歓待すること。相手を思いやり、喜んでもらおうとする気持ちそのもの。茶道では、道具選びから和菓子の選定、空間の演出まで、すべてが「もてなし」につながる。
■ 意匠性(いしょうせい):
デザインや装飾の美しさ、工夫のこと。和菓子では、色や形、模様で季節の風景や物語を表現する工夫が凝らされている。
■ 共感記号(Empathy Symbol):
ここでは「特定の文化や文脈の中で、共有された感情や経験を呼び起こし、共鳴させるような表現やモノ」と定義。和菓子が、味だけでなく、見た目や背景にある物語を通じて人々の心に共通の感情を呼び起こす働きのこと。
■ 心の飢え:
情報や物質は満たされているのに、精神的な満足感や充実感が得られず、どこか虚しさを感じること。人との深いつながりや、感動する体験が不足している状態を指す。

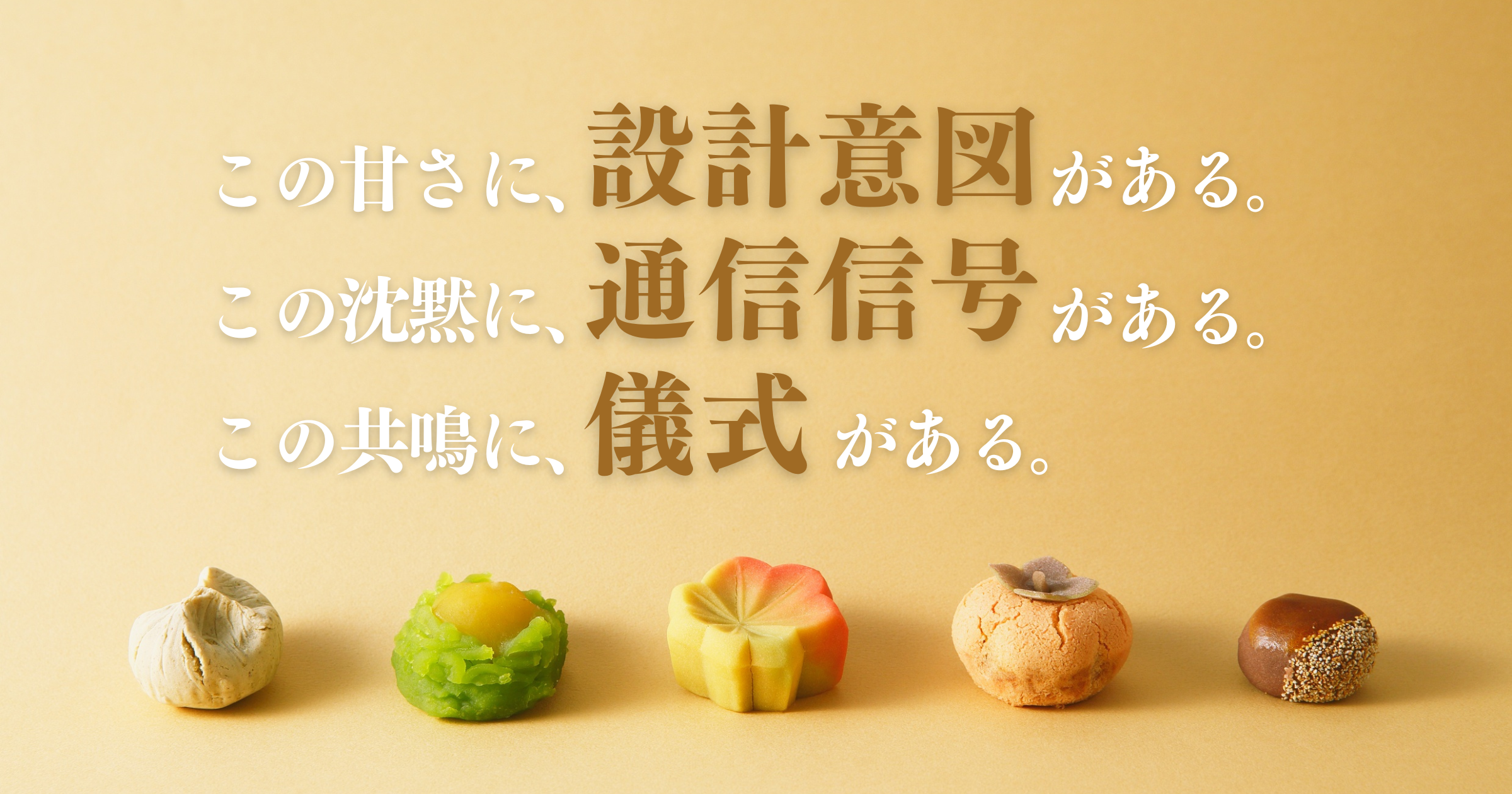
和菓子に込められた意味を茶道を通して考えさせられました
日本的なコミュニケーションとされる場の空気を読む、察する、へりくだるなど、そういえばいつの間にか忘れさられているのでは?
そう考えると資本主義の発達と文化を忘れることは比例するのかもしれません
経済発展こそが正義と言わんばかりにひたすらGDPの拡大を目指す。企業も利益がでなければ株価下落し、株主から責任を追及される。今の資本主義の仕組み上、そうならなくてはいけないようにされている
限りある地球の資源の中で経済発展をひたすら追及し、実現することはできるのか?その先に何があるのか?
人類全体が人口減少の時期に達した時に経済発展は終わり、何かが変わるのか?
それともそれ以前に世の中の仕組みが変わるのか?
現在の人間関係が空虚に感じられるのだとすれば「個人の利益の追及が社会を発展させる」という言葉は詭弁なのかもしれない
デジタル(離散量)で表現される世界では、アナログ(連続量)のものをデジタルへ変換するときに、何かしらの欠損するデータが必ず存在し、どんなにデジタルのデータ量が増えても、離散化すればするほど永遠に割り切れない、表現できない領域が必ず存在すると思います。
そこに本質的な価値が存在しているのかなと思いました。
今回でいえばおもてなしやコミュニケーション、共感などはまさにその領域なのかなと思います。