問題提起
「もしAIエージェントが本当に有用なものになるなら、インターネットは暗くなるだろう」
ウェブサイトやアプリがなくなるわけではない。
多くのウェブサイトやアプリについては、消費者が直接訪れたり、見ることはなくなるだけだ。
その代わりに、「情報集約の中心」となるAIアシスタントを通じて、消費者は情報やコンテンツ、ウィジェットにアクセスすることになるとアナリストたちは述べている。
―TECH INSIDER―
「AIエージェントが私たちの日常を根底から変えるのではないか。」
近年、こうした仮説が、スタートアップ界隈や学術界、さらには政府機関やメディアの間で急速に注目を集めています。
なかでも鮮烈なのが、いわゆる「アプリの消滅」と呼ばれるシナリオです。
それは、単体のアプリケーションをダウンロードする行為そのものが消え去るのではないかと。
代わりにAIエージェントが必要な機能をすべて「裏側」で自動的に引き出してしまうのではないかという未来予測です。
そしてこの現象と表裏一体で語られるのが、「主観なき人生(造語)」という、ややショッキングなフレーズを伴う仮説です。
身体的・精神的データを常時解析され、どの瞬間に「快」を与え、どの瞬間に「不快」を避けるのが最適かをAIエージェントが先読みしてしまう。
その結果、人間が自ら選択するプロセスや個人的な欲求、さらには感情の揺れ幅までもが画一化されるのではないかと。
もし本当にそうなれば、「幸福感の標準化(造語)」や「意識のダウンサイジング化(造語)」と呼ばれる概念が登場するのかもしれません。
「誰もがそれなりに安定した幸福状態を享受する代わりに、個性や創造性が希薄化するのではないか?」
「幸福感の標準化」とは、AIによって個々の嗜好やバイタルデータが最適化された結果として起きる現象です。
「人間の脳自体が本来備えている認知機能を使わず退化させ、新たな人種的変化や進化(あるいは退化)が生まれるかもしれない。」
また、「意識のダウンサイジング化」は、アプリや感情までもAIに丸投げする生活が続いた末に起きる現象と考えられます。
これらは一見突飛なシナリオのように思えるかと思います。
しかし、すでにデータ駆動型のマーケティング手法やAPIを活用したプラットフォーム連携は進んでいます。
そして、高精度の感情解析技術が市場に投入され始めている現在、そのリアリティは日増しに高まっていると言えるでしょう。
では、アプリが消滅する未来で見えるものとは何か。
人々が「主観なき人生」に追い込まれた先に待ち受けている結果とは何か。
いずれ訪れる変化と未来は、私たちにどのような影響を与えていくのでしょうか。
背景考察
これは究極の「新しいアプローチによる最初の段階」になるかもしれない。
我々一人一人をの代理となるAIエージェントは、テック企業が消費者との間に新しい形の直接的な関係を作り出す強力な手段となるだろう。
今までは消費者が個別にアプリやウェブサイトにアクセスしてサービスを受けていたのが、
AIエージェントがそのすべてを集約して一元的に提供する形に変わり、何らかの料金を支払わざるを得なくなるだろう。
―TECH INSIDERー
「ユーザーが好みのアプリを自分でダウンロードして、能動的に使う。」
まず、現在のスマホを通じたネットサービスはその前提のもとに成り立っています。
そしてiOSやAndroidといったモバイルOSが普及して以来、アプリは利用者とのダイレクトな接点として機能し、いわゆる「アプリ経済」を支えてきました。
「AIエージェントが必要な機能だけをまとめて提供する。」
しかし今、多くのスタートアップや大手テック企業が目指すビジョンはこの図式を崩そうとするものです。
それは、ユーザーがアプリを探してダウンロードする手間すら省略するという世界観です。
特に注目すべきは、APIエコシステムの急拡大である。
これまでは個別企業ごとに独自アプリを構築し、ユーザーの目に触れるよう広告やマーケティングを仕掛けていました。
しかしこれからは、AIエージェント向けのAPIを公開することで、ユーザーがエージェントを通じて自社サービスを間接的に利用するモデルが増えるでしょう。
この現象は経済学的観点から見た場合、プラットフォーム寡占を加速させる大きな要因となり得ます。
なぜなら、大手AIプラットフォーム企業があらゆるサービスの入り口を一括で握り、いわば「ゲートキーパー(Gatekeeper)」として機能するためです。
「アプリ消滅の未来は、主観なき人生と感情調整の自動化という現象を呼び起こす。」
アプリの消滅は、単純なUXの変革だけで終えるような小さな変化ではありません。
そこにAIが常時取得するバイタルデータや心理データが掛け合わされるとき、私たちの日常はより深い次元で変容すると考えられます。
例えば、ある感情解析スタートアップが、蓄積するニューラルネットワークを用いた場合を想定して頂きたいのです。
ニューラルネットワークとは、人間の脳にある神経回路の構造を数学的に表現する手法で、Googleの検索アルゴリズムにも採用されています。
また、音声や画像などの複雑なデータパターンを認識・学習できるため、AI(人工知能)を支える技術として近年注目を集めています。
では、その技術を用いて、人間の脳波パターンや心拍変動をリアルタイムで取得・共有・蓄積した場合、何が起きるのでしょうか。
その結論は、ストレス状態や幸福感のピークを予測・再現・依存させる領域にまで到達すると考えられます。
「科学技術が、その社会の社会構造や文化的価値観を決める。」
ちなみに、アメリカの経済学者ソースティン・ヴェブレンは、技術決定論を提唱しました。
言い換えれば、「技術が進化し得る範囲であれば、それは必ず社会実装されうる。」という論理が成り立つということです。
「今、このタイミングでこのサービスを利用すれば、ストレスが軽減されます。必要ですよね?」
「この映像コンテンツを見れば、幸福感を浸れますよ。断る理由はありませんよね?」
つまり何が起きるのかというと、AIエージェントがユーザーの「快・不快」を先読みして、瞬時に提案してくる時代が到来するということです。
「ユーザーは、あえて脳内ホルモンの分泌を最適化した選択肢を拒む理由が見当たらない限り、「受信者」として行動するだろう。」
学術の領域では、「HCI(ヒューマン・コンピュータ・インタラクション)」という言葉が近年注目を集めています。
それは、「人間がコンピュータにどのように関与し、互いに作用し合うか。」を追求する学問です。
しかし、AIエージェントが極度に自律化すると、その相互作用は一方通行的になります。
つまり、人間はコンピュータの推奨を“オートパイロット”のように受け取るだけの存在になりかねないのです。
それはまさに、映画『MATRIX』で見たようなAI>人類というディストピアが、静かに、真綿で首を絞めるように迫って来ているということです。
「幸福感の標準化が引き起こすのは、価値観の均質化である。」
AIエージェントが大量のユーザーデータを分析し、それぞれに最適化された幸福状態を規定した場合。
その過程が一度普遍化してしまえば、後は緩やかにユーザー全体が均質化していくと。
それが、幸福の標準化の末に起きる均質化という現象です。
いい意味では捉えれば、心理学の領域で言われる「ウェルビーイング(心身ともに満たされた状態、心の豊かさ)」の最大化というゴール設定になるのでしょう。
しかしそれが、「社会構成主義」から考慮すれば、幸福の概念自体がAIアルゴリズムによって規定されていることになると。
つまり、「ウェルビーイングそのものがアルゴリズムに決められている状態は、本当にウェルビーイングなのか?」ということです。
そう、それが「主観なき人生」という状態を作り出すのかもしれません。
もちろん、多くの人々が安定した幸福を得られるのであれば社会的には一見望ましくも見えますが。
また一方では、「人間らしい喜怒哀楽や不確実性が持つ創造力」を潰してしまう可能性があると考えられます。
例えば、芸術や音楽の世界では、不安や苦悩、さらには予想外の刺激が新しいアイデアを生む重要な要素とされています。
しかしAIによる“画一的な幸福誘導”が常態化した場合、そうした創造性を育む土壌が確実に狭まるのではないかと。
では最も重要なことは何か。
それは、詮ずるところ、AIアルゴリズムの進化は逆説的に「多様性の喪失を引き起こしていく」ということです。
「アプリが消滅し、AIエージェントによってすべての意思決定が最適化される世界は、我々が想像する以上に現実味を帯びている。」
ここで強調したいのは、私たちがその未来を遠いSFの話と捉えるべきではないということです。
「主観を失ったまま幸福を享受する、主観なき人生を全うする人間」になるのか。
「AIが押しつける標準化された幸福観に抵抗し、より人間らしい不確実性や創造性を守ろうとする人間」になるのか。
言い換えればその未来は、誰もがどちらかを選ぶ世界です。
次回は、具体的な事例を交えながら「主観なき人生」について焦点を当てて、そこで暗躍するであろう“AIエージェント産業”の思惑に迫りたいなと。
そんなことを考えさせられました。
それではまた、後編の②でお会いしましょう!

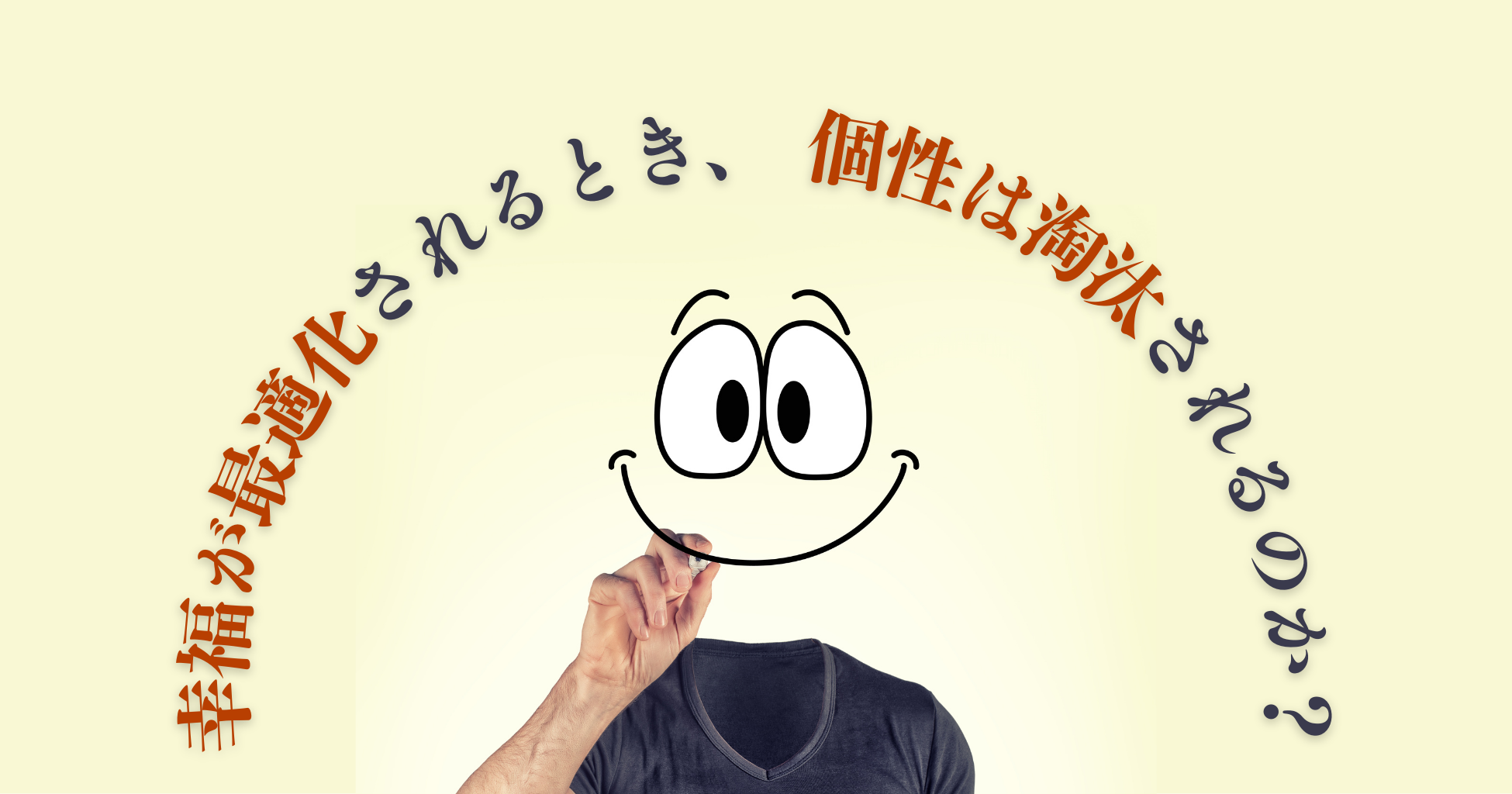

今回の記事を読んで皆さんはどう思うのか?
そもそも理解できない
そんなわけないだろ
本当にそんなことが起こるのか?
納得する、そうなりそうだよね
私は「納得する、そうなりそうだよね」と思う
50年ほど生きてきて、「そんなことできるわけない」と思ってきたことが意外と今、できている
いくつか例をあげると
1.中学、高校の時に固定電話で長電話(死語か?(笑))をすると「電話代払え」と親に怒られた。特に当時、長距離電話はそれなりに高かったのでわかる。
子供ながらに電話代が只ならどんなによいだろうと考えていた
その後いつかは覚えていないが新聞で「将来、音声通話はすべて無料になる」と話していた人がいて、大学生の時も電話代を結構払っていた私はそれを読んだ時は「そんなわけないだろ」と感じた
その後、スカイプがでてきて、whats up やline の無料メッセージアプリがでて、今ではライン、メッセンジャーなどで音声通話は無料なのが当たり前になっている(海外との通話もできるのが昔の国際電話の価格を知っている私としては驚愕する)
2.小学生の頃、ファミコンに熱中していた
ディスクシステムは低価格(当時500円〜1,000円だった気がする)で「書き換え」ができて書き換えができる機械が玩具店などに置いてあり、そこでできた。当時は週一くらいで書き換えて他のゲームで遊んでいた。中学生くらいのときに「将来ゲームはソフトで買うのではなく、データで買う時代になる」とでていて「そんなわけないだろ、カセットやディスクが消えるなんて」と思ったが、今はソフト購入はダウンロードが当たり前になり、さらにはオンラインゲームも当たり前になった
3.高校の時にサイバーフォーミュラというアニメに熱中した。未来のF1の話が題材で意思を持った車に乗り、その車がアドバイスしてくれたり、相談にのってくれたりして相棒としてドライバーとタッグを組んでレースを戦う内容だった。主人公が自分がまったく勝てる自信のないレースにでるか、でないか迷った時に車に相談したら「もし、レースにでなければ勝つ確率は完全にゼロだが、出たならば可能性はゼロではない」と回答がきて、レースに出た。結果、勝てたシーンがあった。
コンピューターに相談できることは当時、非現実的でアニメの世界だと思っていたが、今はGPT、ジェミニなど、何でも聞けて、それなりの回答を得ることができる。これを意思決定にも活かせる時代である
AIエージェント、おおいにあり得ると思う。それに人がある意味で知らないうちにコントロールされることも
今思えば、マスコミも似たようなものだったとも思う
テレビがブームの仕掛け人だったときは繰り返し放送し、それがブームだと洗脳していく。大衆をコントロールできればビジネスは有利である。そして日本人は特にコントロールされやすい人たちだと私は感じている
いつもありがとうございます。
サイバーフォーミュラに思わず反応してしまいました。
OP『Winners』はもっと評価されていい隠れた名曲だと思っています。
「人の瞳が背中についてないのは、前に向かい生きてゆく使命があるから。」
この50年で獲得した人の進化は凄いですよね。
技術進化は留まるところを知らず、資本主義の良い側面が出ているなと思いました。
「今が苦しいからこそ、明日が輝くのさ。」
その反面、そう思える信仰が消え去りつつあるのが現状です。
悪い側面である格差拡大をどのようにコントロールするのか。
人よりも、資産をコントロール出来る状態を。
そんなことを考えさせられました。