問題提起
今、この国が求めている物は、第三者を消費する事でのみ成立する桃源郷の再現だ。
かつて、この国は偶然にもそれを体現した歴史がある。
動機なき者達は今もそれを無自覚に欲している。
―攻殻機動隊―
「静かに、しかし確実に、かつてこの島国が経験した栄華の『影』が忍び寄っている。」
我々が日々の生活で享受するささやかな安寧、スマートフォン越しに眺める理想化された社会。
その裏側では、見知らぬ「誰か」や「何か」が無自覚に、或いは意図的に「消費」されている。
それが、この国の冷たい真実です。
つまり、現代社会が抱える根深い構造的な問題とは。
それは、視えない「消費」と「他者」の関係性です。
グローバル化、デジタル化、そして経済格差といった現代の課題。
それらは、システムとして意図的に、或いは自動的に再生産されている可能性があります。
「もしその構造が強固になれば、我々は自らの手で、安定と引き換えに倫理を差し出す社会を築いてしまうかもしれない。」
これから我々が直面するのは、この構造的な「消費」がデジタル空間で加速し、倫理的な責任の所在が曖昧になることです。
経済的合理性という名の元に、人間の尊厳や共感をいかにして守るべきか。
この問いに応えなければ、私たちは知らず知らずのうちに、誰かの犠牲の上に立つ社会の共犯者となるでしょう。
その変化と未来は、私たちにどのような影響を与えていくのでしょうか。
背景考察
「この国は第三者を消費することで成立する桃源郷を偶然にも体現した歴史がある。」
それは、間違いなく日本の高度経済成長期(1955年~1973年頃)を指しています。
この時期、日本は驚異的な経済成長を遂げました。
実質GDPは1960年代に年平均10%以上もの成長を記録、今のマイナス成長とは真逆です。
1968年には西ドイツを抜いて資本主義世界第2位の経済大国へと駆け上がりました。
これは紛れもない事実であり、「日本の奇跡」として国内外で賞賛されました。
国内では都市化が進み、「三種の神器」に始まる消費ブームが生活水準を飛躍的に向上させました。
まさに、多くの国民が「桃源郷」と呼ぶにふさわしい安定と豊かさを実感した時期だったと言えます。
しかし、この繁栄の裏側には、「第三者を消費する」構造が深く組み込まれていました。
そう、国際的には、冷戦構造下で米国からの経済的・軍事的な保護を受けていました。
そして、アジア諸国からの安価な労働力や資源を積極的に活用する経済構造がありました。
国内においても、急速な工業化は、水俣病や四日市ぜんそくといった深刻な環境汚染を引き起こします。
つまり、住民の健康という「第三者」の犠牲の上に成り立っていたと。
また、農村から都市への大規模な人口移動は、地方の過疎化を招き、伝統的な共同体の解体を促しました。
これは、都市の繁栄のために地方という「第三者」が構造的に疲弊していった側面を示すものと言えます。
「私たちは背景にある「第三者」の犠牲が見えていながら見ないふりをしてきたのか?それとも見えていなかったのか?」
自らの手元を清潔に保つために、見えない場所に不都合なものを押し付けた結果が高度経済成長だった。
そう捉える人もいらっしゃいます。
「動機なき者達は第三者を消費することで得られる桃源郷を無自覚に欲している。」
フランスの社会学者エミール・デュルケームは、不安定で無規範な状態をアノミーと名付けました。
日本は今、少子高齢化と経済基盤の沈下により、社会が急激に変化しつつあります。
従来の規範や価値観が揺らぐ中、人々は安定を求め、その安定を保障してくれるならばと考えている最中です。
すなわち、集団の安定と繁栄のためならば、特定の他者の犠牲を許容するという集合的無意識があると。
そのためならば、倫理的な問題から目を背けてしまうと考えられます。
「私たちは「アルゴリズムの鏡」を通して、自分が見たい世界だけを見て、その裏側にある構造的な問題や他者の苦境から目を背けるだろう。」
またここで興味深いのは、この「第三者の消費」構造が、デジタル空間において新たな形で再現されつつあるという点です。
インターネットの普及は、情報へのアクセスを容易にし、多様な意見に触れる機会を増やしたはずでした。
しかし、実際には、フィルターバブルやエコーチェンバー現象が、私たちの情報空間を同質な意見で満たしました。
言い換えれば、異なる視点を持つ「第三者」を不可視化、或いは敵対視しやすい環境を生み出したのです。
とはいえ、ここで一つのジレンマが生じます。
私たちは、日々の生活で「第三者の消費」構造から完全に無関係でいられるのでしょうか?
第三者の消費を否定することは簡単です。
そう、しかしながら、そこにこそジレンマがあります。
安価な商品を購入し、便利なサービスを利用するたびに、私たちはその構造の一端を担っている。
安定した社会システムの中で暮らすこと自体が、その外部化されたコストの上に成り立っている。
そう考えることも出来るのではないでしょうか。
だとするならば、程度の差こそあれど、我々は「動機なき者達」としてこの構造に組み込まれている共犯者なのかもしれない。
もしそうだとすれば、この構造を批判することは、自己否定にも繋がりかねません。
「社会構造そのものに組み込まれた不正義や不均衡によって、特定の個人や集団が物理的・心理的な剥奪や抑圧を受ける。」
ノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥングは構造的暴力という概念を提唱しました。
高度経済成長期の日本の繁栄、地方の疲弊や公害、それはまさに構造的暴力の現れだったのだと。
そう解釈することも出来るでしょう。
「社会システムは、環境との境界を引き、その内部の安定性を維持しようとする。」
ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンは社会システム論を提唱しました。
つまり、経済システム、政治システム、法治システムといった異なるシステムが、それぞれの論理に従って作動する。
そしてシステムにとって不都合な要素、すなわち「第三者」を環境として扱い、システム外部へと押し出そうとするのだと。
「システム内部の安定(「桃源郷」)は、システム外部(「第三者」)からの資源の搾取や、システムにとって有害な要素の排除の上に成り立っている。」
社会システムが自己維持のために、システム外部へと不都合な要素を「環境化」して消費していたのだと。
こうなってくるともはや人の手に余る状態です。
我々はこれからも無自覚に、悪気もなく、生きるために犠牲を糧としなくてはならないのでしょうか。
これまでの議論を踏まえ、我々は自身の立ち位置を内省していく必要があります。
【内省】
- 因果的な問い:なぜ我々は、他者の犠牲の上に成り立つ「桃源郷」を無自覚に求め、構造的な変革に抵抗してしまうのか?
・命題: 人間の本質は、自己の生存と集団の安定を最優先する利己的な存在であり、倫理的な配慮は二次的なものである。
・通説: 歴史を見れば、多くの集団は他者との競争や排除を通じて自らの繁栄を築いてきた。これは自然な人間の行動であり、構造的な変革は困難である。
・新説: 我々が構造的変革に抵抗するのは、単なる利己心からではなく、システムそのものが提供する「安寧」や「効率性」への依存、そして構造の見えない歪みにある。この構造的無自覚を可視化することが変革の第一歩となる。
- 新たに生まれる個人の命題:「第三者の消費」構造の中で、いかにして倫理的な主体性を保ち、責任ある選択を行うか?
・命題: 個人にできることは限られており、巨大なシステムの前では無力である。倫理的に振る舞おうとしても、構造を変えることは不可能だ。
・通説: 個人の倫理的な努力だけでは、構造的な問題は解決しない。政治や経済のシステム変革が必要であり、個人はそれに従うしかない。
・新説: システムは個人の行動の集合によって構成されており、個人の意識と行動の変化は、システムへの緩やかな圧力となる。倫理的な主体性の回復は、構造的な無自覚から脱却し、システムが提供する歪みを見抜くことから始まる。それは、不都合な真実から目を背けず、たとえ小さな選択であっても、その背景にある構造を意識し、倫理的な判断を継続する努力である。我々自身のレジリエンスを高めることが、システムの圧力に抗う力となる。 - 新たに生まれる社会の命題:「第三者を消費しない」包摂的な社会システムをいかに構築するか?
・命題:「第三者の消費」は資本主義システムに内在する問題であり、抜本的なシステム変革は不可能である。市場原理を維持しつつ、法規制やCSR(企業の社会的責任)によって構造的な問題を緩和するしかない。
・通説: 経済成長と倫理的な社会の両立は困難であり、どちらかを選ばざるを得ないトレードオフの関係にある。国際協調は理想論に過ぎない。
・新説: システム変革は、単一の政策や法改正だけでなく、デジタル・インフラの設計、多分野横断的な対話による規範の再構築、そしてノン・ルフールマン原則のように、誰一人として「環境化」しないという強い意志に基づいた国際的な連帯によって可能となる。それが、構造的暴力をシステム内から排除しようとする試みとなる。
【専門用語/学術用語の解説】
- アノミー (Anomie):
- 意味: 社会の規範や価値観が揺らぎ、個人が行動基準を見失い、無規範・無目的の状態に陥ること。社会的な統合が弱まり、逸脱行動などをもたらすとされる。
- 出所: フランスの社会学者エミール・デュルケームが提唱。
- フィルターバブル (Filter Bubble):
- 意味: アルゴリズムによる情報の選別で、ユーザーが自身の考えと異なる情報に触れにくくなる現象。
- 出所: イーライ・パリサーが提唱。
- エコーチェンバー現象 (Echo Chamber Effect):
- 意味: オンラインなどで同質な意見を持つ人々とだけ交流し、意見が増幅・強化される現象。
- 出所: メディア論などで用いられる比喩。
- 集合的無意識 (Collective Unconscious):
- 意味: 人類全体に共通する根源的な記憶やイメージの層。個人の意識や行動に無自覚な影響を与える。
- 出所: スイスの精神科医・心理学者カール・グスタフ・ユングが提唱。
- 構造的暴力 (Structural Violence):
- 意味: 社会構造そのものに組み込まれた不正義や不均衡によって、特定の個人や集団が苦痛や被害を受けること。
- 出所: 平和学者のヨハン・ガルトゥングが提唱。
- 社会システム論 (Social Systems Theory):
- 意味: 社会を相互に関連しあう要素(コミュニケーション)からなる自己組織化されたシステムとして捉え、その構造、機能、ダイナミクスを分析する理論。
- 出所: 生物学の一般システム理論などを背景に発展。社会学ではニクラス・ルーマンの理論が代表的。
- 構造的無自覚 (Structural Unawareness):
- 意味: 社会構造に組み込まれた搾取や排除が存在するにもかかわらず、その構造内にいる人々がその事実に気づきにくい状態。
- 出所: 社会学における構造分析や批判理論の文脈で用いられる概念。
- ノン・ルフールマン原則 (Principle of Non-refoulement):
- 意味: 難民を迫害の恐れのある領域へ追放・送還してはならないという、国際難民法における基本原則。
- 出所: 難民の地位に関する条約(難民条約)第33条に明記。
- レジリエンス (Resilience):

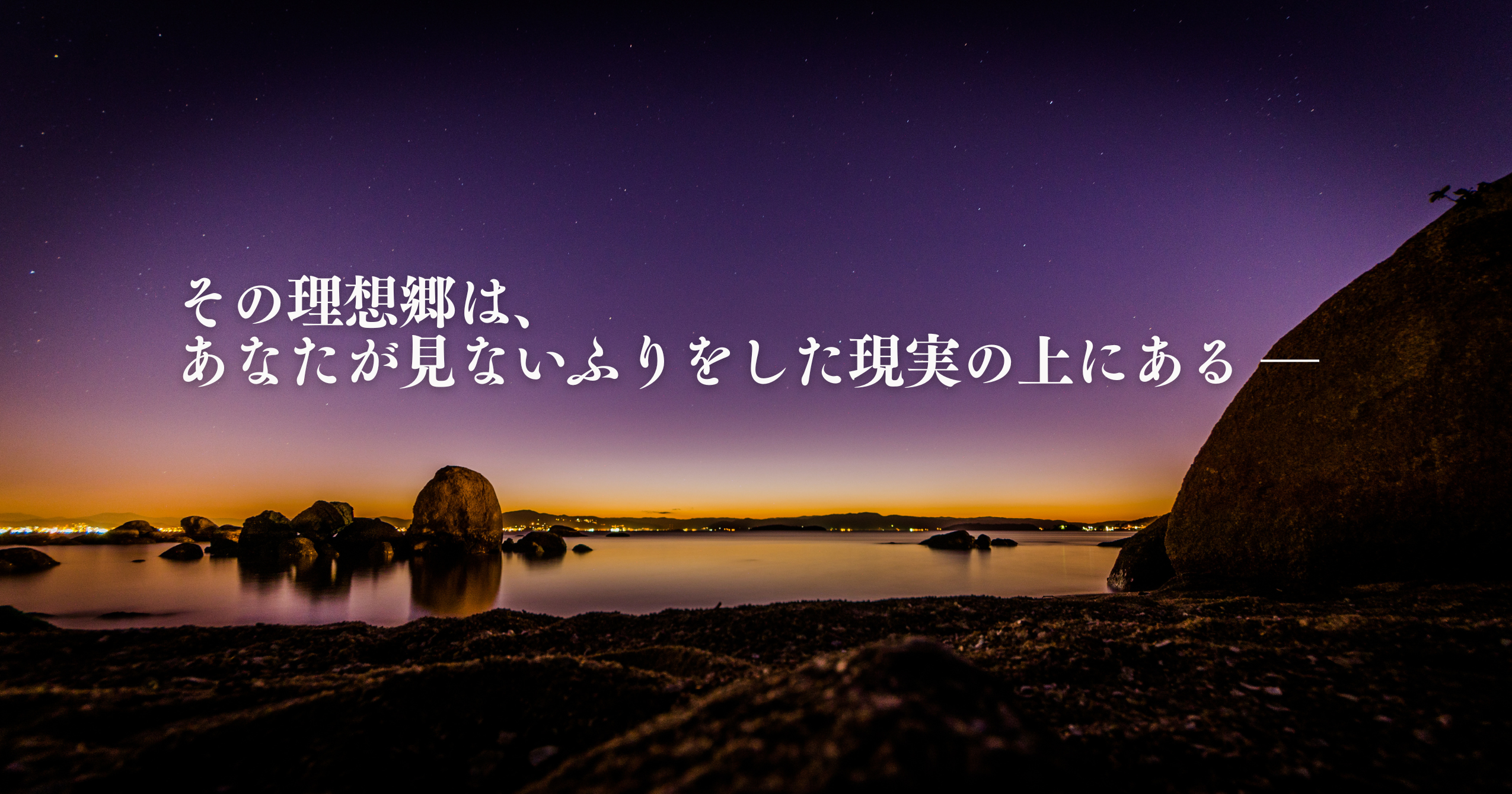
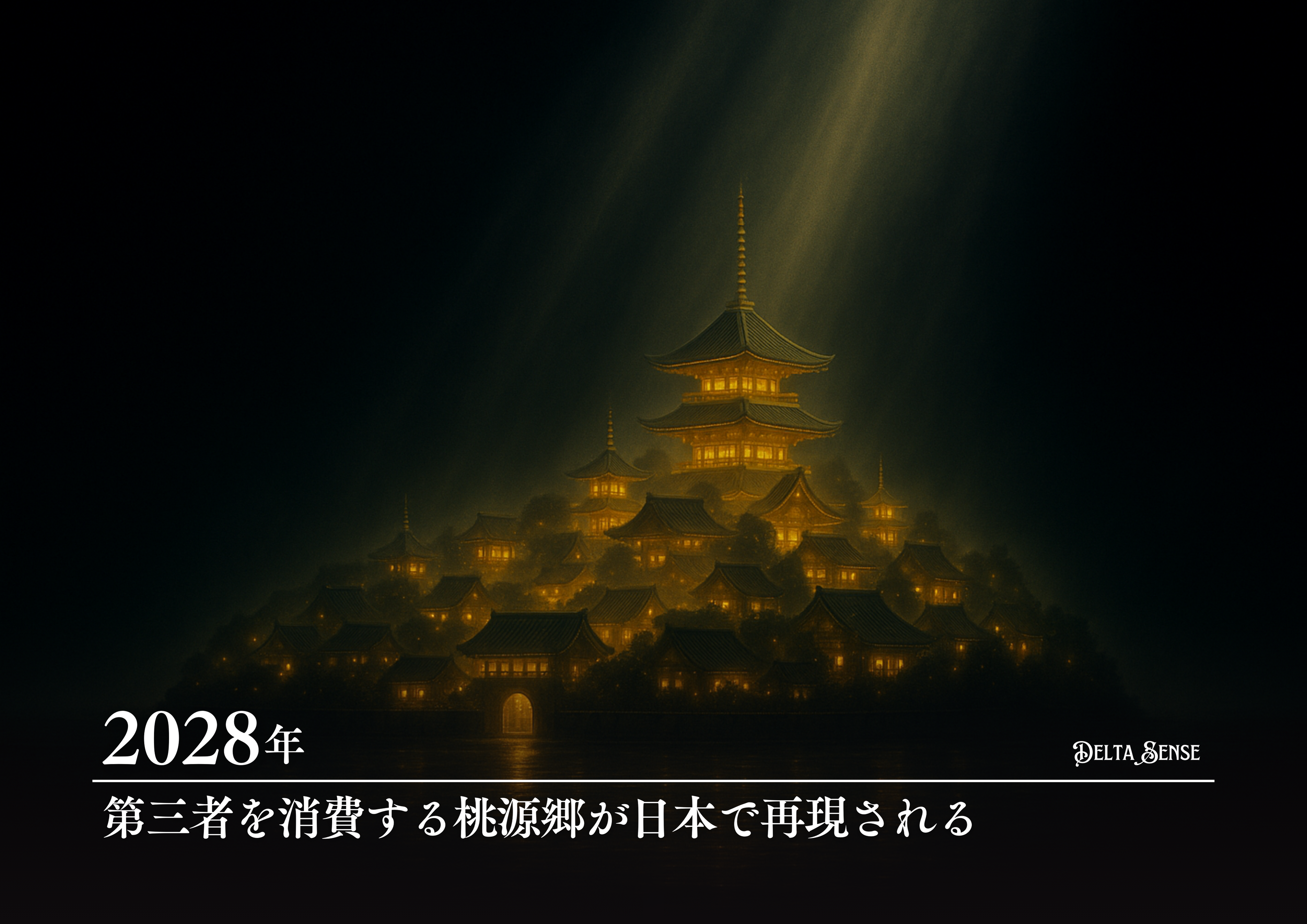
第三者を消費するという捉え方
資本主義社会である限り避けられないと思う。また、世界情勢の中での生き残りの戦略という面もある。
他の道はあるのか?
ex裁定取引、比較貿易論(リカードなど)
資本主義では常に市場の歪みをつく、その仕組み自体が誰かが犠牲になる面があるのではないか?
根底に奴隷文化があるのではないか?日本もそれ流れに染められつつあるのか?
現システムでの富の再分配の限界(経済格差拡大)
シン資本主義VSシン社会主義の権力争い
などの中で日本独自の道はあるのか?
そんなことを考えさせられました