問題提起
今後数年間でAIなどのテクノロジーによって失われる雇用は数千万件にのぼり、
同時に新たな雇用も生まれるものの、その質と求められるスキルは大きく変化するだろう。
―世界経済フォーラム―
「今、人類はかつて経験したことのない産業的・社会的な変革期を迎えている。」
その変革の中心にあるのが、目覚ましい進化を遂げる人工知能。
特に私たちの知的作業や創造活動の領域にまで踏み込んできた生成AIの存在です。
「AIは、知的労働や創造的な作業さえも代替する能力を獲得しつつある。」
それは、私たちの「働く」という行為を揺るがしています。
そして労働によって成り立ってきた社会の仕組みそのものに、根本的な問いを投げかけています。
「過去のデータを基に市場予測レポートを作成しておいて。AIだと早いよ。」
例えば、データ入力、経理、顧客サービスといった定型業務。
或いは、プログラミング、法律事務、金融分析、さらにはデザイン、記事執筆、翻訳など。
いわゆるホワイトカラーの知的労働やクリエイティブな分野もAIに代替され始めています。
「労働とは主に経済的な報酬を得るための手段であり、個人の社会における役割や自己実現は職業と強く結びついている。」
このAIによる労働代替の進展は、私たちの社会が長年前提としてきた通説を根底から揺るがすものです。
もしAIが人間よりも効率的に、そして低コストで多くの仕事を行えるようになったとしたら。
その時、人は、生活のために「働く」という直接的な必要性から解放されるかもしれません。
そう、この変革が行き着く先にあるものとは何か。
つまり、それは、「ポスト・ワーク社会」(造語)です。
多くの人が有給雇用に従事しない、或いはその必要がなくなる社会の到来です。
しかし、その時人間は一体何のために時間を費やし、何にエネルギーを注ぐべきなのでしょうか?
私たちは自身の存在意義や社会との繋がりをどこに見出すべきなのでしょうか?
ポスト・ワーク社会は、単なる経済構造の変化ではありません。
人間の労働観、価値観、そして哲学的な問いを私たち一人ひとりに突き付けているのです。
その変化と未来は、私たちにどのような影響を与えていくのでしょうか。
背景考察
「この社会は、「働く」という行為に、なぜ大きな価値を見出すようになったのでしょうか?」
それは、歴史的な文脈の中で理解する必要があります。
「産業革命以前の社会では、労働は主に生存と共同体の維持に直結していた。」
当時は、現代的な意味での「職業」や「雇用」といった概念は希薄だったと言います。
つまり、社会を成立させるために、各々が必要な役割と責任を全うするというものですね。
次第に工業化と都市化が進み、労働は個人の経済的自立と社会参加の基盤を得るための手段になります。
この時代、労働の価値は主に物理的な生産量や効率性で測られ、美徳は「勤勉さ」や「生産性」でした。
まさに、日本国の高度経済成長が「勤勉性」と共に語られていることからもハマりましたよね。
そのうち、電話交換機の自動化やコンピューターの普及といった技術革新が起きます。
それは、特定の職業を消滅させる一方で新たな産業を生み出し、労働市場の構造を変化させてきました。
「AIがもたらす変化は、これまでの技術革新とは質的に異なる側面を持っている。」
従来の革新は、人間の「肉体的な能力」や、ある程度の「定型的な知的作業」を代替するものでした。
それに対してAIは、「パターン認識能力」や「創造性」、「判断力」といった領域を代替します。
つまり、これまで人間固有と考えられてきた領域にまで踏み込んでいるということです。
さらにAIは、膨大なデータ学習から論理的な推論、そして人間の感情を認識・分析することでしょう。
それは、つまり、私たち人間の脳内で行われる複雑な認知プロセスの一部を模倣するということです。
そうなると、生産性や効率性を労働価値の主要な指標としてきた従来の経済学は限界を迎えます。
なぜなら、AIが人間よりも効率的で生産性が高いならば、人間の労働を測る意味が無くなるからです。
「労働時間」や「物理的な生産量」という基準で人間の労働を評価する理由が薄れるとは思いませんか。
だからこそ、ポスト・ワーク社会は、AIには代替できない人間固有の能力を発見/発明すること。
そして、新たな経済的価値が見出される必要があるのです。
「AIが物理的・知的な生産活動の大部分を担うポスト・ワーク社会で求められる価値とは何か?」
1つは、人間の労働の主要な形態が、他者の感情に寄り添い、共感を呼び起こす「感情労働」です。
他者との深い共感や人間的な繋がりを伴うサービスが経済的重要性を増すと考えられます。
例えば、AIは顧客対応マニュアルに基づいて、論理的かつ効率的にカスタマーサービスを提供します。
しかし、顧客が抱える複雑な感情、言葉にならない不安。
或いは人間的な温かさを求める気持ちに、AIはどこまで寄り添えるでしょうか。
日本文化は、他者の目を意識して行動し、自己抑制を重んじる「恥の文化」であり、
西洋文化は良心による自律的な行動を重視する「罪の文化」である。
―ルース・ベネディクト『菊と刀』―
日本人とは何者かという像が崩れ始めていることを象徴する出来事が続いています。
先日、大阪万博で土下座事件が起きましたが、本来の日本人はそのような対応を強制/称賛しません。
電車の中で踊る外国人よりも、それを煽って称賛/応援するフォロワーである日本人が気掛かりです。
本来は、たとえ拙くても共感を持って話を聞いてくれる人に深い信頼や安心感を感じていたはずです。
この、他者の感情に寄り添い共感を呼び起こす能力は、いずれ新たな経済的価値を生み出すでしょう。
もう一つは、AIが生み出す膨大なデータやアイデアを無意識的に再構成する「無意識編集」(造語)です。
前回の記事でジブリ風の画像が大量生成される現象をお話しました。
AIはネット上のあらゆる文化要素やアイデアを学習し、それを基に無数のバリエーションを生成します。
しかし、AIが生み出すのは、あくまでデータとパターンに基づいた組み合わせです。
私は、人の内面的な経験、感情、閃きから生まれる「予期せぬ創造」にこそ価値があると考えます。
「最後は自身の勘や直感で選んだ結果、それが最善の道だった。」
過去にあなたもそんな経験をしたことがあるのではないでしょうか。
イメージの断片、言葉の組み合わせ、音響パターン。
AIが生成する膨大な情報は、洪水と見ることもできますが、閃きの素材と見ることもできます。
つまり、意識的な意図ではなく、個人の無意識的な嗜好や経験と共鳴する要素を選び出し創造すること。
それは、人のライフストーリーが密接に関わるため、独自性の宝庫になり得るかもしれません。
データ分析に基づいて最適な配色や構図を提案するAIのデザインツール。
料理人が長年の経験と直感に基づいて食材を選び、味付けを調整するプロセス。
例えば後者は、合理性だけでは説明できない、人間の無意識や感性による「無意識編集」の賜物です。
言ってしまえば、AIが自己意識を持たない限り辿り着けない領域です。
そこには、価値が見出される意義があるのではないでしょうか。
私たちの内面的な世界、すなわち「感情」や「無意識」といった領域。
それらは、ポスト・ワーク社会における新たな「労働価値」の源泉になると考えます。
とはいえ、この希望の光の裏側には、深い影が潜んでいます。
「感情」や「無意識」を駆使する人とそうでない人との間に新たな社会格差が生じるからです。
しかも、能力開発ができるか疑わしい領域のため、固定化される危険性も孕んでいます。
例えば、他者への共感や人間的な温かさを持っている姿を演じる人も登場するでしょう。
すると、感情はどこまで「本物」で在り続けられるのか、といった問いも生じると考えられます。
また、常にAIの予測を超える「無意識編集」を求められるプレッシャーも生じるでしょう。
すると、「創造性枯渇症候群」が蔓延して、ストレス過多が慢性的になる可能性も否定できません。
「すべての人々が人間としての尊厳を保ちながら生きていける仕組みを構築出来るのだろうか?」
ポスト・ワーク社会という未知の領域は、私たちに大きな問いを投げかけています。
【内省】
- 因果的な問い:
もしもAIが生産のほとんどを担えるほど賢くなった場合、我々は何のために「働く」のでしょうか?
- 新たに生まれる個人の命題:
・通説:
労働とは、経済的な報酬を得るための行為であり、個人のアイデンティティや自己実現は、特定の職業に就き、スキルを磨き、社会に貢献することで確立される。キャリア形成は、市場価値の高いスキルを習得し、昇進を目指すプロセスである。
・新説:
AIによる労働代替が進むにつれて、個人のアイデンティティや自己実現は、経済的な報酬とは切り離されて、内面を探求する活動の中に見出されるようになる。キャリア形成は、自身の内面世界を深く理解し、それを他者との共鳴や創造的なアウトプットに繋げるプロセスとなる。 - 新たに生まれる社会の命題:
・通説:
社会は、人々の労働によって生産される富を分配し、経済的な成長を通じて発展する。社会保障制度は、労働できない人々を支援するためのセーフティネットである。教育システムは、市場で求められるスキルを習得させ、経済的な自立を促すことを目的とする。
・新説:
社会全体の富はAIによる効率的な生産によって生み出される。社会保障制度は、人間の感情的・創造的な活動を支援する基盤となる。教育システムは、市場価値の高いスキルだけでなく、人間の感情を理解し、共感する能力、そして無意識的な創造プロセスを支援・育成することを目的とする。
ポスト・ワーク社会における感情と無意識編集。
それは、AIがもたらす労働と価値の変容という、私たちの社会の根幹を揺るがす壮大な物語です。
しかし、その変化がすべての人々にとってより良い未来へと繋がるかどうかは別の問題です。
あなたのスマートフォンに届く、感情に訴えかけるAI生成メッセージ。
それは、単なるデータやパターンに基づいて作られたものなのでしょうか?
それとも、AIがあなたの内なる「無意識」に触れ、眠っていた感情を呼び覚まそうとしているのか?
あなたが誰かの心に寄り添い、共感の涙を流すような瞬間。
その時の一瞬の感情は、テクノロジーの力で、お金で買えるものになってもよいものでしょうか?
人間の労働、価値、そして存在意義に関する問い。
この問いに対する答えは、まだ誰も知りません。
私たちはその価値を、何と引き換えに手放すことになるのでしょうか。
この問いへの答えを探求する旅路こそが、ポスト・ワーク社会における壮大な物語となるのかもしれません。

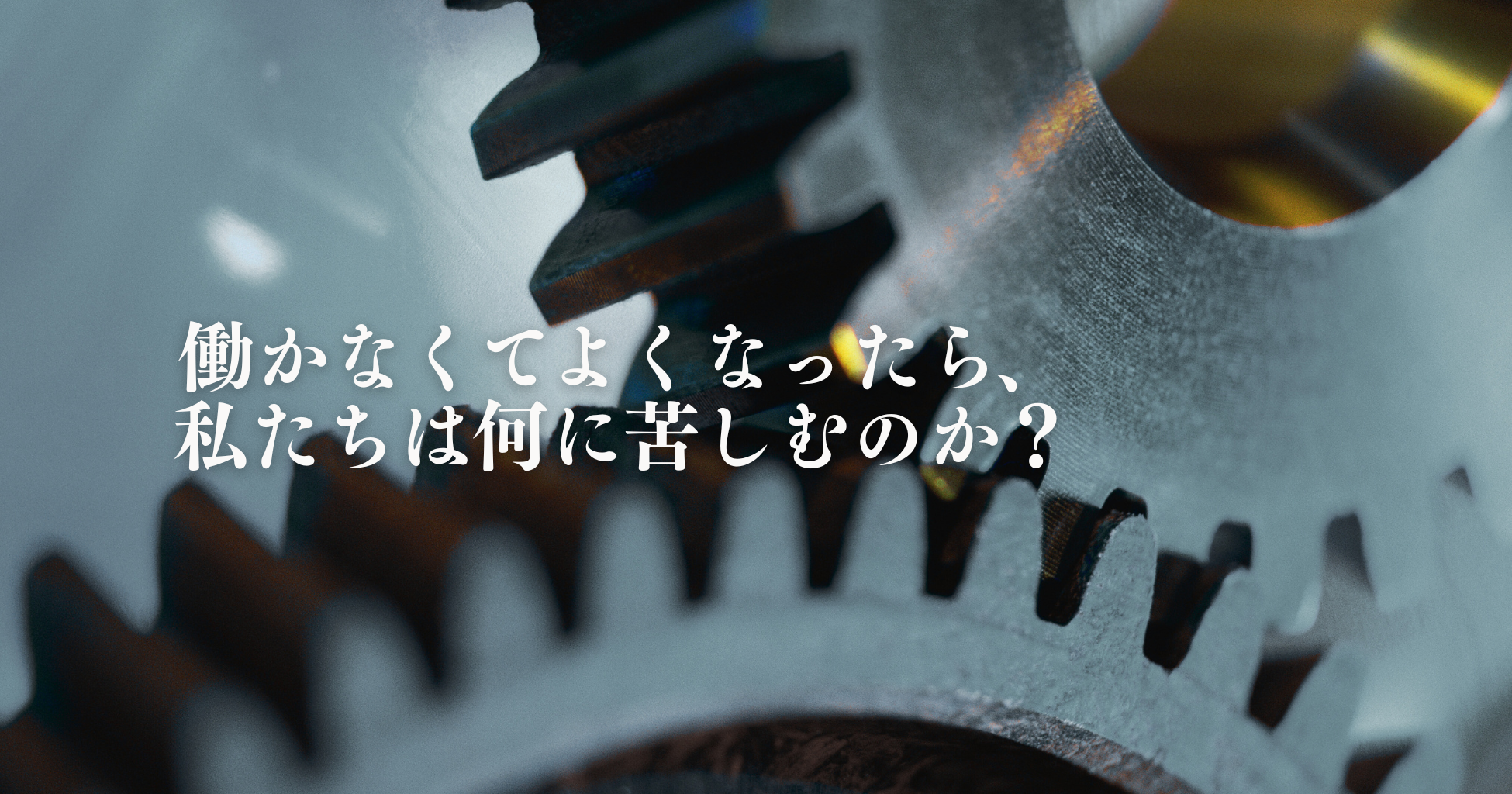
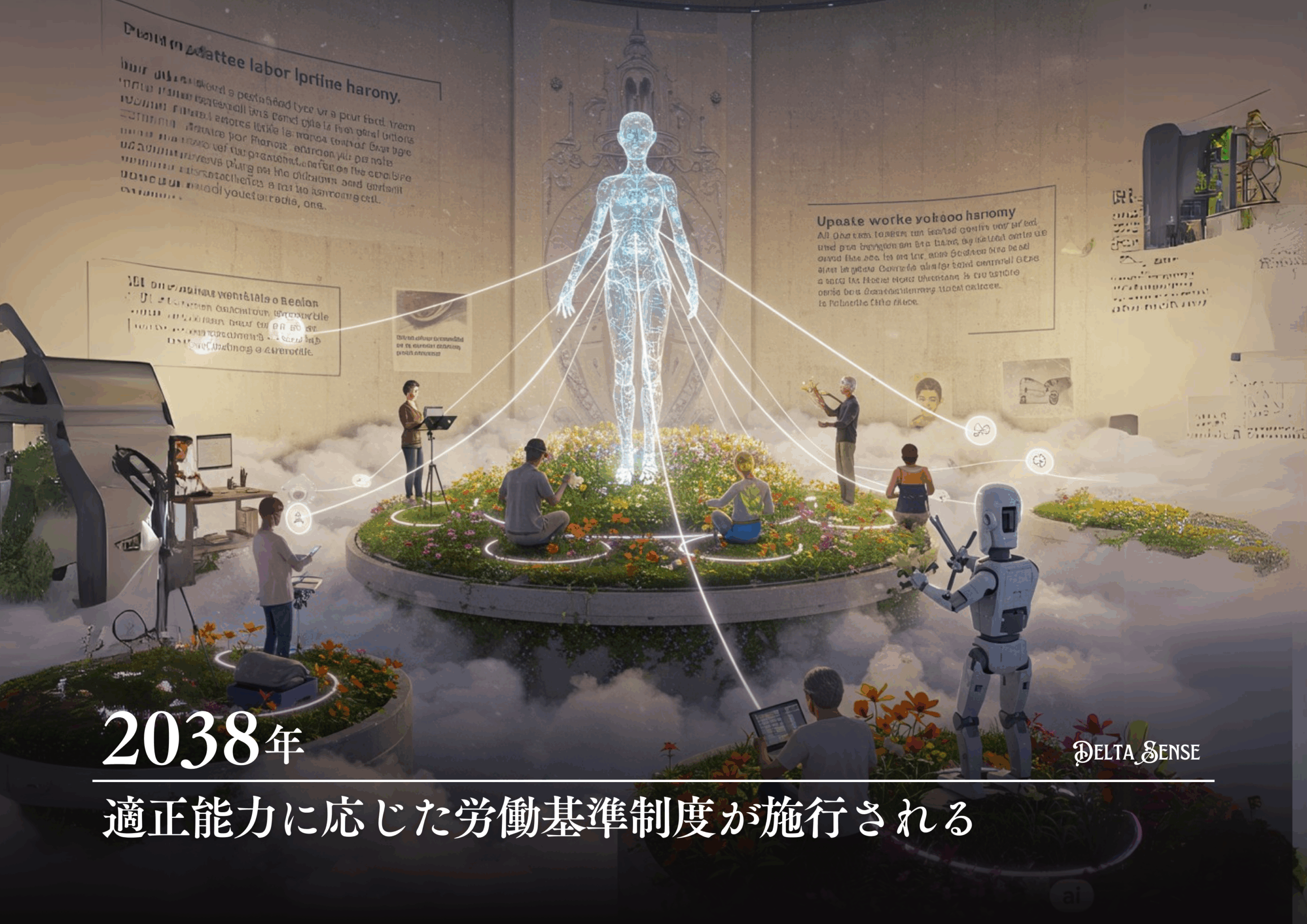
AIが人間の仕事を代替した時にどのくらいの人が職がなくなるのか?
また、その人たちを吸収できる産業があるのか?
AIが社会に普及し、社会が変化するときに
その変化に今の社会制度は適応できるのか?
など課題があるが今後AIが社会のあらゆるところで活用されるようにはなっていくことは間違いないと思う
ただ、現実と矛盾していると感じるところは人不足、インフレだが肌感覚は給料が十分に上がっていない、景気がよい感じではない。
AIが入ったところで格差が固定化され、富の分配がより、かたよるのではないかと考えた