問題提起
2023年10月7日以降、イスラエル社会では、死後の精子採取に「空前の需要」が起こっている。
フィナンシャル・タイムズ紙は、これは次の3要因が組み合わさったことによるとしている。
第一は、「喪」だ。「喪を先送り」し「何かにすがる」方法として死後受胎を選ぶ遺族もいるとノガ・フックス・ワイツマンは述べている。
第二は、「生殖技術」だ。イスラエルは、生殖技術の分野で世界を牽引している。
体外受精の数は、国民1人当たりでは世界最多だ。
45歳(卵子提供を利用する場合は51歳)以下の女性にかかる体外受精の費用を2児まで、無制限に国が負担する唯一の国でもある。
第三は、「出産奨励主義」だ。イスラエルでは、「誰もが子供を持ちたがっていると考えられている」という。
「ホロコースト後のユダヤ民族再生を誓って建てられた」国では、「家族の存続こそが至上」なのだ。
―クーリエ・ジャポンー
「人間は、生を終えた後にもなお“何か”を遺したいと願うものなのでしょうか。」
その“何か”が、現代においては生殖技術によって「次世代の存在」に姿を変え、亡くなった人々の遺志を延長する一つの手段として用いられるようになりつつあります。
ことに戦争や事故で命を絶たれた人々の精子が、遺族の希望によって保存され、次世代を育む役割を与えられるという事実。
それは、私たちに新しい死生観をもたらす可能性があります。
もし死後生殖技術の合法化が先進国を中心に進んだ場合、生者と死者、そして新たに生まれる子供たちの関係性はどのように再定義されるべきなのでしょうか。
そこには、個人の価値観、社会的な倫理観、そして法的規制のバランスという難問が横たわっています。
この取り組みは未来の私たちにどのような影響を与えていくのでしょうか。
背景考察
イスラエルは政治的危機と聖俗間の緊張が原因で、分裂した状況にある。
だが、子供を産むことの重要性と軍の神聖性という2点で、ユダヤ系イスラエル人の圧倒的大多数の意見は一致している。
世界の豊かな国が集まる経済協力開発機構(OECD)の加盟38ヵ国のなかで、女性1人が一生に3人以上の子供を生むイスラエルの出生率は、他国を大きく引き離している。
次に多いトルコとメキシコでも、出生率はイスラエルより1近く低い。
国民1人当たりのGDPがもっと近い国々では、出生率はイスラエルのほぼ半分だ。
イスラエルの人口は過去30年間でほぼ倍増して950万人に達しており、今後30年もほぼ同じペースでの増加が予想されている。
―クーリエ・ジャポンー
「重要なのは、それがただの遺産ではないということ。」
まるで時の砂時計のようなもので、亡くなった人々の記憶や愛情が風化することなく、砂粒の一粒一粒が未来に受け継がれていく。
亡き者の精子を用いることは、彼らの「存在の延長」としての意味を持ち、未来の砂時計に新たな一粒を加える行為に他なりません。
しかし、言い換えればそれは、物資的な遺産ではなく、透明な遺産(造語)という生命の根幹に関わるものです。
例えば、ある家族が亡き息子の精子を用いて孫を得たいと望む場合、その意図は単に血を絶やさないためだけではありません。
そこには、息子の記憶を「生ける記念碑」として後世に残したいという遺族の切実な思いが宿っているのです。
しかしその一方で、死者(亡き息子)の遺志とは無関係に、遺族が主体的に決定を下すことで死者の遺志を損なう結果をもたらす可能性があります。
例えば、亡き息子が愛して守りたいと望んだ女性を遺族が何らかの理由を付けて見放してしまえば、その遺志は永遠に果たされないでしょう。
或いは、別の家族がその遺族の精子(亡き息子)を得て出産した場合、遺族の切実な思いとは真逆の結果をもたらす可能性も想像出来ます。
例えば、祖国のために戦った勇敢な息子のDNAが、触法少年(日本は20歳以下)と扱われる期間に子どもギャングの一員として殺人を犯すこともあるでしょう。
実際に子どもギャングや青年ギャング問題は世界で大きな問題になっています。
例えば、多文化共生を推進する福祉大国と称賛されていたスウェーデンは人口約1000万の内、約200万が移民です。
国民も移民も難民も平等に個人税率を上げて法人税を下げるという、今の日本と同じようなこと(消費税上げて、法人税を下げる)を進めた結果、何が起きたのか。
多文化共生と多様性を認める政策で世界から絶賛されていたのですが、その実態は残酷です。
「どれだけ学ぶ環境を整えても、本人の意志が無ければ意味を成さない。」
寛容なお国柄と福祉に甘えてフリーライドすることを目的にした移民と難民は、スウェーデンの文化と折り合うつもりがそもそもありませんでした。
そう、学業を修めることも文化を学ぶこともせず、まず「可哀想な自分たちを認めてもらうこと」を優先して来たのです。
「どこまで配慮すれば認めたことになるのだろうか?」
その答えが誰にも出せず、スウェーデン語を理解出来ず就職難に苦しむ外人と良質な教育で高付加価値の仕事に従事する国民で分断されていきます。
すると経済的困難と社会的孤立に苦しめば苦しむほど、フリーライドの外国人は「自分たちの文化を残そうとする」ので、ますますスウェーデン文化を無下にします。
そして自分たちが苦しいのはスウェーデンの責任だとして、反スウェーデンで団結してギャング集団を組織しました。
地獄の始まりです。
まずは罰則されない触法少年(15歳以下の子ども)を用いて、競合企業の経営層を契約殺人で処理して非合法な手段で収入を手にします。
その金で学校や病院、老人ホームというインフラ事業の経営に乗り出して合法的な企業を設立しました。
証言によれば、触法少年は1回の殺人で1000万円を手にすると言います。
また調査によれば、ギャングに関わる95%が外国人です。
犯罪でお金を稼ぎ、そのお金でインフラ事業を展開して、あたかもスウェーデンを思いやるかのような顔をしますが、その実態は違います。
この事態を鑑みて、「スウェーデンは国家として崩壊してしまった。」という旨を首相も明言している深刻な状況です。
今、日本では望まない妊娠が社会問題になっており、誰にも頼れずに孤立出産し、赤ちゃんを遺棄したとして女性が罪に問われる事件が絶えません。
また、人工妊娠中絶に至ることも多く、中絶にいたった理由として「パートナーが産みたくないと言った」「今回のパートナーと結婚・育児する気はない」「仕事がある」などの理由が挙げられます。
そして体裁を繕うために出来ちゃった結婚をした場合、養育の放棄や児童虐待問題に発展することが指摘されています。
「誰の声かも確かめずに、世間やネットの声に流される国民性が日本人の特徴だ。」
さらに言えば、義務教育を否定して登校拒否する子どもを称賛する文化も形成されつつあります。
SNSの声が誰の声なのか、少数派だとしてもネットで拡散されればいずれ多数派になる可能性があります。
そう、つまり、子どもギャングが猛威を振るう下地が固まりつつあると言えるでしょう。
子々孫々で受け継がれるDNAやミームがどれだけ崇高なものであったとしても、恣意的な思想が入り込めば全く違う将来を招きます。
本人にはどうすることも出来ない環境上の制約によって、過去や遺志とは真逆の結果を招きうる存在、それが相反孤児(造語)です。
透明な遺産は、一歩間違えれば相反孤児を誕生させる危険性を孕んでいると考えることが出来るでしょう。
「透明な遺産から生を受けた子どもは、誰のために生きるのだろうか?」
亡き者の精子が冷凍保存され、生きる者のために再利用されるという現実は、死者が「現実の中で生き続ける」新たな形を象徴しています。
言い換えれば、父親の遺志が社会の中で生き続ける一方で、その子どもは「自分の生を望んだ、恣意的な他者の期待を満たすための器」として存在するようなものです。
「あなたは特別なのよ。」
英雄のDNAを継いで生まれた子どもは、アイデンティティをどのように形作り、またどのようにして自己の存在意義を見出していくのでしょうか。
彼らは、亡き父親の意志を継ぐべく生まれたのか、それとも遺族の希望のために存在するのか。
生物学的には自由で独立した意志を持つはずが、社会的には特異な立場に置かれ、社会的認知の中で自我を保てなくなるという懸念があります。
「誰が救えるのか、誰が寄り添えるのか、そもそも救えるのだろうか?」
自己が空白のまま、ただ他者の夢や欲望のために形づくられた存在であることに葛藤する子ども。
つまり、望まれた妊娠ではありますが、望まれすぎた妊娠(造語)という新たな問題が浮上すると考えられます。
「亡き者の意志はどこまで尊重されるべきか?」
望まれすぎた妊娠を回避するためにも、死後に遺された生殖細胞を利用する権利は、遺族にとって重要な問題となるでしょう。
現状では、遺族の希望によって実施が許容される場合も多く、法律によって厳格に管理されているわけではありません。
もしも死後生殖が当たり前になった場合、遺伝子は「個人の遺産」としての価値を持ち始め、物質的財産と同等の意義を持つ新たな文化が生まれる可能性があります。
つまり、遺伝子を「記憶を継ぐ遺産」として捉える考え方は、死者の遺志を生者の中に生かし続ける新しい死生観の構築に寄与するということです。
例えば、その流れが加速すれば、DNAが遺産として「財産権の対象となる未来」も考えられます。
伝説のバンドBeatlesのジョン・レノンを惜しみ、その影を息子のショーン・レノンに見たファンは多いでしょう。
『圭子の夢は夜ひらく』で有名な藤圭子の面影を宇多田ヒカルに重ねたファンも多いでしょう。
「もしも将来、天皇が女性となり、その花婿に選ばれた者が実は中華系の血を有していた場合、皇族の血統はどうなるのだろうか?」
そう、まさかとは思いますが、弱った日本が中国に朝貢したという、政略結婚したのだという既成事実が語れる日が来る可能性だって否定出来ません。
もしも遺伝子が「国家遺産」として位置づけられることになれば、遺伝子の持つ社会的価値はさらに高まり、家族間の文化や儀礼としての新たな価値体系が構築されるでしょう。
名前で客が呼べるような影響力や国家を揺るがすような血統。
その渦中で相反孤児となった子どもたちは、独自のコミュニティを形成し、自分たちの生き方を新たな社会の一翼として正当化していくでしょう。
つまり、「生殖選択の自由権と家族の意志の境界線が曖昧であること」は大きな騒動の引き金となるため、今後の法的な整備が求められます。
「遺伝子の延長として存在する未来世代にとって、自らの命は何を意味するのか、そしてそれは誰が決めるのか?」
作られた命の問題はクローン技術で生まれた場合も同様です。
個々の存在意義は他者によって決定されるべきなのか、或いは自己のアイデンティティと自由意志が尊重されるべきなのか。
「誰かの役に立ちたい、誰かのために生きること。」を称賛する多文化共生と多様性の時代。
もっと真剣に、その意味を考える必要があるなと。
そんなことを考えさせられました。

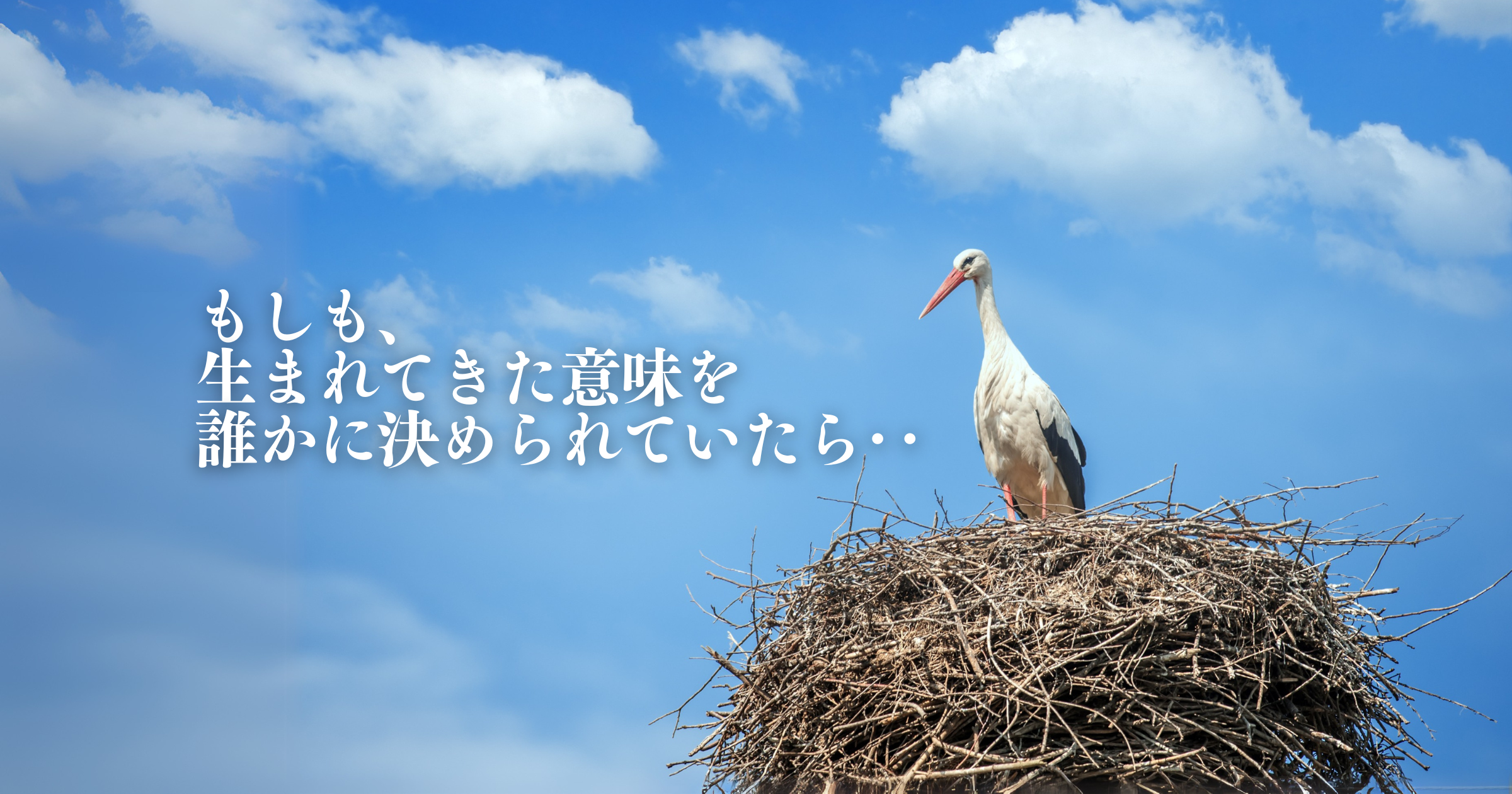

この記事へのコメントはありません。