問題提起
日本企業が、強硬なアクティビストによる厳しい要求への対応や、批判を強める年金基金の懐柔、
あるいは資金力のある正当な買収者に対する独立性の維持について、アドバイザーに相談を持ちかけている一方で、
証券会社や銀行は、企業価値が低くガバナンスが劣る企業のなかで、どこが最も脆弱な標的になるかを示すリストの作成を着々と進めてきた。
「もはや、どの企業も安全ではありません。本来そうあるべきなのです。
日本は非常に安価で流動性が高く、買収ターゲットが豊富な市場です」と、
CLSA証券の日本担当ストラテジスト、ニコラス・スミスは指摘する。
―クーリエ・ジャポン―
「利益のために、何を犠牲にできるか?」
この問いは、経営者にとって決して新しいものではありません。
しかし、近年のコーポレートガバナンスの潮流がこの問いをより一層鋭利なものへと研ぎ澄ませているように思います。
「利益率の低い部門を切り捨て、株価を上昇させるべきだ。」
2024年、アメリカの著名アクティビスト・ファンドが日本の老舗企業に対し、大規模なコストカットと事業のスリム化を要求しました。
理由は明確です。
「短期的な株主価値を最大化するために、従業員の雇用や地域社会への責任を切り捨ててよいものなのか?」
アクティビスト・ファンドの台頭は、企業経営の在り方を根本的に揺るがし、経営者に選択を迫ります。
だが、その部門こそが、数千人の雇用を支え、地方経済の要となる存在だったのでした。
まだ造語ではありますが、近年は「フィデューシャリー・デッドロック(受託者義務の袋小路)」という現象が増えつつあります。
現代の企業経営者は、どこまで資本市場の論理に従うべきなのか。
そして、企業は本当に株主のもので良かったのか。
「利益と責任の境界線」に経営者たちは揺れ動いています。
こうした現象は未来の私たちにどのような影響を与えていくのでしょうか。
背景考察
コーポレートガバナンスの形骸化や不適切な資本配分、そして慢性的な株主利益の軽視といった問題は、もはや隠し通すことが難しくなった。
「同意なき買収」という国家公認の概念が登場するなど、市場は新たな脅威をもたらす場所と化している。
―クーリエ・ジャポン―
かつて、企業とは長期的な視点に立ち、地域社会や従業員と共に歩むものでありました。
こと日本においては、「会社は株主のものではなく、社会の公器である」という考えが支配的だったように思います。
しかし、この哲学は次第に崩れつつあります。
「2030年代に、ファンド資本主義の全盛期が到来するのではないか?」
2020年代に入り、アクティビスト・ファンドによる企業介入は急増しました。
日本企業も例外ではなく、過去5年間で50社以上が敵対的買収の標的となっています。
特に、PBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る企業は「非効率経営」と見なされ、改革を求められる対象とされます。
ファンド関係者に言わせれば、株主価値を高めることが正義とされ、そこに社会的要素が入り込む余地はないと言います。
しかし、この流れに異を唱える動きもあります。
2024年、ある地方都市に本社を構える食品メーカーは、アクティビストの提案を拒絶し、「地域雇用を維持すること」を優先したのです。
この決断は一部の投資家の不興を買いますが、地域社会からは絶大な支持を受けました。
「企業価値とは、本当に株価だけで測られるものなのか。」
我々は改めてこの問いについて、考えさせられる事態に直面しています。
「利益追求のために共有資源が過剰利用されると、社会全体に損失が生じる。」
アメリカの生物学者ギャレット・ハーディンは、「コモンズの悲劇」を提唱しました。
それは、まさに企業経営も同様と言えるのかもしれません。
短期的な利益の最大化を求めるあまり、従業員や地域社会という「無形資産」が軽視されれば、企業の長期的な存続そのものが脅かされるのだと。
こうした構造的問題に対処するため、新たなガバナンスモデルが模索され始めています。
例えば、将来ある多国籍企業がアクティビスト・ファンドへの対抗措置として、「トリプルライン経営宣言」を提唱するかもしれません。
それは、「財務パフォーマンス」「人材育成」「地域貢献」の3要素を同時に改善することを目指した指標です。
中長期的に企業を持続繁栄せしめるのは「人の力」に他ならないという、AI全盛の時代にあえて「力強い人間讃歌」を謳うことが共感を誘うことでしょう。
当然アクティビスト・ファンドからは「株主軽視であり、企業価値を損ねる。」と声が挙がることでしょう。
とはいえ、この一件が象徴するのは、二項対立を超えるための新たな世界観への兆しです。
言い換えれば、アクティビストと地域社会、そして企業の間にある緊張関係は、避けられない対立ではなく、新たな価値創造の契機となり得るということです。
つまり、それは、「株主至上主義」と「社会的責任」のどちらかを選ぶのではなく、両者を包摂する新たなフレームワークが必要だということです。
ここで鍵となるのは、トリクルダウンにも近い考え方である、「ダウンストリーム・コミュニティ・ファンド」(造語)という発想かもしれません。
それは、企業が原価管理やバリューチェーンの最適化の一環として、地域社会への投資を行う仕組みを組み込むというものです。
なぜなら、これまではアクティビスト・ファンドによる株主価値の最大化という要求が先立っていました。
これにより、地域雇用や社会的責任を担う企業の狭間で生じる「フィデューシャリー・デッドロック」が課題になっていたと。
そこで、将来的には「財務パフォーマンス・人材育成・地域貢献」という“三本柱”を同時に維持すべきだという論調のファンドも登場するのかなと。
すると、従来のように、捨てるべきものを捨てて株価を上げるのか否かで、深刻な選択を迫られるという経験を我々は目にするのでしょう。
その経験があればこそ、「ダウンストリーム・コミュニティ・ファンド」という概念が実態を帯びて登場するのではないかと。
企業が地域社会や各家庭と協働しながら長期的な価値を生み出す試みは、地域社会や文化規範が整っている日本にとっては最適解になるのかもしれません。
「そんなの無茶だ。ヒト・モノ・カネの経営資源に投資すべきで、法則を越えている。」
とはいえ、新しいことに批判は付き物ですので、新たなガバナンス手法に対して、マーケットはしばしば冷ややかな反応を示すでしょう。
より具体的にいえば、株価評価軸は依然として短期的な指標に寄りがちであり、「地域に投資しても回収可能なのか?」という懐疑が常に付きまとうからです。
では、もしそんな世界が訪れたとしたら。
具体的に企業の“現場”ではどのようなジレンマが発生し、そこにアクティビストはどのように介入してくるのでしょうか。
後編では、本件に関わるステークホルダー達に視点を当てて、より未来を身近に引き寄せたいと思います。
それではまた、後編の②でお会いしましょう!

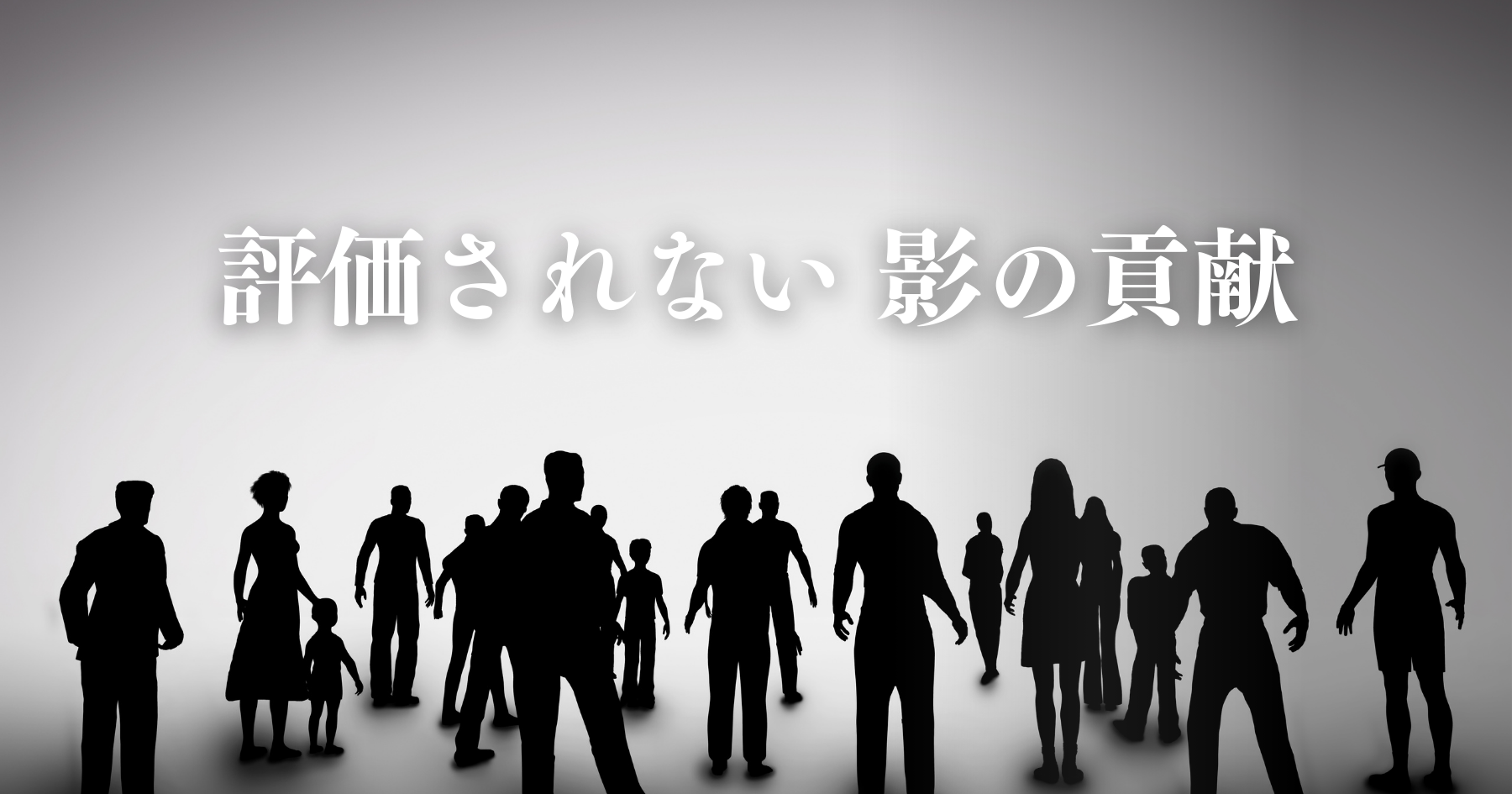

「会社は誰のものか?」
「会社が社会に果たす役割はどうあるべきか?」
このような問は20〜25年くらい前は話題になっていた気がするが最近はめっきり聞かなくなっていた気がする。つまりは「会社は株主のもの、株主の利益が最優先されて当たり前」という考えが当然、として定着してきたためかもしれない
そういった中で財務、人、地域といったことが投資基準になり、行き過ぎた株主資本に揺り戻しが起きることは良い流れであると思う
株式を上場することが膨大な資金調達の手段となったり、社会的に認められたり、時価総額を高めることが大企業としてのステータスだったり、と利点もあるが、欠点としては常に買収リスクに晒され、自身の経営権も持ち株比率により制限されてしまったり、ある程度の情報公開を市場に求められたりと注意しなければならない部分もある。
資本力のある、特定の外国ファンドがあらゆる国の主要な企業の株主になっている現状は非常に問題であると考えている。国を超えて様々な企業を支配しているようなものだからだ
その支配された企業たちが、大株主のファンドの意に反することはできるのだろうか?
日本的経営は今になっては死語になってしまったが、振り返ると合理的で社会的にも合致していたのではないか?
取引先との株の持ち合いは強固な取引先との関係になるとともに買収防衛にもなったはずだし、終身雇用・年功序列は後輩の教育やファーストプレイスの役割を果たし、従業員の自己肯定感のよりどころになっていたはずだし、企業別労働組合は「物言う株主」よりも身内での話し合いであるから経営陣と従業員、お互いの意見のぶつかり合いで企業の発展に寄与していた可能性もあるし、従業員たちの利益=地域の利益にもなっていたのではないか?
こうして考えると令和に合ったシン日本的経営が今だからこそ求められているのかもしれない
日本式経営と海外のアクティビストファンドとの対比が描かれていたかと思うがどちらにも良い点がある。
しかし実際地方都市の地元企業の場合、商圏も減り文化も廃れていき経済的にも厳しいという状況になるとファンドのいうことを聞かざるを得ない状況になっていると思う。
だからこそそういった日本企業に対しての応援を募る活動や、「日本式株式市場主義」を確立し老舗の日本企業にアドバイスできる第三者機関みたいなものができ(無知なので既にできていたらすみません)なるべく日本の技術や文化を海外の企業に渡さず、かつ発展できる場を設けられたらいいなと思います。
Q、「利益と責任の境界線」に経営者たちは揺れ動いています。
こうした現象は未来の私たちにどのような影響を与えていくのでしょうか。
A、短期利益を追求する株主優先の企業経営 vs 長期的な価値を見出し中長期にわたる利益を大事にしようとする社会貢献を意識する企業経営の考えが生まれると思っております。
また、今まで株主からの経営者に求めていた経営指標などのあらゆる数値化もまた、目に見えない過程軸に評価をおいてもいいんじゃないかという未来も出てきて経営者の再定義といった影響がでてくるなと思ってます。
なので、思うに、経営者は今一度、ビジョン、ミッションなどのパーパスといった存在意義を問われる未来が来ると思います!