今回は、「デジタルデトックス」の観点から、「社会的権利」の所有について考察していきます。
問題提起
iPhoneの使いすぎで虚しさと苛立ちを感じていた私は、この5年間、スマホの機能を基本的なアプリだけに削ぎ落としてきた。
真っ先に削除したのはSNSだ。続いてEメール、ニュースアプリ、果てはウェブブラウザまで……。
機能を減らすたびに解放感が増し、スマホをチェックしたいという飽くなき衝動も徐々に薄れていった。
―クーリエ・ジャポンー
「私たちの眼の前には、不便という贅沢を選ぶ権利が用意されている。」
近年、「デジタルデトックス」という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。
デジタル依存による精神的な疲労を軽減し、私たちを自己発見と充実した人生へと導く可能性があるという触れ込みで。
「かつてはオフラインで育まれた人間関係が当たり前だったが、今やスマートフォンやSNSを通じて、断片的な交流が常態化している。」
現代人は多くの「友人」を持つが、その友情は希薄で、触れることのできない幻影に過ぎないと。
つまり、実際にデジタルデトックスを試みる人々の多くは、情報過多に苛まれ、心の静寂を求めている層だと言われています。
「アナログを選ぶ権利は、用意されているものの世界から歓迎されていない。それが現実だ。」
アナログは尊いけれども、デジタルが正義になっている世界。
そんな中で、デジタル社会における個人の「選択の自由」というものが本当に存在するのでしょうか。
デジタルデバイスが不可欠となった現代生活は、実は私たちの選択の自由を奪っているのかもしれません。
それは、未来の私たちにどのような影響を与えていくのでしょうか。
背景考察
【ガラケーで得た最大の喜び】
予想どおりガラケーは不便だが、それこそが狙いだった。たいていの不便というものは、実はとても心地良いものなのだ。
ショートメッセージの入力は恐ろしく手間取るので、代わりに電話をかけて、5分程度の楽しい会話を重ねるようになる。
一日中、それの繰り返しだ。
お薦めレストランの情報は、「イェルプ」のようなグルメアプリではなく、近所の人とおしゃべりしながらゲットする。
スーパーでレジ待ちしているときは、スマホをいじる代わりに店員さんと会話する。
初めての場所へドライブするときは、家で地図を調べてから出発し、あとは成り行きに任せる。道に迷うこともあるが、それも望むところだ。
これがガラケーを持つことの魅力的でロマンチックな側面である。
より多くの会話、より多くのアイコンタクト、より多くのつながり。
これこそが、ガラケーに切り替えることで得た最大の喜びでもある。
―クーリエ・ジャポンー
「それはまるで、高速道路を降りて、あえて下道を選ぶドライブのように。」
目まぐるしいスピードで流れていく情報の渦を避け、ゆっくりと自分のペースで人生を歩むという選択。
かつての生活に立ち返るように、スマホを手放した人物たちが、都市の喧騒から逃れるかのごとく静かな生活を手に入れている。
最新のモデルではなく、古い携帯電話を手に取り、必要最低限の連絡手段に限定する。
レコメンドやパーソナライズ化によって選択肢を与えられる状態から、選択肢を自分で作り自分で選ぶ状態を作り出す。
「自分らしさはフローチャートに答えれば得られるものではない。」
本当に自分らしさを貫こうと思えば、そもそも「どうなりたいか?」or「どう在りたいか?」をまず定義する必要があるのだと。
そのための第一歩として、スマホからガラケーに変えて情報を制限した彼らの行動は、今となっては回り回って贅沢な状態と言えるのかもしれません。
「連絡の手段が制限されることで、周囲との繋がりは薄まり、彼らは次第に自分の世界に閉じ籠もるようになる。」
しかし、この「不便という贅沢」には、別の側面も存在しています。
確かにデジタルデバイスを手放すことで、静寂や内面的な充実感を得ることができるかもしれません。
とはいえ、その静寂は孤独に対する耐性が無い人にとってあまりにも深いものであり、世界から孤立していく孤独感を伴うものです。
例えば、認知症のきっかけは難聴にあるのではないかという説があります。
それは、耳が聞こえないが故に他者との対話よりも自分との対話を優先していく結果、認知症が加速していくのだと。
「デジタル依存から脱却することは、自己実現かそれとも社会不適応なのか?」
また、アナログを選ぶという選択は、本当に自分らしさを取り戻すという崇高なものであり、社会から逃避するものではないと言えるのでしょうか。
例えば、若者の◯◯離れという現象がありますが、それは単純に所得格差が引き起こした現象に過ぎないと。
或いは、お一人様肯定ムーブは単純に婚期を逃した人間が自分を慰めるために作り出した現象なのではないかと。
そんな皮肉や当てつけのような分析と同じく、単に「デジタルデバイスが買えない」or「デジタル上で馬鹿騒ぎする人々に対する嫌悪感」がそうさせているのではないか。
本当にデジタルの利便性を犠牲にしてまで追求するようなKDFを持った人間がアナログ回帰を唱えているのでしょうか。
つまり、我々が直面する葛藤には、それが単なる自己受容(セルフコンパッションやマインドフルネス)か否で揺れ動く人間の本質的な脆弱さがあるということです。
言い換えれば、自分が成し遂げたいKDFに基づいて内発的に生まれた理想像なのか。
それとも、自分で自分を慰めようとした結果、外発的に作られた幻想が自分の理想像になっているのか。
いずれにせよ、その幻想を生み出す根源が世間の情報(他者の意見や他人の視線)にあると。
だとするならば、それを断ち切るために自ら不便を選べる「意志そのものが至福をもたらしている」と言えるでしょう。
「オンライン上で育まれた友情は本物なのだろうか?」
繋がりを求めてSNSやメッセージアプリを頻繁に使用する現代人にとって、これは大きな議論の的になっています。
例えば、Facebookの友人リストがその人の社会的価値を測る指標とされるような風潮が存在し、友人の数が少なく質が低ければ社会的に評価されにくいことがあります。
「いや待て、そもそもその評価基準は正しいのか?」
そう、ここで私と同じくあなたもそう考えたことでしょう。
言い換えれば、現代のような繋がりやすく解けやすい紐帯社会(造語)において、「知人の数と質で人の価値を測る社会は正しいのか?」という命題がすでに浮上しているのです。
「アップルやフェイスブック、アマゾンなどのテック企業が封建領主となり、それ以外の全員が小作農のような立場に置かれている。」
近年、元ギリシャ財務大臣のヤニス・バルファキス氏が唱えるテクノ封建制という概念が話題に挙がりました。
それは、大手テック企業のプラットフォームが中世ヨーロッパの封建制のような様相を呈しているという考えです。
例えば、X(旧Twitter)でユーザーが投稿するという行為はイーロン・マスクの私有地を耕しているようなもので、無償の労働を提供していると。
なぜなら、ユーザーが投稿してアクティブになればなるほど規模の経済が成立してXの収益に繋がるからです。
もっと言えば、市場は荘園に代わり、デジタルプラットフォームにアクセスするための地代(課金)を収めなければならないのだと。
その意味で言えば、オンラインで育まれた友情はプラットフォーム在りきで、「仮初の友情である。」という意見もあります。
「やはり人の価値はオンラインの数値やランキングに依存するものではなく、人間関係の質にこそあるべきなのだ。」
もしそのような思想が伝播すれば、例えば将来的には「フレンドゼロ運動」としてSNSの友人リストを削除し、自己価値の再評価を試みる運動が流行するかもしれません。
SNSで繋がらずとも電話番号1つで十分なのだと、遭遇と邂逅こそが心を満たすのだと。
しかし、これは簡単に実行できるものではありません。
なぜなら、現代社会はオンライン上の繋がりが現実の人間関係と代替可能とされているため、SNS上での友人削減は一種の「自己犠牲」にも等しい行為だからです。
とはいえこの運動は、社会に大きな波紋を広げる可能性がある一方で、私たちに「繋がりやすく解けやすい紐帯社会における豊かさとは何か?」を再考させてくれるでしょう。
また別の観点から探ると、デジタルデバイスを駆使出来ないことで情報格差が生じ、社会参加における不利益を被る事例も増えています。
例えば、デジタルデバイスを持たない人々は「お得意様カード」や「アプリ限定クーポン」を利用できず、他の消費者よりも割高な買い物を強いられるケースがあります。
さらに言えば、スマホでQRコードスキャンが必要な学校や職場のシステムによっては、デジタルデバイスを使いこなせないことで不便を強いられる状況もあります。
ここで考えなければならないことは、「デジタルディバイドがもたらす情報アクセス制限はどこまで許容されるのか?」ということです。
この問いは、単なる利便性の問題に留まらず、「デジタル社会における基本的な権利」として議論される可能性があります。
つまり、言ってしまえば、健康で文化的な最低限度の生活という日本国憲法第25条「生存権」に含まれるか否かというものです。
なぜなら、情報へのアクセスが公共サービスや社会的な参加機会と密接に関連しているためです。
例えば、マイナンバーカードが個人の証明のみならず、保険証とも紐づきこれからも機能が拡充されるということは、行政や市政との結び付きがより強固になるということです。
すると、たかがマイナンバーされどマイナンバーで、そのカードを持たない・持てない・使えない人は著しく不利益を被ることが予想されます。
もちろん、マイナンバーカードによる政治投票及び参政権を視野に入れようものなら大問題です。
そして、もしもそのカードが没収・紛失・偽造された場合、当人には致命的なダメージが降り掛かることでしょう。
ちなみに、外国人技能実習生が職場に在留カードを管理(没収)された結果、これに近い現象が起きています。
つまり、夜逃げした外国人技能実習生が、偽造カードを作って保有したことで言われもない罪を着せられている人が生まれているのです。
そもそも夜逃げするな、させるなという問題がありますが、これはあくまでされてしまった場合の話です。
夜逃げ後、金も無く帰るに帰れない人は日本に滞在するために偽造カードを求めます。
そう考えれば、違法ビジネスには必然的に需要があることが見えてきます。
しかし偽造カードは本物のカードを基に偽造する必要があります。
例えば、金がなくて在留カードを担保にした者もいれば、恋人に無断で売られた者、窃盗にあった者。
それぞれ何らかの理由で偽造の基になるカードが製造者の手に渡ります。
不注意と言えばそれまでですが、窃盗にあった被害者の場合。
或いは、自業自得と言えばそれまでですが、夜逃げした外国人技能実習生の在留カードが勝手に売られた場合。
そう、違法を犯す外国人だけでなく、実は日本人が経済的困窮のために在留カードを売りさばくこともあるのです。
つまり、マイナンバーカードに頼るということは、カード1つで一生が脅かされる可能性があるということです。
「テクノロジーが生活に浸透する中で、デジタルデバイスを持たない人々も平等に情報にアクセスできるような制度的保障は必要なのだろうか?」
冒頭でお伝えしたように、デジタルデバイスを手放すことが単なる一過性の自己満足ではなく、「意志そのものが至福をもたらしている」場合。
それは、「個人の「選ぶ自由」を尊重するための社会的権利として認められるべきではないか?」という問いが生まれます。
言い換えれば、私たちには、「デジタルデバイスのない生活を選ぶ権利が残されているのか?」ということです。
私は、これが21世紀中盤に掛けて非常に重要な問題になると考えています。
なぜなら、デジタルデバイスを持たない人々は、情報の即時性を失い、社会の流れから取り残される危険性を孕んでいるからです。
この「デジタルによる社会放出」とも呼べる現象が、社会の中で孤立と新たな分断を呼び起こし、まさかの事態が引き起こすと考えているからです。
そう、丁寧さや豊かさを求めた人々は、自分が成し遂げたいKDFに基づいて内発的に生まれた理想像のためにデジタルデトックスをしたはずです。
しかしながら、孤立と分断から自分で自分を慰めることを促進して、外発的に作られた幻想が自分の理想像に取り込まれていくという流転現象(造語)が起きるのです。
要するに、ミイラ取りがミイラになるという流転現象が見えないところで人間を動かしてしまうということです。
だからこそ、過度なデジタル依存によって生まれた社会において、デジタルデバイスのない生活を選ぶ権利を真剣に考える必要があるのだと。
そんなことを考えさせられました。


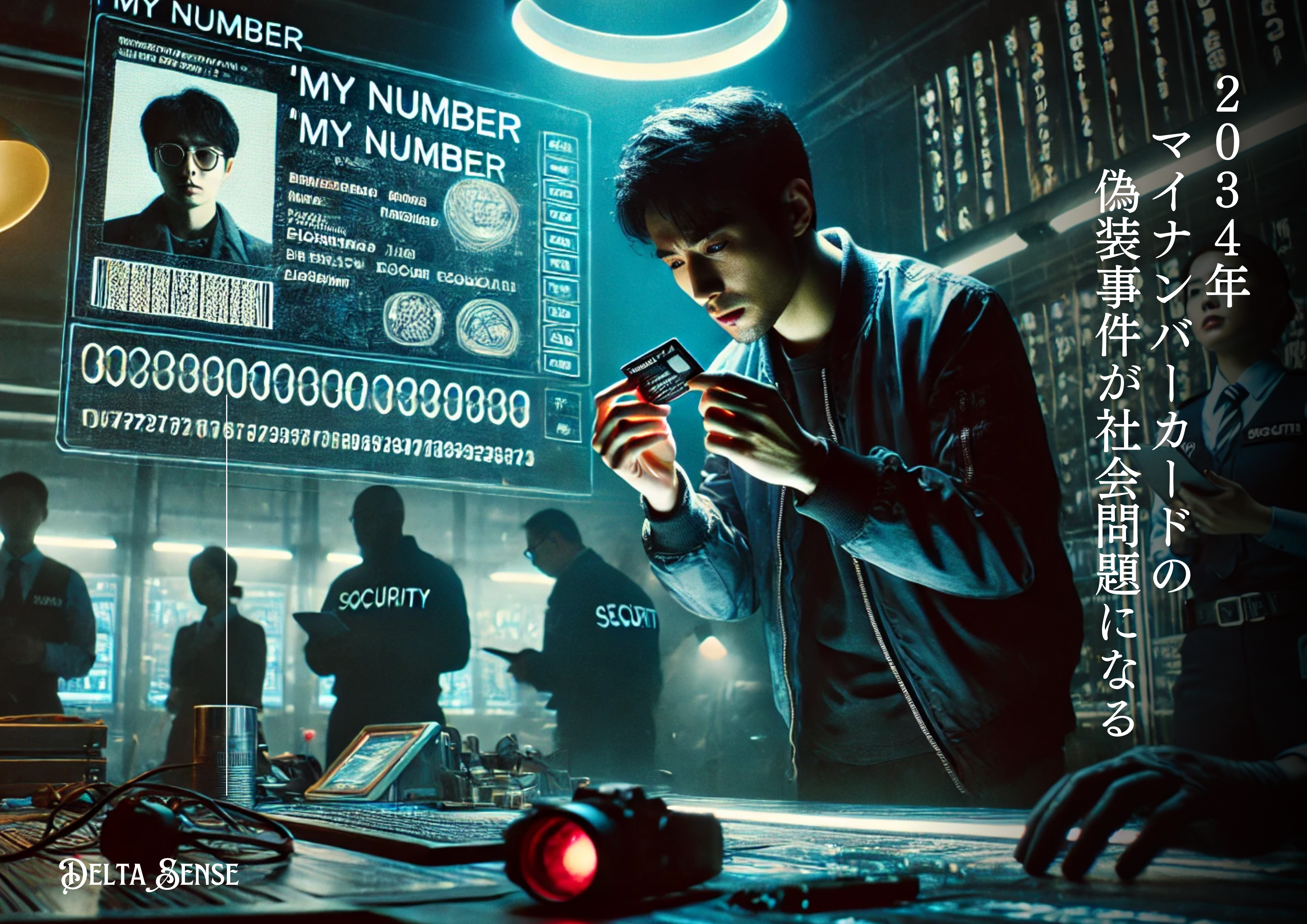
町内の会議で「回覧板を廃止したらどうか?」と意見を言ったら反対された。「みている人がいる」とのこと。私が住む地域は新興住宅も多く、古くからの住民との情報格差を感じた。
回覧板の広報は今やほとんど市のサイトにアクセスすればみることができる
それすら知らないのだと思うし、発想もないのかもしれない(それを批判しているわけではないが)
スマホなどのデジタルデバイスを持たない権利はなくなると思う。持たざるおえない、というか下手をすると体の一部になる可能性があると考える(手首にマイクロチップを埋め込むなど)
マイナンバーカードが不正利用や偽造されたときに「それではこんな方法は」となり
体の一部論がでるかもしれない
故、寺沢武一氏の漫画で右目に神の眼を持つ男を描いた「ゴクウ」という作品がある。これは右目が世界中のコンピューターにアクセスすることができ、右目で見たものを瞬時に解析できる男が主人公として描かれている。スマホを持った私たちはある意味これに近い。これを活用できないとどんどん社会生活が不利になるし、スマホに変わるデジタルデバイスも近い将来、出てくることは間違いない。
その結果が我々がより管理される社会の完成に近づくのか、より自由な行動ができる社会になるのかはわからないが、私は前者になると予想している。
デジタルデバイスを持たない権利を選ぶ(選ばざるおえない層)のアナログ的な需要を取り込むビジネスはニッチなビジネスとしては成立すると考え、そこを担えるのは零細起業だと思う(完全なデジタルシステムを導入することが困難である等の理由から)