問題提起
イタリア北東部にある、トリエステ総合病院の精神科救急病棟のドアは、いつも開かれている。
この病棟には、患者の友人や家族も気軽に訪れることができる。
室内にはカラフルな絵が飾られ、どこでも好きな場所に座れる。
精神科病棟とは思えない居心地のよさだ。
―クーリエ・ジャポン―
「日本の精神医療はなぜ“世界一の病床数”を抱えながら、自殺率を十分に下げられていないのか?」
この国では、精神科病院の病床数が人口10万人あたり258床に上ります。
これは先進国の中でも突出して多い数字であり、にもかかわらず自殺率はG7のなかで依然として最も高い水準にある。
経済が豊かであるにもかかわらず、多数の人々が孤立無援のまま死を選ばざるを得ない──この矛盾にこそ、我々は向き合わねばならないのではないか。
私はそう考えています。
「精神科病院をできるかぎり解放し、地域を基盤としたケアに移行する。」
他方で、イタリアのトリエステ方式は、患者の人権を尊重しながら自殺率の低減に成功したと報じられています。
事実、トリエステはかつて10万人あたり25人の自殺率を記録していたが、いまでは13人程度にまで改善しています。
では、なぜ同じ先進国でありながら、日本はトリエステのような改革を成し遂げられないのか?
その本質は、「長期入院ビジネスを支える診療報酬制度の歪み」にあるのではないかと。
そして、「社会全体に根づく精神疾患への偏見」もあり、「孤立を防ぐ地域コミュニティの未整備」にも起因しているのではないかなと。
つまり、それらすべてを根底で支えているのが「囲い込み医療」という歴史的慣行にあるのかもしれません。
──この構造を放置すれば、自殺者は減らないままであるばかりか、身体拘束による人権侵害や“地域との断絶”といった悲劇が繰り返される可能性すら高い。
私たちは、この矛盾を乗り越えるためにいったい何をどうしていくべきなのだろうか。
そして、この先に待ち受ける未来と変化は、私たちにどのような影響を与えていくのでしょうか。
背景考察
トリエステでは50年ほど前に、精神病院の病床を1200床削減し、
それで浮いた資金を使ってコミュニティベースの精神医療サービスを拡充させた。
その結果、1990~96年には10万人当たり25人だった自殺率が、2005~11年には13人にまで減少した。
―クーリエ・ジャポン―
- 収容主義とは何か
OECDの統計によれば、日本の精神科病床数は先進国中もっとも多い部類に入り、世界全体で見てもトップクラスの数字です。
これは戦後の精神衛生法(当時)以来、精神疾患を「なるべく隔離し、社会不安を鎮める」方向で政策が組まれてきた歴史の帰結でもある。一方、イタリア・トリエステ市では70年代にフランコ・バザーリアが指揮した脱施設化運動により、大規模な精神病院を閉鎖し、地域のメンタルヘルスセンターを整備しました。結果として、ベッド数が大幅に削減されただけでなく、開放型の病棟や訪問診療を導入し、患者にとっても周囲の住民にとっても「いつでも来られる・いつでも行ける」心のインフラを作り上げました。 - 日本型ロングステイの矛盾
日本では、精神科病院に入院した患者の平均在院日数が極端に長いことで知られます。
長い人では数年、あるいは数十年も退院できないケースすらあると。
そう、一体何が起きているのかという話ですよね。これを支えているのが、医療機関が長期入院で診療報酬を得る仕組みです。
つまり、民間病院の経営は「病床を埋め続ける」ほど安定する構造になっているということです。言ってしまえば、過疎地域などでは、精神科病院が地域経済を支える雇用の場ともなっています。
ベッド数の削減や入院期間の短縮が進むと、病院経営のみならず自治体経済にも影響が及ぶ恐れがあるということです。一方、長期入院が続けば、患者やそのご家族の自尊心や社会復帰へのモチベーションは低下し、身体拘束などのリスクも膨らんでいきます。
そして社会復帰の遅れは、自殺率の高止まりに寄与する悪循環を生む可能性が高い。そう、まさに、「病床数を増やすほどケアが行き届く」という考え自体に根本的な疑義が生じているということです。
- コミュニティ・レジリエンスとビフォーケア
トリエステ方式において注目したいのは「地域が、患者と共に生きる。」という考え方です。
入院はあくまで短期的かつ必要最小限とし、退院後は地域の精神保健センターやアウトリーチチームがサポートを継続すると。これにより、患者は孤立の淵に立たされることなく、社会参加を続けられる。
近隣住民もまた、患者を「特殊な存在」としてではなく「地域の一員」として迎え、生活の場面を共有していくことが出来ると。その背景には、「ビフォーケア」の視点──すなわち、自殺念慮や重度化が進行する前に手を差し伸べる予防的アプローチがあります。もちろんこのモデルを日本に移植するには、地域医療従事者の増員や行政予算の再配分など多岐にわたる課題を克服しなければならない。
しかし、もしそれが成功すれば、長期入院依存を減らして自殺率を下げ、医療費の長期的なコスト削減にも資する可能性があると言えるでしょう。
「では、日本がトリエステ方式を導入し、病床を減らして地域支援へと転換したらすべては変わるのでしょうか?」
ある意味、長期入院病棟は「安全な檻」だと形容できます。
患者は少なくとも“居場所”があり、社会は目に見える問題を隔離した安心を得られるからです。
「檻を開けたはずが、外の世界にこそ、新たな“見えない壁”が佇んでいた。」
しかし、この檻を急に壊したとしても、そこに地域のフォローアップ機能が整備されていなければ逆効果となる可能性があります。
つまり、“檻の外に放り出された”当事者がどこへ行けばいいのか分からず、むしろ危機的状況に置かれてしまう危険性があると。
なぜなら、その理由が「地域スティグマ」にあります。
スティグマとは、個人や特定の社会集団に対して周囲から否定的な意味づけやレッテルを貼られることです。
日本語では「差別」「偏見」「汚名」「烙印」などと表現されています。
想像してみてください。
「元精神病患者」が隣人となることに対して、あなたは何を思いますか?
様々な理由があれども、結論から言えば「拒否感が強い」のではないでしょうか。
「入院患者を地域に戻すこと自体が、「安全神話」の崩壊と受け取られる可能性があるのではないか?」
それもそのはずです。
しかしそれは、私たちが精神疾患に対して深い偏見を根強く持つ差別主義者だからではありません。
トリエステ方式の理念は、「治療と自由は両立する」という前提に立っています。
しかしながら、この理想を日本社会にそのまま導入することは、必ずしも万能薬にはなり得ないのです。
なぜなら、日本には「囲い込むことでしか安心を得られない」社会心理が横たわっているからです。
すでに、現在進行系で外国人が流入していく中で、様々な文化的衝突が発生しています。
例えば、近頃はやけに外国人運転手による自動車事故が多発しているとは思いませんか。
その理由が下記です。
外国免許証から日本免許証への切り替え手続きはホテルの住所で登録が可能。
知識確認では日本の交通ルールについての問題が「○×形式」で10問出題され、7問以上正解すると、次の技能確認の試験に進める。
つまり、標識も読めず、加害者の追跡も不可能な状態で運転されている。
そして、そもそも事故を起こしたときに損害賠償金が払い切れるかわからない者に自動車の運転を許可した結果、何が起きているのか。
一言で言えば、外国人に何かをされたら、泣き寝入りとなる事件が増加しています。
「外国人の起こす事件は天災だと思って、日本人は我慢せよ。」
リスクと引き換えにツーリズムで経済は潤うとでも言いたいのでしょうが、納得できる国民はどれほどいるのでしょうか。
つまり、文化的衝突が起き始めている今、トリエステ方式のような「脱施設化」は新たな排除の形──“地域スティグマ”を生むリスクを孕んでいるのです。
言い換えれば、「多様性に溢れた、誰もが誰にでも心を開けるような理想の地域社会」を作ることの限界に直面しているということです。
繰り返しお伝えしますが、その理由は日本人が、あなたが、差別をしているとか器が狭いからではありません。
もう、衝突が始まってしまったからなのです。
では、どうしていくべきなのでしょうか。
後編では、より未来を身近にしていきたいと思います。
それではまた、後編の②でお会いしましょう!

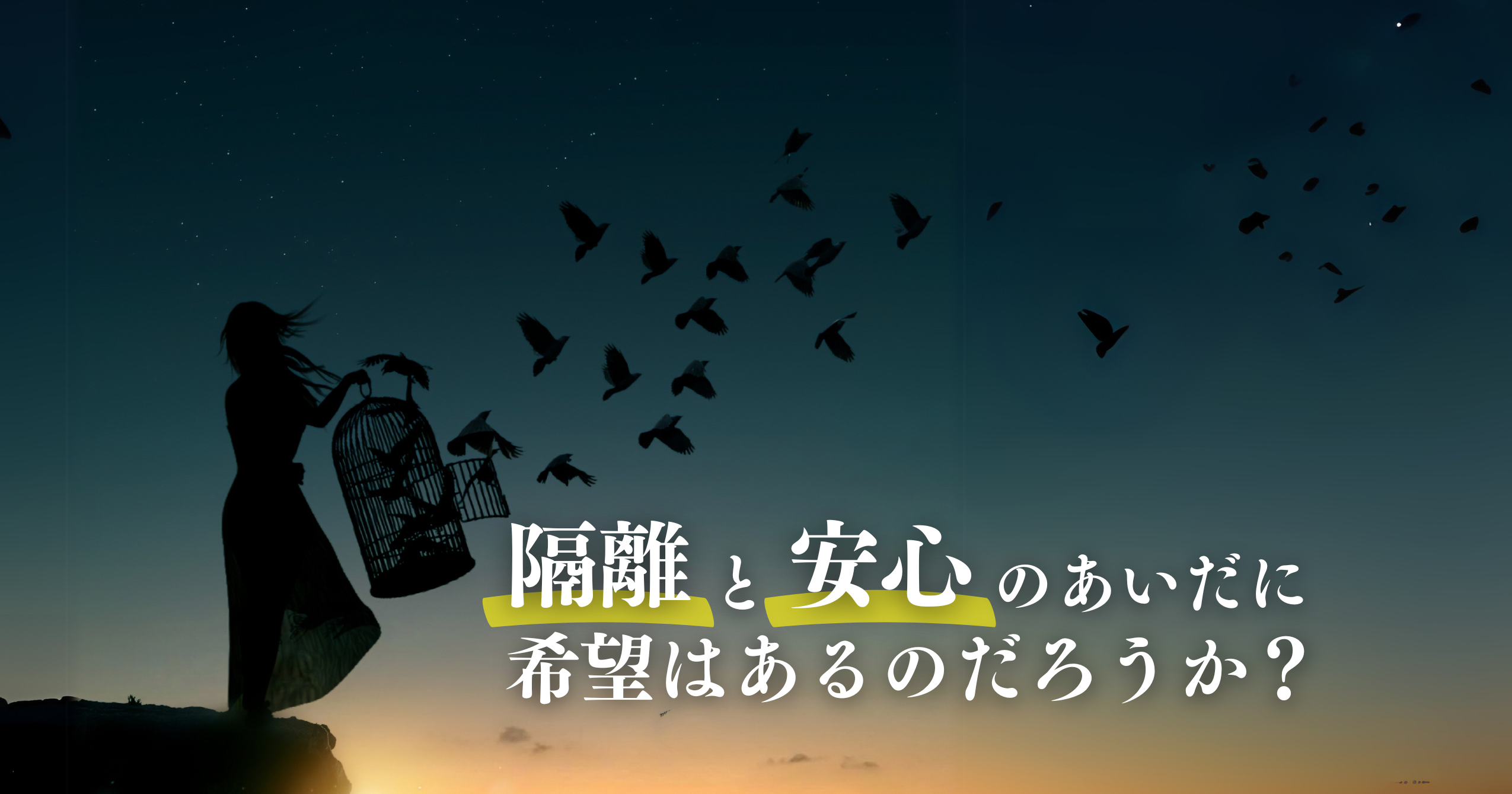
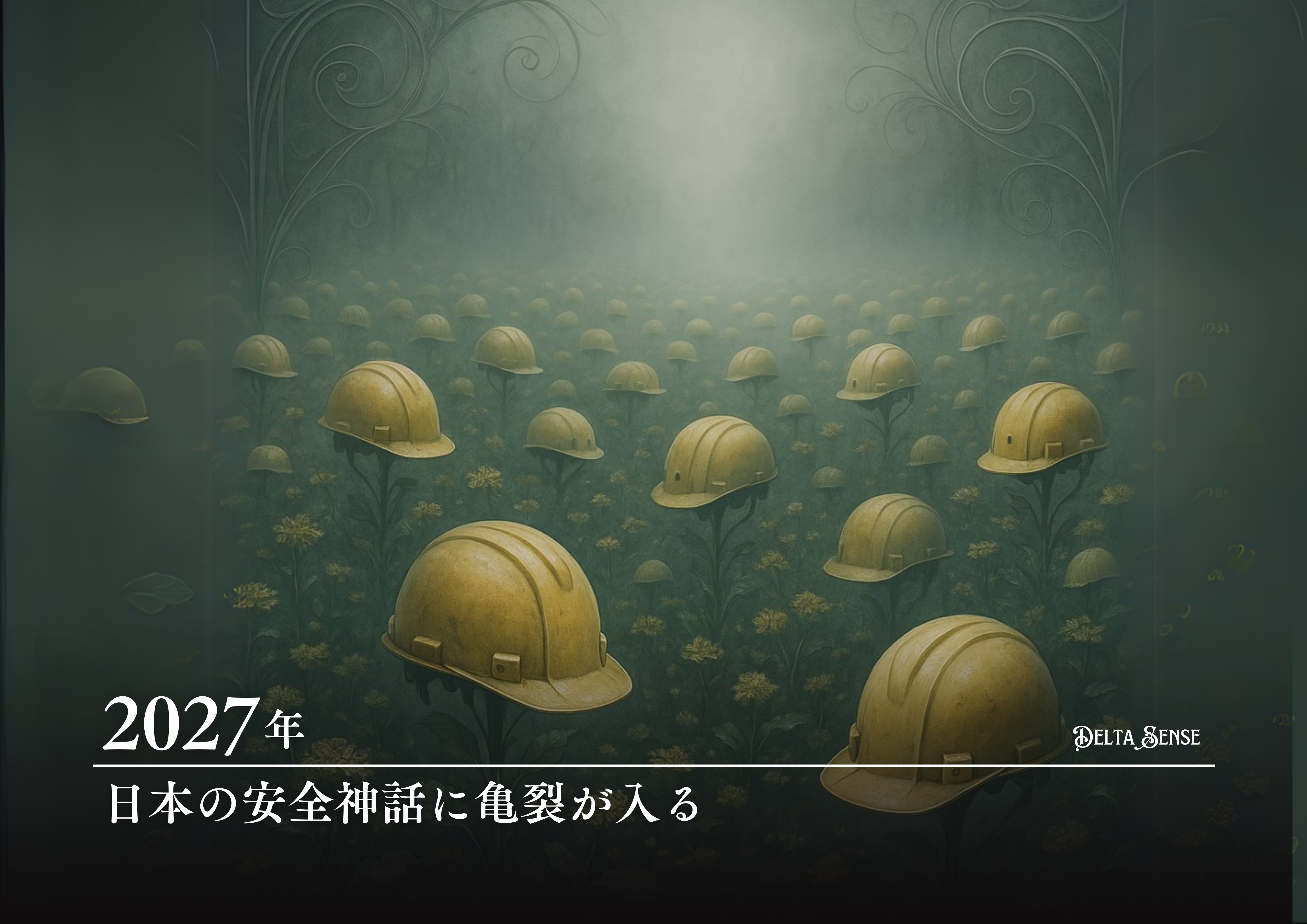
この記事から疑問に思ったこと
日本はなぜ精神病大国なのか?
それが精神医療制度の問題なのか?
若者の自殺率が高いのはなぜなのか?
重度の精神病患者の社会復帰率は?
精神病棟に入る事がさらなる社会復帰の妨げになっていないか?
精神病という定義がおかしくはないか?→例として発達障害は昔は少なかったが、今は検査の充実で「発達障害」とされてしまう
食と精神病との関係は?
住む地域、住環境との関係は?
犯罪者の社会復帰についての現状は?
似たような問題ではないか?
外国人の観光もそうだが、労働力としての受け入れの問題点とは?
私としては自殺率の増加は精神病医療制度の問題とはまた異なった部分が大きいのではないかと考えていましたが、実際はどうなのか?
私なりの予想として
囲い込むことで安心する社会の維持が外国人の入国で困難になっているのであれば、それがどう変わるのか?
「治安の良さは日本の文化」と言っていた人がいたが、文化が変わってきている昨今、治安の良さが失われていくことも文化の変化として受け入れざる終えないのかもしれない
以上
こんにちは。今日も楽しく拝読しました。
多様性に溢れた心理的安全性の確保された社会は、相互理解と相互受けいれが無ければ出来ないもの
▶︎成り立たなくなったということは、上記のどちらかが破綻した。と考えられると思います。
受け入れる前に理解する段階があるのだとすれば、今の日本で欠落・崩壊したのは相互理解の部分なのでしょうね。
そこには、
1.理解すべきことがVOCA化
2.理解させられない(伝えられない)
3.理解できない(受け取れない)
という問題がそれぞれあるように思えます。
何が悪か。ではなく、結果として悪になっている。
そんな社会で動いていくには、多方向へのコミュニケーションが必須になるし、自分がどのように見られているかの客観視も肝要になると感じました。
「日本の精神医療はなぜ“世界一の病床数”を抱えながら、自殺率を十分に下げられていないのか?」
というとに対して、「どこで治すか」ではなく、「どう共に在るか」、まさに共にいき、共に歩むといった「共生」という言葉が近い気がしました。
前々から知らぬ間にあった病床が“安心”をもたらす時代は終わり、精神を治すということだけでは、孤独は癒せないと思ってます。
まさに秩序や同調圧力を重んじる傾向が強く、「違い」や「弱さ」に対してそこまで寛容ではない日本社会は、社会全体の価値観や文化の変革を心の底から求めているのかもしれません。