問題提起
前編で提示したとおり、日本の精神医療においては「世界一の病床数」と「高い自殺率」が同居するという、ある意味で相矛盾する現象が続いています。
一方、イタリア・トリエステ方式の成功例を見るに、病床削減と地域ケアが自殺率低減に寄与する可能性は決して低くないものです。
「もし仮にトリエステ方式を導入した場合、日本で本当に機能するのだろうか?」
我々は果たして、この巨大な「囲い込みシステム」をどう刷新していくことが出来るのでしょうか。
そして、その過程で“人の生死に関わる選択”を社会はどこまで許容し、支えていくべきなのだろうか。
この先に待ち受ける未来と変化は、私たちにどのような影響を与えていくのでしょうか。
背景考察
「近代国家は“規律権力”を通じて人々を管理し、逸脱者を隔離するシステムを生み出した。」
フランスの社会学者ミシェル・フーコーは『監獄の誕生』で、精神病院こそまさにその象徴的施設であり、患者は「病」のレッテルを貼られることで社会から距離を置かれると。
また同時に、家族や社会にとっては「専門家に任せておけばいい。」という安堵感が得られ、結果として長期入院が容認されてきたのだと。
それは、「(あなたもわたしも)大変だから」介護福祉施設に親を預けるという現象にも言い換えられるものです。
つまり、このような収容主義(隔離することで安心感を得る)ということが、歴史的にも容認されて来ました。
「真の治療は「患者を地域から切り離す」ことではなく、「地域の中で関わり合いながら人間的尊厳を回復する」ことである。」
しかし、イタリアの精神科医フランコ・バザーリアが提唱するトリエステ方式は収容主義とは相反するものでした。
そう、ここで登場するのがコミュニタリアニズム(共同体主義)という概念です。
個人の自由や権利を尊重しつつも、共同体の絆や連帯によって社会的統合を図る思想とも言えます。
トリエステ方式が成功した理由は、単なる病棟閉鎖や病床数の縮小だけではありません。
地域住民の協力と公共サービスの密接な連携によって“人々の相互扶助”が制度として機能したからだと考えられます。
その一方で、日本では「病床が多いほうが安心」という通俗観や、民間病院経営に伴う利害構造が、コミュニタリアニズムを阻む大きな壁となっています。
さらに、「精神疾患を抱えた人が近隣に住むのは怖い」といった地域スティグマが根強いため、たとえ病棟を開放しても、当事者が孤立無援のまま放置されるリスクがあると。
このように考えると、“本当に檻を壊すだけで人々が救われるのか”という問いがより切実に浮かび上がることが分かります。
「自殺を防ぐということは、突き詰めれば「人が死を選ばなくてもよいと思える環境」を創ることです。」
もしそうだとするならば、やはりその答えは、 “地域と共に生きるケア”という概念に潜んでいるのではないでしょうか。
トリエステ方式の核は、「ビフォーケア」と呼ばれる予防的アプローチや、地域保健センターが自宅訪問を繰り返すアウトリーチにあります。
つまり、トリエステ方式の本質は、“開かれた空間”に解き放つことではありません。
“信頼が存在する空間”に解き放つことと解釈するべきなのではないかなと。
「家族を乗せた車で危険な運転はしないし、顔と名前の分かる場所で悪行はしない。」
それはつまり、制度でも建物でもなく、人と人との関係性に宿るものです。
住民が患者と顔を合わせ、同じ社会的空間を生きることで偏見もまた薄れていくのではないか。
このプロセスそのものが“治療”であり、“共生社会”の創成でもあるのだと。
そう捉えることも出来るのかなと思います。
ここまでの流れを踏まえて、これからの未来を整理してみましょう。
1. 「病床削減で本当に自殺率が下がるのか? あるいは地域が“見捨てる”形で逆に増えるリスクはないのか?」
・通説: 長期入院を減らすほど当事者を地域へ送り出すことになるが、適切なフォローがなければ逆に生きづらさが増す。
・新説: しっかりとビフォーケアとアウトリーチを組み込むことで、むしろ初期介入が充実し、“助けを求められない孤立”が解消されやすくなる。
2. 「身体拘束や隔離を減らすことで、地域社会が抱える偏見や恐怖心はどう変化するのか?」
・通説: 退院者が増えるとトラブルも増えるという先入観を助長する。
・新説: 実際に接する機会が増えることで、当事者の現実的な姿を認知し、無用な恐怖が緩和される。生身の交流こそ差別意識をほぐすカタルシスとなり得る。
3. 「コミュニティ主導のケアを実行する財源や人材は、本当に確保できるのか?」
・通説: 地方自治体には財政難や人材不足が深刻であり、理想論だけでは対処できない。
・新説: 地域包括ケアへの転換は中長期的なコスト削減と地域経済の活性化をもたらす可能性があり、公共投資としてはむしろ合理的である。
≪個人の命題≫
1. 「安易な長期入院で自分を守るか、地域に戻るリスクを取るか──どちらを選ぶか」
・通説: 病院にいれば安全・安定が保証されると思われがち。
・新説: 地域のネットワークを活用すれば、より人間らしい生活を取り戻せる可能性が広がる。
2. 「精神疾患を抱えているとき、自分の物語をオープンにすべきか、それとも隠すべきか」
・通説: 差別や偏見を避けるためには、公にしないほうが無難。
・新説: 自らの経験を共有することで他者の共感や理解を得られ、生きやすさやサポートを得る新たな道が開ける。
≪社会の命題≫
1. 「自殺率を下げるために、医療だけでなく地域全体を巻き込む仕組みをどこまで構築できるか」
・通説: 専門家任せで、地域住民は受け身。
・新説: コミュニティ全体が当事者意識を持てば、自殺予防の初期介入の幅が大幅に拡充される。
2. 「診療報酬制度や地方自治体予算の再配分をどのように行い、既得権益と折り合いをつけるのか」
・通説: 利益相反が大きすぎて抜本改革は困難。
・新説: むしろ医療依存型の収容主義が続けば医療費負担も高まり、国や地域の財政的破綻を招くリスクも。コミュニティベースのケアこそ、長期的な費用対効果が高い。
私たちは、「なぜトリエステ方式が自殺率低減に成功したのか」を問い続ける中で、人間が本来持っている社会的本能や、地域が持つ潜在的な互助力に目を向けざるを得なくなるでしょう。
するとそこで、“地域の当事者”として行動する一人ひとりの覚悟が問われます。
まさにそれは、個人のリスク選好や生き方の選択にも深く関わる問題と言えるでしょう。
「精神疾患を抱える人々が“檻”ではなく“生活の中”でケアを受けられるように。」
トリエステ方式は、「病床削減」と「コミュニティ・レジリエンス育成」という2つの大きな柱を軸としたものです。
その結果、自殺率や再入院率の低下が実現し、WHOや国際的な評価機関も高く評価するに至っています。
しかし、日本では民間病院のロビー活動や財政構造の問題、そして何より社会に根づく精神疾患への偏見が壁となっています。
一時的に病床を減らすだけでは、患者を“地域の荒野”に放つだけの結果になりかねないと。
だからこそ、地域における予防的な取り組みやアウトリーチチームの充実、住民教育や子どもへのメンタルヘルス授業など、広範な社会的変革が必要になる。
とはいえ、いくつかの自治体やNPOのパイロット事業では、既に地域支援モデルが奏功し、当事者の孤立を軽減した事例も報告されています。
「人と人とが顔を合わせる」回数が増えるほど恐怖や偏見は薄れ、そのかわりに“互助”という新しい経済やコミュニケーションが芽生えるものです。
そこには、まさしくトリエステ方式の醍醐味──“本来、人間は孤立して生きるものではない”というメッセージが、はっきりと映し出されているのかもしれません。
「あなたは、精神医療を社会の片隅の出来事だと思っていませんか? もし、自分や家族、あるいは大切な友人がその現場にいるとしたら?」
自殺率が示す統計の裏側には、名もなき人々の痛切な物語があります。
ある日突然、愛する人が“見えない崖”から落ちそうになったら、私たちは病院に任せるだけで安心するのか。
あるいは「一緒に支えるから、ここにいていいんだよ。」と声をかける社会をつくるのか。
その選択は個人だけでなく、私たち全員が担わなければならないものです。
トリエステ方式のエッセンスは、決してイタリア独特の文化や歴史だけから生まれたものではない。
人間の尊厳と、生きる意思を育むために欠かせない“他者との関係性”という普遍的な価値に根ざしたものです。
「精神医療は、そこに携わる専門家だけのものではない。むしろ、地域や家庭、学校、職場のあらゆる人々に関わる総合的な課題である。」
日本が本気で自殺率を下げたいと願うのであれば、今こそ私たちは「病床数が多い=安心」という思い込みを捨てるべきです。
地域ベースのケアこそが長期的に人々を支えるインフラになるのだという現実を直視しなければならないでしょう。
とはいえ、社会全体が再編されるプロセスには時間も労力も掛かるものです。
しかし、その先にこそ、“誰もが孤立せずに、自分の存在を認め合う場所”が形作られるのではないでしょうか。
と、ここまで書いておきながら、ふと思います。
お互いを認め合う場所を作ろうとした結果、慰め合う場所になってしまって、承認欲求を制御できない状態に陥っているんだよなぁと。
本当に難しいテーマだなと改めてそんなことを考えさせられました。

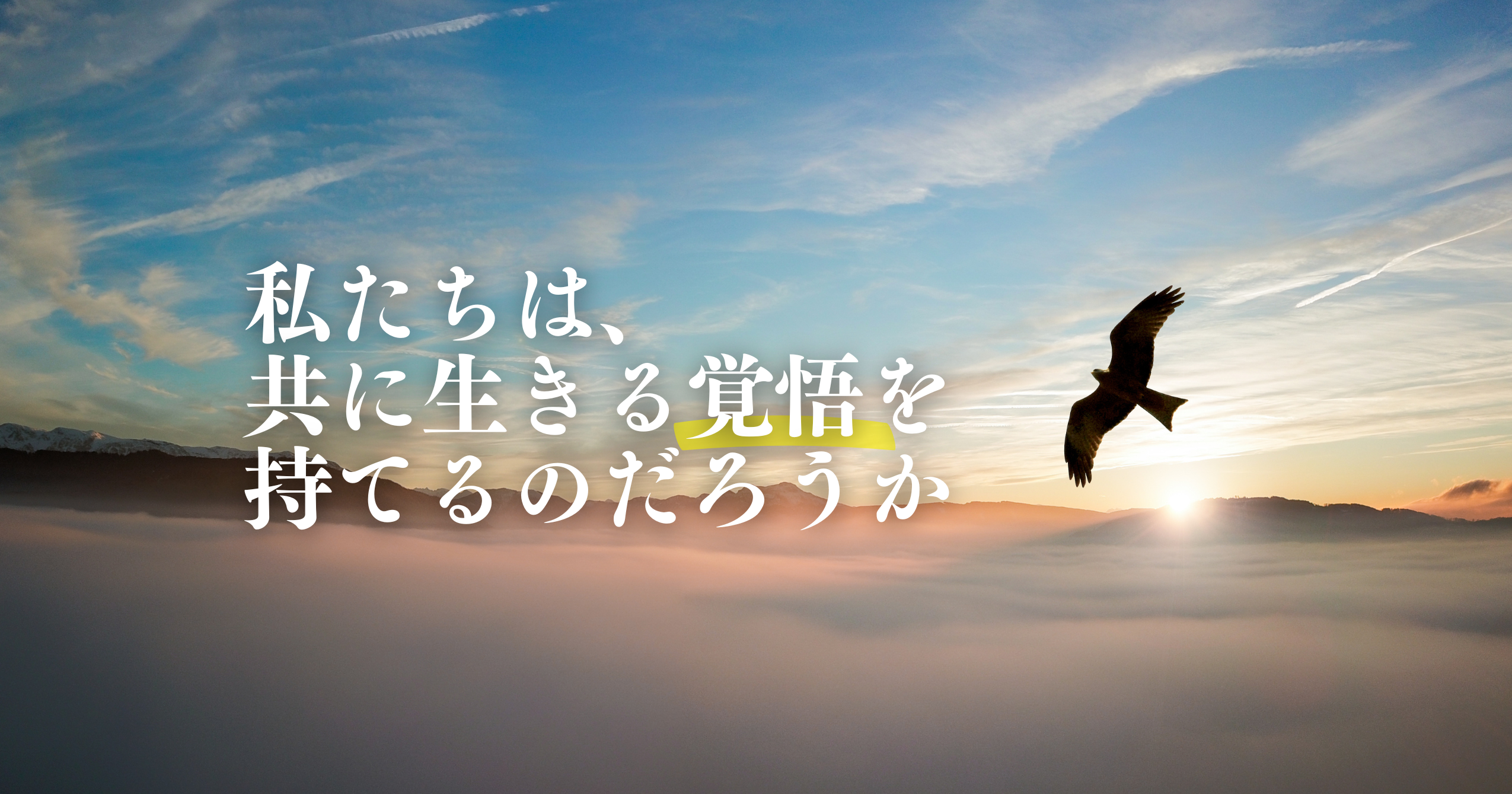
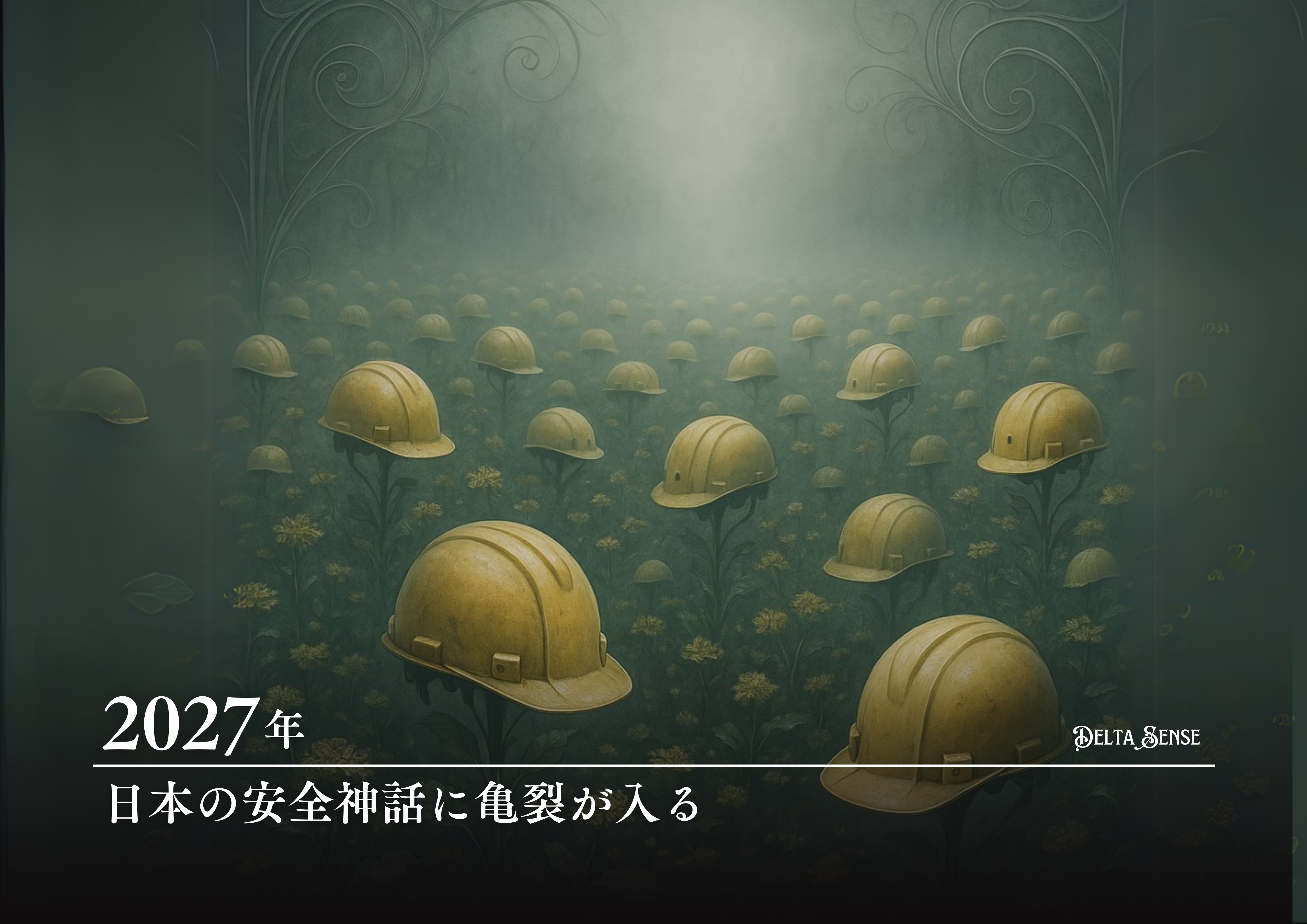
精神病の患者を隔離ではなく、いかにコミュニティが理解し、そのコミュニティにむかえいれるのか?社会の偏見をなくし、理解が必要になるであろう
そこで考えた解決策
近年、通信制高校の入学希望倍率が高くなっていると聞いた
学校にいけなくなった生徒は精神病ではなく、ちょっとしたきっかけで不登校になってしまう。それを理解し、受け入れ、教育することで社会復帰を目指していく
学校にくる回数や勉強の仕方は生徒のペースに合わせる
職員室は常に開かれ、生徒の相談を受け入れる
こんなスタイルの通信制高校が人気なようだ
精神病棟も教育関係者を入れて学校のようなコミュニティを作ってみたらどうだろうか?
そこを卒業するころには社会復帰できるようにするとか
その中で資格取得などもできるようにする
精神病院と学校がコラボする感じ
どうだろうか?