問題提起
前編では、「フェラーリ方式」の待機時間マーケティングが家電業界へ波及していく可能性と、それがもたらす儀礼的消費という現象ついて見渡しました。
では、こうした戦略はいったい具体的にどのようなプロセスで形作られ、そしてどのように顧客心理と結びついていくのでしょうか。
後編では、当事者たちの視点を交錯させることで、より立体的な内容にしていきたいと思います。
まず、家電市場では伝統的に「大量生産×効率的流通」が一種の定石とされてきました。
それゆえ、製品の陳腐化サイクルが短いことを前提に、いかに迅速な製造・物流・販売を実現するかが競争力の源泉でした。
しかし今後は、「高品質・高価格帯」が叶う製品セグメント(例えば、趣向を凝らす系)において、あえて生産枠を絞り込み、消費者に“待つ喜び”を提供するモデルが注目を集め始めるのではないかと。
最高のデザイナーでもいつかは勢いが衰え、交代する必要が出てくる。
バーンスタインのルカ・ソルカ氏の分析によれば、高級ブランドの株価と営業利益は、一人のデザイナーが5年間在職するとピークに達する傾向にある。
今は契約期間が大抵3年で、順調なら延長するオプションが付く。
グッチのデ・サルノ氏の在職期間はたった2年だった。
昨夏にトム・フォードを退任したピーター・ホーキングス氏は1年に届かなかった。
―クーリエ・ジャポンー
「グッチやバーバリーが起用するスターデザイナーが短命なのにはれっきとした理由がある。」
それはなぜかというと、大きな要因として、コモディティ化の進行が挙げられます。
機能や基本性能については他社と似たり寄ったりになり、AI導入によりデザイン面でももはや差異をつけにくい時代になってきました。
「メーカーの印を隠してPCを並べられたら、どれがどのメーカーなのかを判別するのは至難の業。」
するとこのアパレル業界の事例を軸に家電業界でも同じような現象が起きていることが想像できるのではないでしょうか。
そのため、企業は「待機時間」という“非機能的価値”に光を当て、それを独自のブランドストーリーとして発信するのではないかと。
しかし、そもそもフェラーリが実施しているような「市場の需要より1台少なく売る」戦略は、家電業界のスケールにはそぐわない部分があります。
自動車のように高額商品がゆえに、1台あたりの利益率が極端に高いわけでもないと。
そこで疑問が生まれるのは、「家電メーカーはどうやって採算を取るのか」という点です。
さらに、納期を長期化することでユーザーの期待値が増大しすぎ、いざ製品が届いたときの落差(いわゆる“幻想と理想のギャップ”)がブランドの評判を毀損する可能性も高まる。
こうしたリスクとリターンのトレードオフは決して小さくありません。
そして何より、このトレンドが家庭の消費生活や社会構造に与える影響は想像以上に大きい。
もし「待つ時間こそ価値」「少量生産こそ高級の証」という認識が浸透しはじめれば、消費文化全体が大量生産社会の終焉に向かう転機となるかもしれない。
そこには、サプライチェーンの大規模再編や、新たなマーケティング倫理の確立が求められるでしょう。
ひとたび歯車が大きく動き始めれば、商品流通の根底にある“当たり前”が次々と覆っていくのは想像に難くないです。
こうした現象は、未来の私たちにどのような影響を与えていくのでしょうか。
背景考察
「当社は洗練された製品技術を誇ってはいるが、その魅力が市場で十全に伝わらないジレンマを抱えていました。」
内容をより身近に引き寄せるためにも、最も近い事例として、クラウドファンディングを実践しているメーカーのお話も参考にしていきます。
ある家電メーカーでCMOを務める人物(以下、A氏)は、「待ち時間価値」マーケティングの導入に興味を持つ人物の一人でした。
A氏によれば、同社ではかねてより「製品差別化の限界」を感じているのだと。
競合他社の追随をすり抜けるため、より先進的な機能やデザインを模索してきたが、すぐに模倣品が出回るのが常でした。
ところが数年前に、レジャー/観光業界のPR戦略を分析した際に“待機期間のエンターテインメント化”というコンセプトに大きなヒントを得たと。
そこで、納期を通常よりも3~4カ月程度伸ばして、限定◯◯台の予約注文に切り替えることを決断。
プロダクト系に強く、受発注がスムーズに出来るMAKUAKE/マクアケ(クラウドファンディングサイト)で予約販売を展開。
「製品到着前の段階で“自分の人生を変える特別な商品”という物語が、購買者の頭のなかで完成しはじめる。その体験こそが、いわゆる“待つ価値”に繋がると考えます。」
ユーザーに“完成を待ちわびる”行為自体を楽しんでもらい、製造の進捗具合をポストして、製作者の思いを伝えるのが狙いでした。
結果的に、予想販売数の3倍の予約希望が殺到しました。
「過度に期待を煽ると、届いたときに落差を感じさせてしまうリスクは大きいのではないか?」
この質問については、待ち時間を付加価値に変えようとしているからこそ、到着後に失望されては意味がないと。
そのために、通常よりもバッファを持った納期にしておくことで、品質保証とアフターのサポート体制を手厚くしたそうです。
また、一度やってしまえば保障や体制の仕組み部分は別ラインに横展開出来るので、売上以外の面でも付加価値が付いてきたという認識でした。
このお話から見えてくるのは、コミュニティ形成の妙技によって待つことへの苦痛を“儀式化”して緩和出来ていること。
その結果、ユーザーは「自分は特別なプロダクトに携わっている」という高揚感を得ていること。
つまり、それは、儀式的消費が一種の美学のように働き、「共同で作る幻想体験価値」を醸成しているということです。
ではここで、これまで語られてきた内容を整理してみます。
新たに生まれる個人の命題
1. 通説: 「家電は実用重視。早く届き、すぐ使えることが至上。」
・ 大量生産社会の価値観に沿えば、日常必需品としての家電は迅速さが正義と見なされます。
・ 故障時など、待たずに即座に代替品を手に入れることが当たり前という考え方です。
2. 新説: 「機能よりストーリーを優先する投資は、自分の人生を豊かにする。」
・ 少量生産やSNS配信による製造進捗の公開、コミュニティへの参加などを通じて、“家電を待つ過程”が一種のエンターテインメントや学習体験になり得る。
・ まるで美術品やワインを熟成させるように、家電という実用品すら“人生の彩り”として捉える観点です。
・ ここから生じる問いは、「実用か、物語か」どちらに自分は重きを置くのかという決断であり、価値観の再構築が迫られるでしょう。
新たに生まれる社会の命題
1. 通説: 「大量生産社会は豊かさを加速させ、多くの人のニーズを満たす」
・ 大衆消費社会の黄金期には、一貫して“速く安く大量に”が経済発展の源泉であり、社会の福利にも資するとされてきました。
・ また、従来の家電市場は「大量生産」「迅速供給」「機能性重視」という三本柱が常識でした。
2. 新説: 「体験型少量生産社会への転換は、サステナブルで独自の文化を育むが、格差拡大を促進し得る」
・ 少量生産により無駄を削ぎ落とし在庫を最小化することで環境負荷を低減し、同時に“待ち時間”を楽しむという新たな生活文化が生まれる。
・ しかし、製品価格が高騰し、多くの人がアクセスできなくなることで、経済的格差や文化的排他性が増す恐れも高まる。
・ この命題は、「多くの人に行き渡る便利さ」と「限られた人が味わう特別な体験」という対立軸を鮮明に浮かび上がらせます。
こうした命題が私たちに突きつけるのは、「自分はどのような消費行動を選択し、また社会としてどの価値観を重んじるべきか」という根本的な問いです。
大量生産社会の恩恵を享受する一方で、「モノがすぐ手に入るのが当然」という行動パターンに麻痺しているのではないかと。
「待ち時間を価値化する動きは単なる一過性のブームにとどまらず、ポスト大量生産社会の布石になる可能性がある。」
総括すれば、フェラーリが象徴する「待機時間マーケティング」が家電業界へ波及する現象は、大量生産社会への強いアンチテーゼと捉えることができます。
当然、幻想と理想のギャップなど、負の要素は少なくないものの、「消費=単なる機能購入」から「消費=体験や物語の共有」へとシフトさせる可能性を内包しています。
そして、新たな現象として消費の儀礼化(儀礼的消費)が起き始めるのだと。
それは、消費が所属や帰属の入口となり、社会通念としての礼儀となるもので、紐帯を繋ぐ役割を果たすものです。
もしもあなたが「極上の体験を提供する商材やサービス」を目の前にして、数ヶ月、あるいは半年以上もの納期を告げられたとしたら、果たしてどのように感じるでしょうか。
煩わしいと感じるのか、それとも贅沢な期待感として楽しめるのか――。
もしも期待感として提供できるのならば、あえて生産台数を絞り込み、“品切れ”あるいは“予約待ち”を常態化させるという発想は家電業界でも通用するでしょう。
また、家電業界に留まらずあらゆる業界でもスタンダードになり、大量生産・大量消費から生まれる大量廃棄の部分にも貢献する仕組みになっていくでしょう。
問題は、その儀礼を気持ちよく楽しく通過するための仕掛けや物語ができるかどうかです。
企業はミッション、ビジョン、パーパスを内側に設定するだけに留まらず、外部(消費者)に対して、それらを世界観として提供することが鍵になるのかなと。
そんなことを考えさせられました。

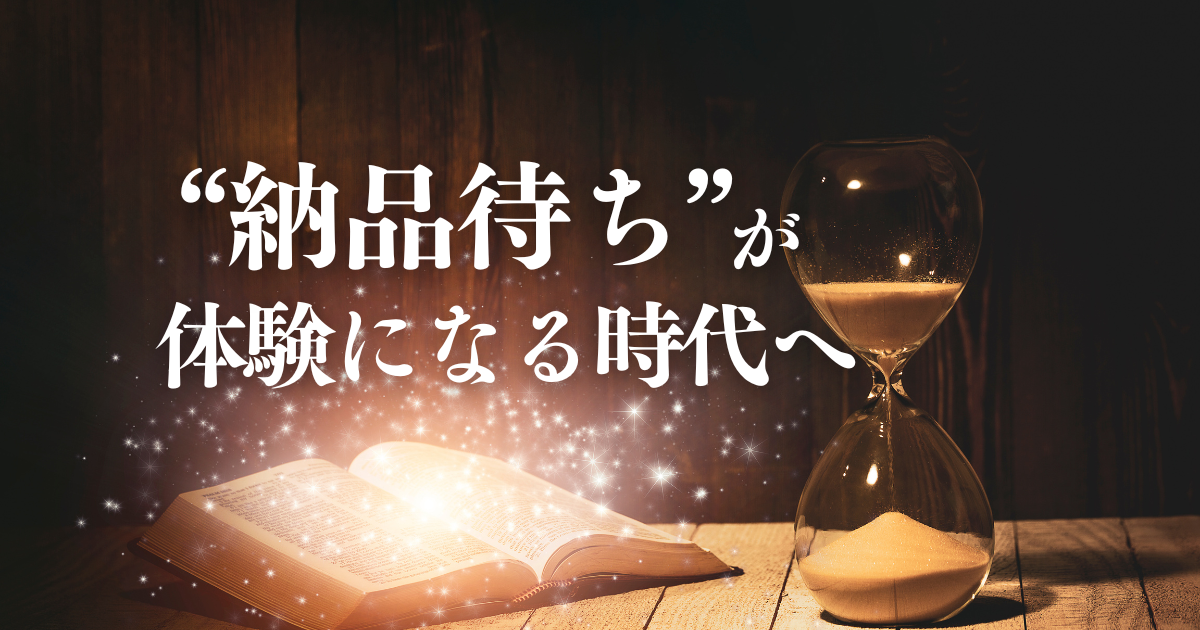

今回の記事から考えたこと
1.儀礼的消費を創造するための商品企画、ストーリー企画、待機時間の仕掛けなどが今後必要になりそう
2.儀礼的消費の普及により、「物を大切にする」という価値観が復活しそう
大量生産、大量消費への問題提起にもなりそう
3.懸念点として供給待ち(不足)により問題が起きないか?
昔あった社会的事件としてナイキスニーカーエアマックスが大人気となり、供給が不足したためにエアマックスが盗難のターゲットになった。強引な場合は履いている人間を襲って奪う「エアマックス狩り」を行う輩も出現し、問題になった
儀礼的消費の要素、考え方を自社の仕事に少しでも取り入れられれば、付加価値をさらに付けられるのではないかと思いました