問題提起
スタジオジブリは日本のアニメ制作会社で、84歳の伝説的な監督、宮崎駿が設立した。
手描きの絵やみずみずしい質感のある色彩、壮大なストーリーを特徴とし、
幼い頃の曖昧な感情と大人になるまでの紆余曲折を思い起こさせる作風で知られている。
―WIRED―
「生涯をかけて磨き上げた、唯一無二の筆致、色彩、そして魂が模倣されている。」
巨匠のスタイルを模倣したAI生成画像がインターネット上で爆発的に増加しています。
そう、誰もがワンクリックで数秒の内に、簡単に無数に再生産できる時代の到来です。
「それは、単なる技術の進歩や一過性の流行として看過すべきものなのか?」
私は、この事態は「文化」が人の手を離れる危険性を持つと考えています。
規範、技術、芸術というのは、世代を超えて伝達されてきました。
そして世代継承の狭間で、選択や変異といった適者生存を経て、今に至ります。
しかし、AIによる特定の文化スタイルの精巧な模倣と、それを可能にする圧倒的な生成力。
そしてデジタルプラットフォームを通じた瞬時の拡散は、文化進化を変えてしまう。
そう、人間の意図や偶然性を超えた、新たな、そして予測不可能な方向へと。
文化が変異、伝播、選択淘汰されていくメカニズムが人間の手を離れた時。
その変化と未来は、私たちにどのような影響を与えていくのでしょうか。
背景考察
ジブリ作品の映像、そして死にゆく森の生き物や湯屋の強欲な幽霊たち、
それらとの失われたつながりという宮崎作品のストーリーラインは、
わたしたちに楽しくノスタルジックな思い出と震えるような悲しみを喚起させる。
大聖堂の写真は聖堂自体がなければ意味をなさない。
同じように、ジブリの作風をコピーしても、
宮崎作品から喚起される美しさに対する集団的な感情がなければ意味がない。
―WIRED―
「私たちの文化は、太古の昔から、生物進化のメカニズムにも似たプロセスを経ている。」
イギリスの進化生物学者リチャード・ドーキンスはミーム理論を提唱しました。
それは、生物の遺伝子のように文化の進化は複製、変異、選択を経て広まると考える理論です。
例えば、ある集団で新しい技術や物語が生まれた時を想像してみてください。
それは模倣や口承、あるいは文字や絵画といった媒体を通じて、世代から世代へ「伝播」されます。
また、その伝播の過程で、文化要素には「変異」が生じます。
例えば、人々の解釈の違いや記憶の曖昧さ、あるいは意図的な改変によって。
そして、環境への適応に役立つ技術、人々の心を強く動かす物語。
或いは、社会的な規範に適した習慣といった文化要素が、「選択」されていきます。
つまり、ゆっくりと、しかし確実に、人が介在することで変化を遂げるということです。
「ミームの変異を生み出し、選択する主体は、いつの時代も人間のクリエイターや編集者だった。」
新聞、ラジオ、テレビといったマスメディアは、ミームの「伝播」速度を飛躍的に向上させました。
しかし、生成AIの登場は、この文化進化の全ての段階に質的な変容をもたらすでしょう。
AIは、インターネット上に存在する膨大なデータ(数兆個のミームの宝庫です)を学習します。
では、あらゆる文化や要素のパターンを詳細に把握した先には何があるのでしょうか。
それは、人間の意図や偶然性を超えた無数の「アルゴリズムから生まれた文化」です。
つまり、文化の「変異」が人間の創造性からAIアルゴリズムへとシフトするということです。
かつての変異には、模倣の不完全さがあればこそ、そこに愛着が宿ったものです。
例えば、新人漫画家が有名漫画家を真似て99%の模倣に1%のオリジナルを介在させたように。
読者はそこに価値を見出して、まるで一派のように絵柄の好みで推しを決めていたように。
しかし、アルゴリズムは、ユーザーの行動データや一定の基準に基づいて取捨選択を図ります。
例えば、特定の色彩構成や構図が、多くのユーザー層のエンゲージメントを最大化すると予測した場合。
AIはその特徴を持つ「アルゴリズム産の文化」を大量に生成し、集中的にユーザーに提示します。
そこに情感は存在しません。
「多様性は、いずれアルゴリズムによって淘汰されるだろう。」
アルゴリズムは、グローバルなレベルで異なる文化要素が似通ってくる現象を引き起こします。
それは、まるで外来種が在来種を駆逐して生物多様性を低下させるような、ミームの収斂作用です。
すると将来的に、伝統的な建築様式や地域の祭りの音楽といった固有の文化要素は淘汰されるでしょう。
しかしその一方には、AIによる創造の機会拡大という輝かしい未来があることを忘れてはいけません。
生成AIツールは、高度な技術や専門知識を持たない人々に、確かな価値をもたらします。
それは、自身のアイデアや感情を、視覚的或いは聴覚的なコンテンツとして具現化する力です。
誰もが手軽に「ジブリ風」の画像を生み出し、自身の感性を表現できるようになった。
その事実は、創造性の敷居を劇的に下げ、多くの人々に生産性向上のきっかけを与えています。
現に、ChatGPTを用いて営業資料やレポート提出を乗り切った方は多いはずです。
だとするならば、文化的多様性や文化的記憶を守るための試みが必要になると考えられます。
例えば、特定の文化をAIの影響から隔離する「文化的保護区」の創設。
或いは、文化的多様性を促進するための「バイアスフリー・アルゴリズム」開発です。
「見失ってはいけないものを忘れないための道標をどこに残しておくべきなのか。」
模倣品が溢れると「本物」や「オリジナル」の価値が揺らいでいきます。
そして何が真に価値のある文化だったのか、次第に思い出せなくなっていきます。
そうならないためにも、現代に生きる私たちがどこに何を残すべきか、真剣に考える必要があります。
【内省】
- 因果的な問い:
なぜ、AIが私たちの文化を驚くほど精巧に模倣し、それを世界中に瞬時に広めることができるほど賢くなったのに、私たちは、AIが生み出す完璧に「最適化された美」よりも、人間の「不完全な」手仕事や、アルゴリズムが効率的ではないと判断する「非効率な」伝統文化に、「感動」や「重み」を感じられるのでしょうか? - 新たに生まれる個人の命題:
・通説:
私たちの美的感覚や文化的嗜好は、個人的な経験や、所属する文化圏、そして社会的な交流を通して、自らの意思で能動的に形成されるものである。
それは、自己表現や個性の一部である。
・新説:
AIアルゴリズムによって、私たちの美的感覚や文化的嗜好は、知らず知らずのうちに特定の方向に偏重され、均質化されていく可能性がある。
個人の「好き」や「美しい」という感覚さえも、アルゴリズムの予測と推奨に影響される受動的な反応となりうる。 - 新たに生まれる社会の命題:
・通説:
文化的多様性は、人類全体の知的遺産であり、社会の創造性や活力の源泉である。その保護と継承は、教育、文化政策、そしてコミュニティの努力を通じて行われるべきである。
・新説:
AIアルゴリズムによって特定のスタイルが偏重され、多様な文化が淘汰される「ミームの収斂作用」が引き起こされる。
文化の保護や継承は、人間の努力だけでなく、AIアルゴリズムの設計、運用、そしてそれに伴う倫理的な基準の策定に強く依存するようになる。
世界には、数えきれないほどの言語、音楽、舞踊、伝統工芸、食文化が存在します。
これらは、それぞれの地域や民族が長い歴史の中で育んできた、かけがえのない宝です。
しかし、アルゴリズムは、世界中で共有されやすい普遍的なスタイルを生成・伝播させようとします。
例えば、ある地域の固有の民謡が、ポップなリズムやメロディーに脚色/変化するなど。
ジブリ風AI画像の氾濫は、今はまだ小さな波紋です。
しかしいずれ、笑って見過ごせるレベルを越えていくでしょう。
私たちは、アルゴリズムに文化の未来を委ねるべきなのか。
それとも、人間として文化進化に主体的に関与し続けるのか、という問いの前に立たされるはずです。
YoutubeやSNS、様々なアプリの「いいね」ボタンを押す前に少し立ち止まって考えてみてください。
それは、本当に残したいと思えるコンテンツだったのかどうかを。
私たちは今、歴史的な岐路に立たされています。
ぜひ、これを機に、より深く想いを巡らせて頂けると私も嬉しいです。

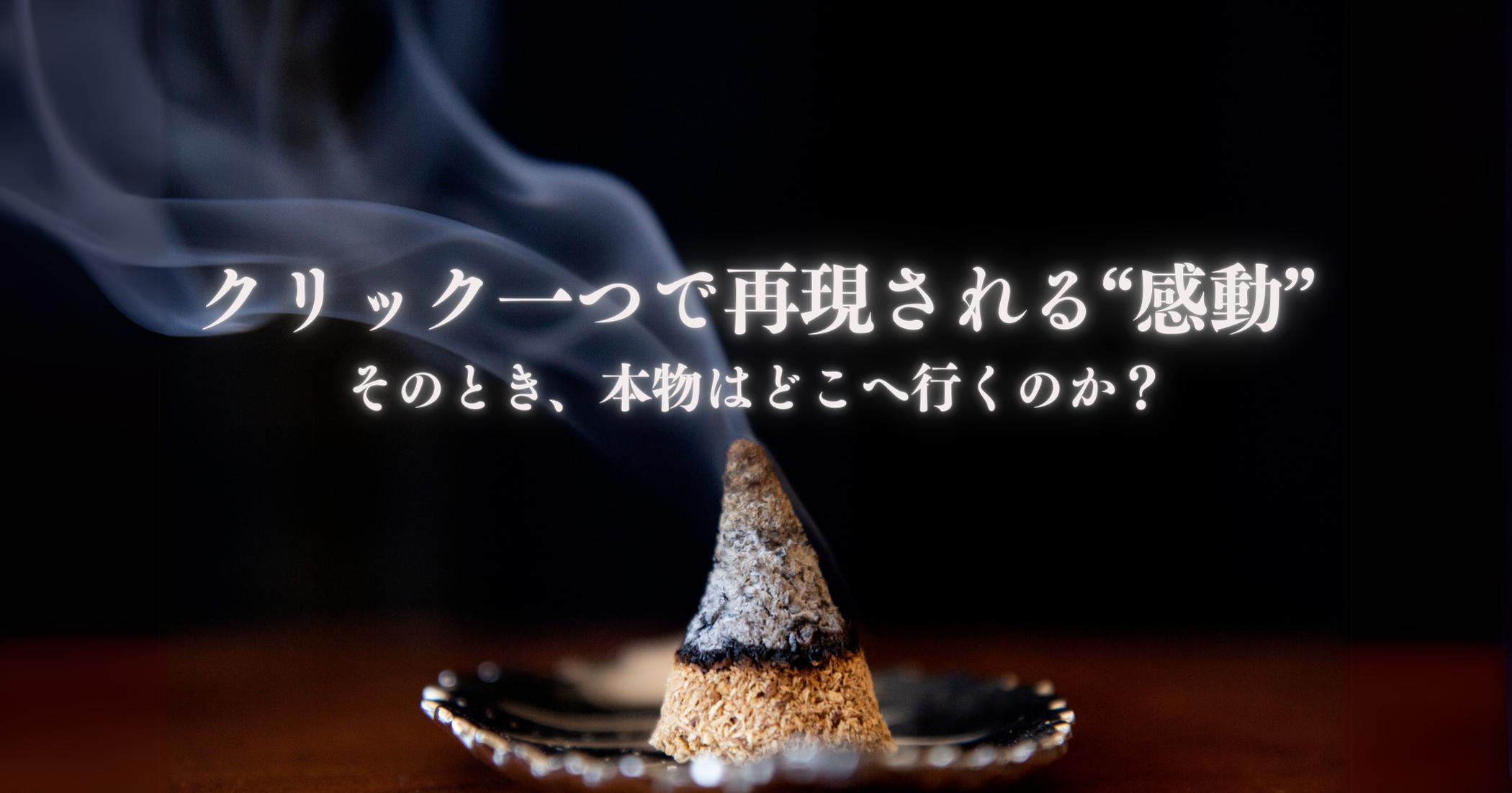
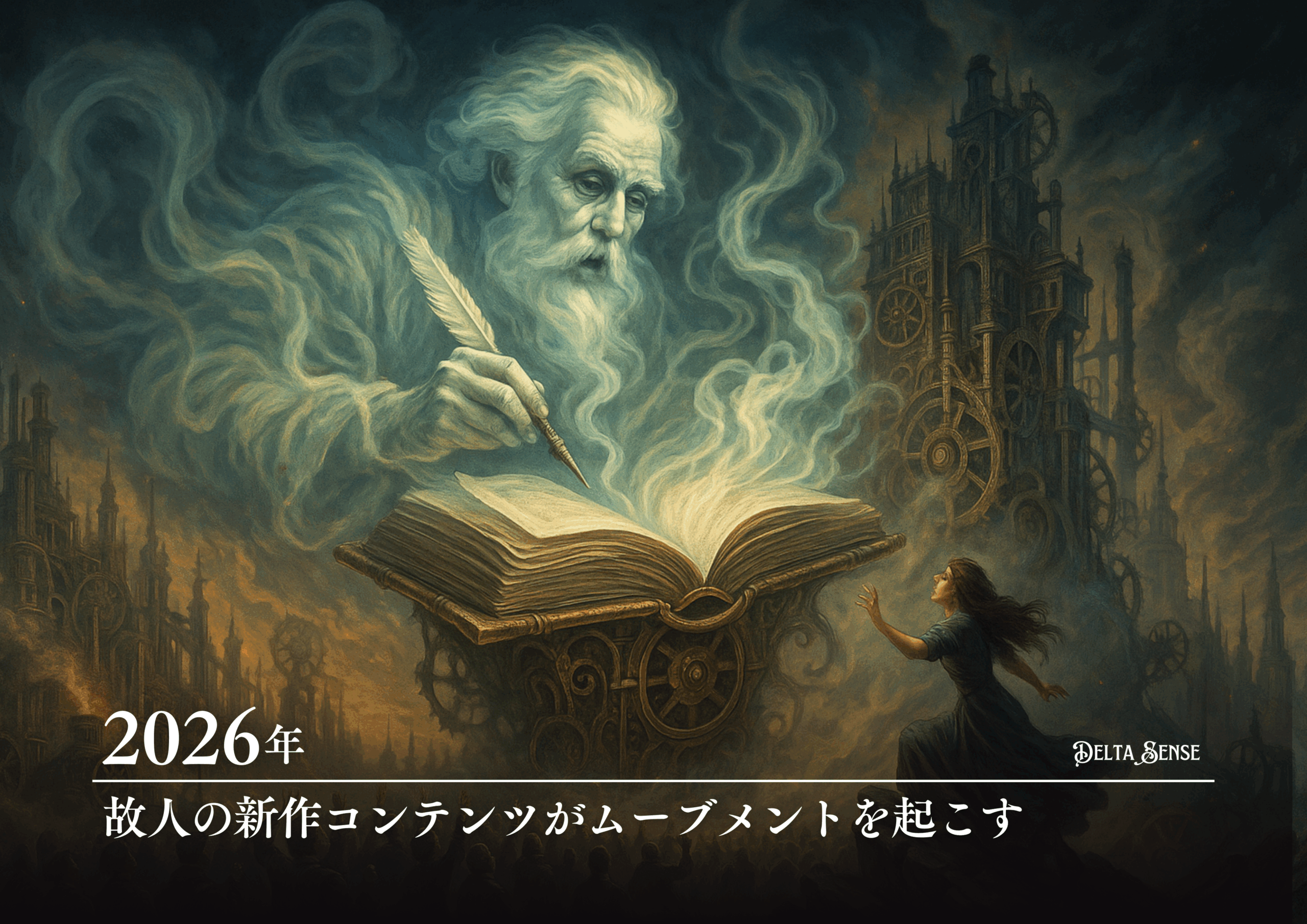
前回のAIエージェントに続きAIの理想と問題点について考えさせられました
便利な半面、AIは人を支配する懸念があると感じた。
そこでふと思ったのが今はスマホなしの生活は考えられず、私自身、何かを調べたり、お店を探す、ナビを使う、SNSを使う仕事を効率化するなど、いつの間にか依存
させられている
スマホに詰め込まれているアプリに依存するように、便利なAIに依存することもそれが汎用化され、誰にでも使えるようになったのならば使うのは当たり前。そしてAIに依存するようになる
人間の本能として「楽をしたい」という欲求があると思う。それをどんどんと満たすのがAIならば、麻薬のように人類を依存させていき、その先はどうなるのか?
文化は人類の歴史であり、それがまた歴史の中で消えゆくのならばそれも必然なのかもしれない
ただ、AIが文化を記録として残すことは可能であると思うので、今後何千年先にも文化の記録は今までより正確に残っていくのかもしれない
ちなみに以下のしつもんをGPTに聞いたらかなりよい回答がきた。私がコメントを考える必要もないのかもしれない(笑)
アルゴリズムに文化の未来を委ねてもいいのですか?という質問に400〜500文字で回答してください
アルゴリズムに文化の未来を委ねることについては、賛否が分かれる重要なテーマです。まず、アルゴリズムの利点を考慮する必要があります。膨大なデータを解析し、人間の意思決定をサポートする力は大きく、例えば、個々の好みに基づいたコンテンツの推薦や、社会問題の解決策の提示においても有効です。これにより、私たちは新しい文化や視点に出会うチャンスが増えることになります。
しかし、一方でアルゴリズムには重大な限界も存在します。アルゴリズムは、与えられたデータとプログラムに基づいて動作するため、人間の感情や経験、歴史的文脈を十分に理解することはできません。結果として、文化や価値観の多様性を軽視したり、偏った情報を助長したりするリスクがあります。また、アルゴリズムによる決定が透明でない場合、権力の集中や不公平な扱いを招く可能性もあります。
したがって、文化の未来をアルゴリズムに完全に委ねるのは危険であり、慎重なアプローチが求められます。人間のクリエイティビティや倫理的判断、コミュニケーション能力を活かすことが、持続可能で豊かな文化を築くためには不可欠です。アルゴリズムと人間の協力を考える際、技術の利用と倫理的側面のバランスを保つことが鍵となるでしょう。私たちは技術を道具として使いつつ、その背後にある文化や人間性を忘れずに、未来を形作っていく必要があります。