問題提起
「明日の朝7時、目覚ましをセットして。」
静かな夜、あなたがスマホに語りかける。
スマホは優しい声で「はいはい。」と応じる。
しかし、その声はあなたの母親の声にそっくりだった。
「俺だよ、俺!」
ある朝、仕事に向かう途中で、見知らぬ番号から電話がかかって来た。
出ると聞き慣れた親友の声だった。
「ごめん、マジでごめん。実は、大変なことになっちゃって、今すぐお金が必要なんだ…」
おそらく、あなたは一瞬、心がざわつくことでしょう。
しかし、それらの声が、たった数分の音声データからAIが生成した偽物だとしたら何を感じますか?
これは、SF映画の物語ではありません。
私たちはずっと「耳」を信用してきた。
声は、体温や匂いのように本人性の最後の砦なのだと。
しかしAIは、数分の録音から声色をほぼ完璧に複製してしまう。
今、世間では「AIカバー」「合成ナレーション」「推しの目覚まし」がバズっている。
しかしその裏側では、本人が一度も発していない言葉が、まるで本人かのように存在している。
そう、耳はたやすく欺かれ、本人性は景色のように加工される時代が到来しているのです。
これから先、私たちは何を信じればいいのか。
そして、私たちは、いったい何を失い、何を得るのだろうか。
背景考察
「267名もの声優の声が、本人の許可なくAIに無断利用されていた。」
2024年の初頭、日本の声優業界に大きな波紋が広がりました。
日本俳優連合が技術進化に明らかな危機感を募らせたからです。
「声は単なる商売道具ではなく、一生かけて築いてきたアイデンティティの一部だ。」
声優事務所の関係者からも切実な声が上がりました。
AI歌唱動画やキャラクターグッズなど、その用途は多岐に渡り、収集がついていないと。
それは、VOCALOID(ボーカロイド)とは全く別で、権利を無断で侵害するものでした。
「私の声ではあるけれど、私のものではない、みんなのミク。」
「(自分が死んでも)ミクは歌い続ける。」
ちなみにVOCALOIDとは、ヤマハが開発した歌声合成技術です。
そして「初音ミク」は、その技術を使い、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に発売したソフトウェアです。
声の起源は、声優・藤田咲 氏です。
そこに、青緑色のツインテールを持つキャラクターのイメージを付与しています。
ユーザーにとってこれは革命でした。
なぜなら、このソフトウェアを使えば、誰でも自由にメロディと歌詞を入力して初音ミクに歌を歌わせることができるようになったからです。
発売から20年近くなる今、投稿された初音ミクが歌う楽曲は数十万曲以上に昇るとされます。
また、「初音ミク」を起用した企業の広告キャンペーンやコラボレーションは国内外で経済効果100億円を優に越えています。
「初音ミク成功の鍵は、技術そのものよりも、二次創作を促進する「場」と「ルール」を設計した点にある。」
声を保護するのではなく、あえて解放し、コミュニティの創造性に委ねるという戦略。
それは、ハリウッド型のトップダウン式IPビジネスとは対極にあり、日本独自の文化的エコシステムの成功例でした。
しかし、それも全ては権利(ルール)に基づくものでした。
声優たちの声が無断で使われている昨今の事例とは全く異なることが想像出来るかと思います。
つまり、それは、日本のサブカルチャーを支える声優が直面する、ある種の「労働とアイデンティティの危機」を象徴しています。
想像してみてください。
漫画家やイラストレーターが描いた絵には「著作権」があります。
音楽家が作った曲には「著作隣接権」や「演奏権」があります。
しかし、声という私たちの「自己そのもの」には、それを守る明確な法的な概念がまだないのです。
この「法の空白地帯」で、AIは猛烈なスピードで私たちの声を“食べて”いる。
そして、その技術は、エンターテイメントの世界をはるかに超えて、私たちの日常にまで侵食し始めています。
声優の声を無断で使って作られたAI歌唱動画をご覧になったことはありますか?
実は、多くの視聴者は喜び面白がるものの、なぜか「不快感」を覚えるというコメントが多いのです。
一体、何がそうさせているのでしょうか。
それは、声の「所有権」或いは「財産権」が侵害されたからでしょうか?
もちろん、それも一因かと思います。
しかし、もっと深い部分に、私たちは何かを感じているのかもしれません。
そう、「魂」です。
AIは完璧な音程で歌い上げるかもしれない。
しかし、そこには、声優が何年もかけて培ってきた感情や、キャラクターへの想いが欠けている。
そしてもっと言えば、「人生の物語」が欠けているように感じられるのです。
私たちの声は、単なる音波の集合体ではありません。
それは、私たちが経験した喜びや悲しみ、葛藤や決断といった、「人生の痕跡」が刻み込まれた唯一無二のものです。
AIは、その痕跡を正確に模倣することはできても、その痕跡を「体験」することはできない。
つまり、AIは「声」のコピーは作れても、その声に宿る「魂」のコピーは作れていないのです。
そう、それが今の現状と言えるでしょう。
結論
「声は、身体の一部だろうか?それとも、データだろうか?」
将来的に、人間の身体情報はデジタル化が可能かどうかで区別されていくでしょう。
その時、デジタル化可能な領域は「デジタル・ボディ・プロパティ」(造語)として区別されるのかなと。
すると、声は指紋やDNAと同じように、私たちの身体に固有の、唯一無二のものであるはずだという境界線が曖昧になるでしょう。
なぜなら、AIによってデータ化され、複製され、自由に加工できるようになる時代はさらに加速するからです
いずれ、「声に魂が乗った」と錯覚するようなレベルまで到達するのかもしれません。
では、その時、声は誰のモノになるのでしょうか?
この問いに、誰もが納得できる答えをまだ見つけられていません。
しかし、答えがないからこそ、私たちは立ち止まって考える必要があるのだと思います。
AIは、私たちから「声の所有権」或いは「財産権」を奪いつつあります。
それは、まるで中世の領地争いのように、誰がこの新しい「声の領土」を所有し、管理するのかという闘いの始まりなのかもしれません。
この闘いは、単に法律や技術の領域にとどまらず、私たちの感情、倫理、そして人間そのものの定義にまで及ぶ、壮大な物語の序章です。
この続きは、中長期経営計画を一緒に作る会でお話が出来ればと思います。
用語解説
■ デジタル・ボディ・プロパティ(Digital Body Property)
定義: 個人の身体から生み出される、声紋、顔、心拍数といったデジタル化可能な生体情報。
由来: 身体の不可侵性を扱う伝統的な哲学・法学概念と、デジタル資産の所有権を議論する現代の法学・経済学の交差点から生まれた造語。
この記事では、声紋を「個人のアイデンティティに紐づく、最も重要なデジタル・ボディ・プロパティ」としています。これは、単なるデータではなく、個人の尊厳を象徴する不可侵の資産であり、その利用には厳格な法的・倫理的規制と本人の明確な同意を必要とするのではないかと。

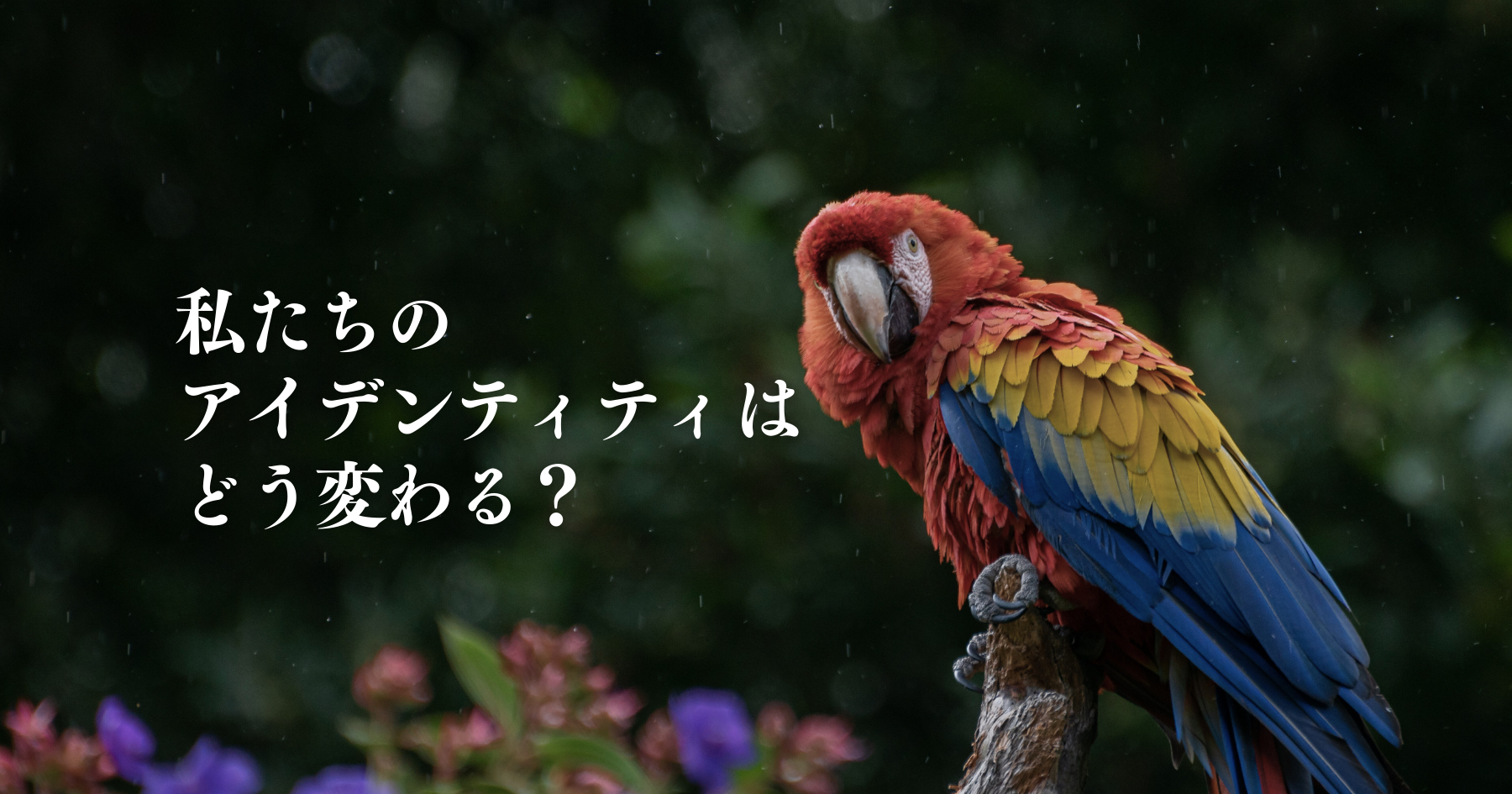
AIの技術進歩により、声の複製が容易になったり、画像や写真の複製も容易になる。それらを組み合わせるとリアルかAIによる複製か、本当に見分けがつかなくなるかもしれない。そこまでになると従来の著作権という法律や肖像権など関係するあらゆる法律や規制を見直す必要になるかもしれない。AIの発展はわれわれの想像を超えるというか予想できない面も多いと思う。
我々はそれに対応できるのか?
今後が楽しみでもあり、恐ろしくもある。
RWAの延長線として、RPA(Real Person(もしくはpersonal?) Asset)みたいな実物資産ではないが、唯一無二、かつ個人に帰属する無形資産に対する価値を保証するようなNFTが出てきて、その権利を各個人が状況に応じて価値に変えることができる。そういうことに挑戦している会社もすでにありますし、マイナンバーの延長線上で、個人情報に関する価値を個人へ帰属させるような仕組みが出てくれば色々と状況が変わってくるかもしれませんね。