問題提起
「——あなたは、何年前の音を覚えていますか?」
夕暮れの京都、四条通(京都市の中心部を東西につなぐ主要な幹線道路)を歩くと、どこからともなく囃子の音が近づいてくる。
耳に届いた瞬間、ふしぎなことが起きる。
今年の音なのに、なぜか子どもの頃の夏休みが蘇る。
屋台の甘い匂い、祖母の浴衣の手触り、肩車してくれた父の背中の高さ。
それは、一度しかなかったはずの時間が、重ねられた音によって何度も呼び戻される瞬間です。
この現象が経済学で語られることはありません。
なぜなら、経済は「今ここでお金が動く瞬間」を追いかけるから。
記憶が長い時間をかけて価値を生み出すことを測定する術を持たないからです。
あなたは、京都の祇園祭をご存知でしょうか。
そのお祭りは、1,100年以上の時を超えて、毎年同じ季節に、同じ場所で繰り返されてきました。
祇園祭は、現代人が必死に追い求める「新しさ」や「効率性」とは真逆の存在です。
それは、まるで時が止まったかのような、非効率的で手間のかかる、古風な儀式なのです。
ではなぜ、そんなにも古く、非効率なものが、現代人の心を惹きつけるのでしょうか?
その理由について、今の私たちは気付きつつあります。
すべてが即時的に消費される時代において、「覚えている」ということが、どれほどの資本になるのかを。
これは単なる観光資源の話ではありません。
この祭りの奥底には、人々が忘れ掛けている「記憶の価値」と、未来を生きるヒントが隠されています。
今回はその奥行きを照らして行きたいと思います。
背景考察
「注意経済(アテンションエコノミー)は、「刹那の経済」とも言える。」
注意経済は、短期的な利益、瞬時の満足、そして絶え間ない「新しさ」を燃料としています。
例えば、エンターテイメント業界。
音楽も、動画も、新しいものが次から次へと登場し、ヒットチャートは目まぐるしく入れ替わります。
「一つのレコードを擦り切れるほど聴き込んだり、お気に入りの映画を何度も何度もビデオで観返したりする人は少数派になった。」
今や、YouTubeやNetflixは好みを学習し、次に観るべきコンテンツを無限に提示してくれます。
これは非常に効率的で便利ですが、その結果、ある習慣が失われたとも感じられます。
それは、「振り返るという習慣」です。
京都・祇園祭。
一方で、祇園祭はこの「刹那の経済」とは対極に位置しています。
およそ1,100年の歴史をもつこの祭りは、観光客150万人を呼び込み、年間200億円もの経済効果を生み出す地元の誇りです。
もちろん数字を見れば立派な観光産業なのですが、実はその本質はもっと地味でより深いところにあります。
「今年の囃子の音は去年より軽やかだったね。」「あの山鉾の飾りの位置が、昔の絵と少し違っている。」
なんと地元の町衆は毎年、山鉾の車輪の軋み具合や、囃子の音の“揃い”を聞き分けているのだと言います。
また、祇園祭の山鉾町では、住民たちが古文書を紐解き、先祖が残した記録を頼りに、懸装品(けそうひん)と呼ばれる豪華な装飾品を修復し、山鉾を組み立てています。
これは、単なる記録ではありません。
それは、世代を超えて受け継がれる「微差記憶」(造語)とでも呼ぶべきものです。
つまり、祭りとは、微差の記憶が積み重なることで生き続けているということです。
これは、TikTokのたった8秒のショート動画がどれだけ再生されても生まれることのない価値だとは思いませんか?
そう、そこには記憶を交換し、更新することで維持される経済が確実に存在している。
私はこれを「残響経済(メモリカル・エコノミー)」(造語)と呼んでいきたいと思っています。
それは、文化財の保存だけでなく、ブランドや企業にも通じるものです。
例えば、何十年も使われている喫茶店の椅子の傷や、老舗旅館の帳場に残る手書きの予約簿。
そこには、即効性ではなく、反復される時間の蓄積が宿っています。
とするならば、祭りの本質的な価値は、お金には換算できない「記憶の更新と反復」にあると捉えることが出来ます。
またちなみに、祭りの修復費用や運営費は、地域住民や支援者からの寄付や協賛で賄われています。
これは、言い換えれば単なる金銭のやり取りではなく、「記憶や誇りと交換している」と捉えることが出来るでしょう。
すると、ここで一つの問いが浮かび上がります。
現代の我々が日々を生きる上で、最も避けたいと考えるのが「非効率」とされています。
しかし、祇園祭のコミュニティは、準備/運営においてあえて伝統的かつ非効率な道を選び、それを誇りにしている。
そう、なぜ日本人は手間暇かけて非効率な儀式を守ろうとするのでしょうか?
この矛盾を解き明かす鍵、それが残響経済(メモリカル・エコノミー)にあるのかもしれません。
例えば、現代の私たちが愛する音楽や映画は、すぐにストリーミングで聴いたり観たりできます。
それは便利ですが、その代償として、人々は「待つこと」や「手に入れるために苦労すること」を知らなくなりました。
かつて、レコードを買うためにアルバイトで必死にお金を貯め、発売日を心待ちにし、何度も何度も聴き込んだ。
そうして手に入れた一枚のレコードには、単なる音楽以上の、自分自身の記憶が宿っていました。
祇園祭の山鉾を組み立てる職人たちも、毎年同じ作業を繰り返す中で、先祖が残した技法や物語を体で覚えています。
それは単なるマニュアルの暗記ではなく、自分自身の人生と重ね合わせた「物語」として継承されているのです。
そう、つまり、もしかしたら、私たちが今本当に求めているのは、安易に手に入る「情報」ではなく。
苦労や時間をかけてようやく手に入れる「記憶」そのものなのかもしれませんね。
結論
注意経済(アテンションエコノミー,以前は反響経済とも呼ばれていた。)及び刹那の経済が支配する現代において。
祇園祭は、「記憶を交換する経済」という、全く新しい価値観を私たちに提示しています。
それは、お金や物ではなく、物語や経験、そして共同体で共有された「記憶」そのものが価値を持つ世界です。
しかし、この美しくも古風な経済モデルにも、現代社会の波は容赦なく押し寄せています。
少子高齢化による担い手不足、都市住民の流動性の高さ、そして効率性を求める市場原理。
伝統の存続は、今まさに危機に瀕しているのです。
このまま「純粋主義」を貫き、伝統を閉鎖的に守り続けるべきなのか?
それとも、「拡張主義」を受け入れ、デジタル技術や外部資本の力で、伝統を現代に再接続すべきなのか?
中長期経営計画を一緒に作る会では、この二つの哲学が激しくぶつかり合う、現代の「記憶をめぐる戦い」を紐解いていきます。
あなたがこの物語に触れることで、忘れていた何かを思い出すきっかけになることを願っています。
用語解説
■刹那の経済(Momentary Economy):
「新しさ」や「効率性」、そして短期的な利益を最優先する現代の経済モデル。SNSのトレンドやファストファッションなど、一瞬で生まれ、一瞬で消費される商品やサービスがその象徴。
■微差記憶(Subtle Memory):
長年同じ経験を繰り返すことで、過去とのごくわずかな違いや変化を敏感に感じ取る能力のこと。祇園祭の囃子の音や山鉾の装飾の微細な違いを記憶し、共有する文化にその例が見られる。
■残響経済(メモリカル・エコノミー)(Memorial Economy):
このコラムで提唱される仮説的な経済モデル。モノやサービスの交換ではなく、「記憶」や「物語」の交換そのものに価値を見出し、コミュニティの持続性を支える仕組みのこと。

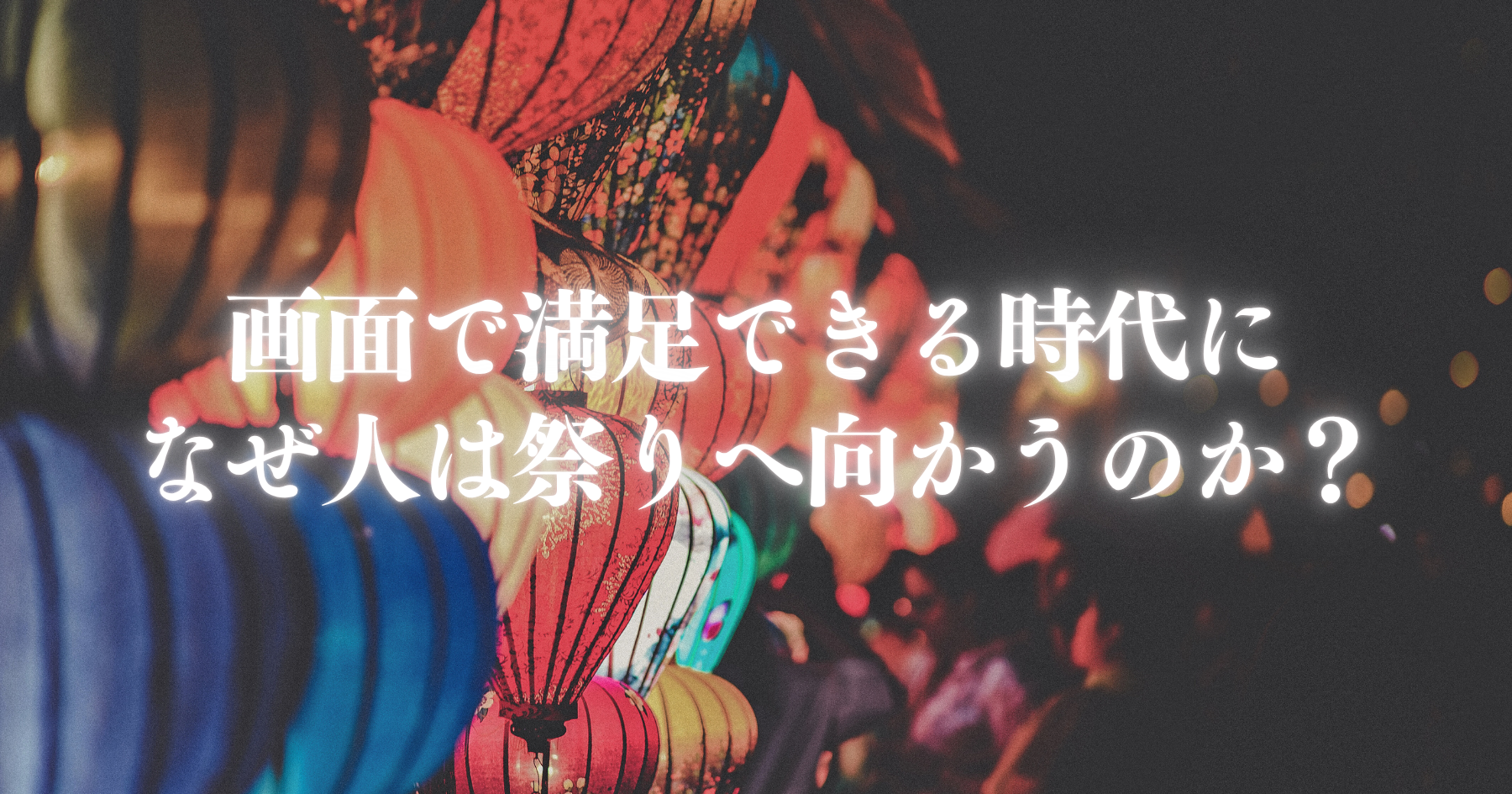
この記事へのコメントはありません。