問題提起
「今日のあなたは、どんな一日でしたか?」
会社の人事評価に一喜一憂して、夜の街に繰り出して同僚たちと将来について語り合った。
子どもの習い事の月謝袋を眺めて、「これで本当にあの子のためになるのだろうか」と、ふとため息をついた。
あるいは、SNSに投稿した写真についた「いいね!」の数を、無意識に数えてしまった。
私たちは、実に様々な「モノサシ」に囲まれて生きています。
そして、そのモノサシが示す目盛りを少しでも上げようと、日々努力を重ねている。
それが公正で、客観的で、正しいことだと信じて。
しかし、もしもその「公正なモノサシ」に何かあるとしたら?
私たちを息苦しくさせ、見えない格差を広げ、社会全体の活力を静かに奪っているとしたら?
そして、もしその仕組みが、あなたが生まれる遥か昔、1300年以上も前から何度も繰り返されてきているとしたら…。
本日は、少しだけ想像の翼を広げてみましょう。
舞台は、きらびやかな現代のオフィスビルではありません。
土埃の舞う、古代中国の都です。
そこには、一つの「評価システム」に人生のすべてを賭け、そして絶望していく人々がいました。
彼らの物語は、遠い歴史の彼方にある埃をかぶった記録ではありません。
それは、驚くほど鮮明に、現代の私たち自身の姿を映し出す、一枚の合わせ鏡です。
すべての始まりとなった、その奇妙で、あまりにも人間的な制度の話。
そこから視える、将来の私たちの姿を想像してみましょう。
背景考察
その制度の名は、科挙。
隋の時代に始まり、清の時代に終わるまで、実に1300年もの間、中国大陸を支配した官僚登用試験です。
「家柄や身分は関係ない。学力さえあれば、誰でも国の重要な役人になれる。」
その理念は、当時としては画期的にして革命的でした。
まさに、現代の私たちが理想とする「機会の平等」の原型がそこにあったのです。
「人々が科挙に人生を捧げて熱狂したのも無理はない。」
貴族が地位を世襲するのが当たり前だった時代。
貧しい農民の子でも、努力次第で宰相にまでなれる道が開かれていたのです。
「万般皆下品、唯有読書高(学問以外のものは全て下品であり、ただ読書だけが尊い)」
当時、価値観が社会を覆い尽くし、無数の若者たちが、人生の一発逆転を夢見て、この超難関試験に挑みました。
では、その「公正」なシステムがもたらした現実とは、どのようなものだったのでしょうか。
いくつかの数字を見てみよう。
最終試験である「殿試」に合格し、エリート官僚の仲間入りを果たせる「進士」になれる確率。
それは、一説には0.1%にも満たなかったといいます。
まさに「千軍万馬が一本橋を渡る」と形容されるほどの過酷さです。
そして、その難関を突破した合格者の多くには共通点がありました。
それは、結局のところ、官僚や地主といった、すでに裕福な家庭の出身者で占められていました。
理由は単純明快です。
試験勉強には、莫大なコストがかかったからです。
一切の労働から離れ、何十年もの間、ただひたすらに儒教の経典を暗記し、決められた形式で論文を書く訓練に明け暮れる。
そんな生活を支えられるのは、当然ながら経済的に恵まれた家庭だけだった。
貧しい農民の子が合格する話は、あまりに稀だからこそ、美談として語り継がれたに過ぎない。
「公正なはずのモノサシは、いつしか、スタートラインに立つための「参加費」を払える者だけが有利になる、出来レースへと姿を変えた。」
小説『儒林外史』には、50歳を過ぎても科挙に合格できず、合格の報せを聞いたショックで精神に異常をきたしてしまう男の姿が、滑稽に、そして悲しく描かれている。
その姿は、現代の成果主義のプレッシャーに心を病むサラリーマンや、過度な受験戦争に疲弊する子どもたちの姿と、どこか重なって見えませんか。
この「科挙の罠」は、決して過去の遺物ではありません。
現代の日本でも、難関中学への合格者の親の平均年収が、一般家庭のそれを大きく上回るというデータは珍しくありません。
また、米国のアメリカン・ドリームを象徴する名門大学入試にも、同じような矛盾が潜んでいます。
それが「レガシー枠」と呼ばれる、卒業生の子弟を優遇する制度です。
巷では、能力とは無関係に、家柄や経済力が合否を左右する、まさに現代の「貴族制度」と言われています。
ハーバード大学の元学長による論文が示すように、レガシー枠の合格率は、一般の志願者の約6倍にも達するそうです。
努力が報われるべき場所で、努力だけでは超えられない壁がそびえ立っているのです。
或いは、スポーツの世界に目を向ければ、アメリカのIMGアカデミーのようなエリート養成機関があります。
年間1000万円以上の費用と引き換えに、最新の科学的トレーニングと最高の指導者が提供される「才能養成機関」です。
これもまた、形を変えた「教育投資」が子どもの未来を左右する、現代版の科挙と言えるでしょう。
伏線
「公正なはずのシステムが、経済格差を再生産している。」
この構造は、ある程度、直感的に理解できるのではないでしょうか。
しかし、この「科挙の罠」の本当に恐ろしいところは、もっと根深く、私たちの日常に潜んでいます。
それも、「善意」という美しい仮面をかぶって。
例えば、ESG投資という言葉を聞いたことがありますか。
それは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の三つの観点で企業を評価すること。
そして、「良い行い」をする企業に投資をしよう、という考え方です。
素晴らしい理念で、利益一辺倒だった資本主義が、ようやく地球や社会全体のことを考え始めたと。
美しい一歩に見えると称賛の声が挙がる考え方です。
しかし、少し立ち止まって考えてみてほしい。
企業が「良い行い」をしているかどうかを、誰が、どんなモノサシで測るのでしょうか。
今、世界中のコンサルティング会社や格付け機関が、この新しい評価基準の策定を競っています。
そして、企業側は、その評価で高いスコアを得るために、専門の部署を作り、多額の費用をかけてレポートを作成し、アピール合戦を繰り広げている。
どこかで見た光景ではないだろうか。
評価基準が複雑化し、専門家でなければ対策が立てられなくなる。
対策にはコストがかかり、体力のある大企業が有利になる。
そして、本来の目的であった「地球環境を良くする」という本質から離れ、「いかにESG評価で高いスコアを取るか」というゲームが始まっていくと。
これはまさに、科挙が「いかに国を良くするか」ではなく「いかに試験に合格するか」というゲームに堕していったのと同じ構造を持っています。
またさらに、もう一つ、身近な例を挙げていきます。
それがAIによる採用です。
人間の面接官が持つ偏見や主観を排除し、経歴やスキルといった客観的なデータだけで候補者を判断する。
これもまた、より公正な社会を目指すための、善意から生まれたテクノロジーです。
しかし、そのAIが学習する過去のデータに、そもそもバイアスが潜んでいたらどうなるのか。
例えば、過去の採用実績データが男性に偏っていた場合、AIは「男性であること」を評価の高い要素として学習してしまうかもしれない。
結果として、AIは人間の差別を、より巧妙に、そして「客観的」というお墨付きを与えて再生産する、最も冷酷な差別主義者になり得るのです。
結論
「私たちは、呪いを繰り返しているのかもしれない。」
科挙、中学受験、ESG投資、そしてAI採用。
それらは一見すると、全くバラバラな事象に見える。
しかし、その奥底には、奇妙なほどよく似た「構造」が横たわっています。
あなたも気づき始めたのではないだろうか。
①. まず、より公正な世界を目指して、善意から「新しいモノサシ」が発明される。
②. 次に、そのモノサシで測られる競争が始まり、対策が高度化・専門化していく。
③. そして、対策にコストをかけられる者が有利となり、新たな格差と序列が生まれる。
④. 最後に、本来の目的は見失われ、モノサシが示す「スコア」を上げること自体が目的化する。
まるで、ギリシャ神話のシーシュポスのようです。
私たちは、良かれと思って「公正なモノサシ」という名の岩を懸命に丘の上まで押し上げては、その岩が麓まで転がり落ちて、新たな不条理を生み出すのを呆然と眺める。
そんな、哀しい呪いを、私たちは何度も何度も繰り返しているのかもしれません。
では、この呪いの正体とは、一体何なのか。
なぜ私たちは、これほどまでに「測る」ことと「測られる」ことに囚われてしまうのでしょうか。
この続きは、中長期経営計画を一緒に作る会でお話させて頂きます‥!
用語説明(前編)
■ 科挙(かきょ)
意味: 古代中国で約1300年間続いた、役人を選ぶための超難関ペーパーテスト。
由来: 「科目」によって人材を「選挙」することから。それまでは家柄で役人が決まっていたので、「誰にでもチャンスがある」という画期的なシステムだった。
背景: この試験に合格することが人生のすべてであり、多くの人が青春、いや人生そのものを捧げた。現代の受験戦争や就職活動の、壮大なご先祖様のようなもの。
■ ESG投資(イーエスジーとうし)
意味: 「環境(Environment)」「社会(Social)」「企業統治(Governance)」の3つのポイントで企業を評価して、応援したい会社にお金を投資するやり方。
由来: 2006年に国連が提唱したのがきっかけ。「儲かれば何でもOK」ではなく、「地球や社会に良いことをしている会社こそが、将来的に伸びるはずだ」という考え方。
背景: 今、世界中の大金がこのESG投資に集まっていて、企業も「私たちは良い会社ですよ」とアピールするのに必死。新しい時代の「企業の通信簿」になりつつある。

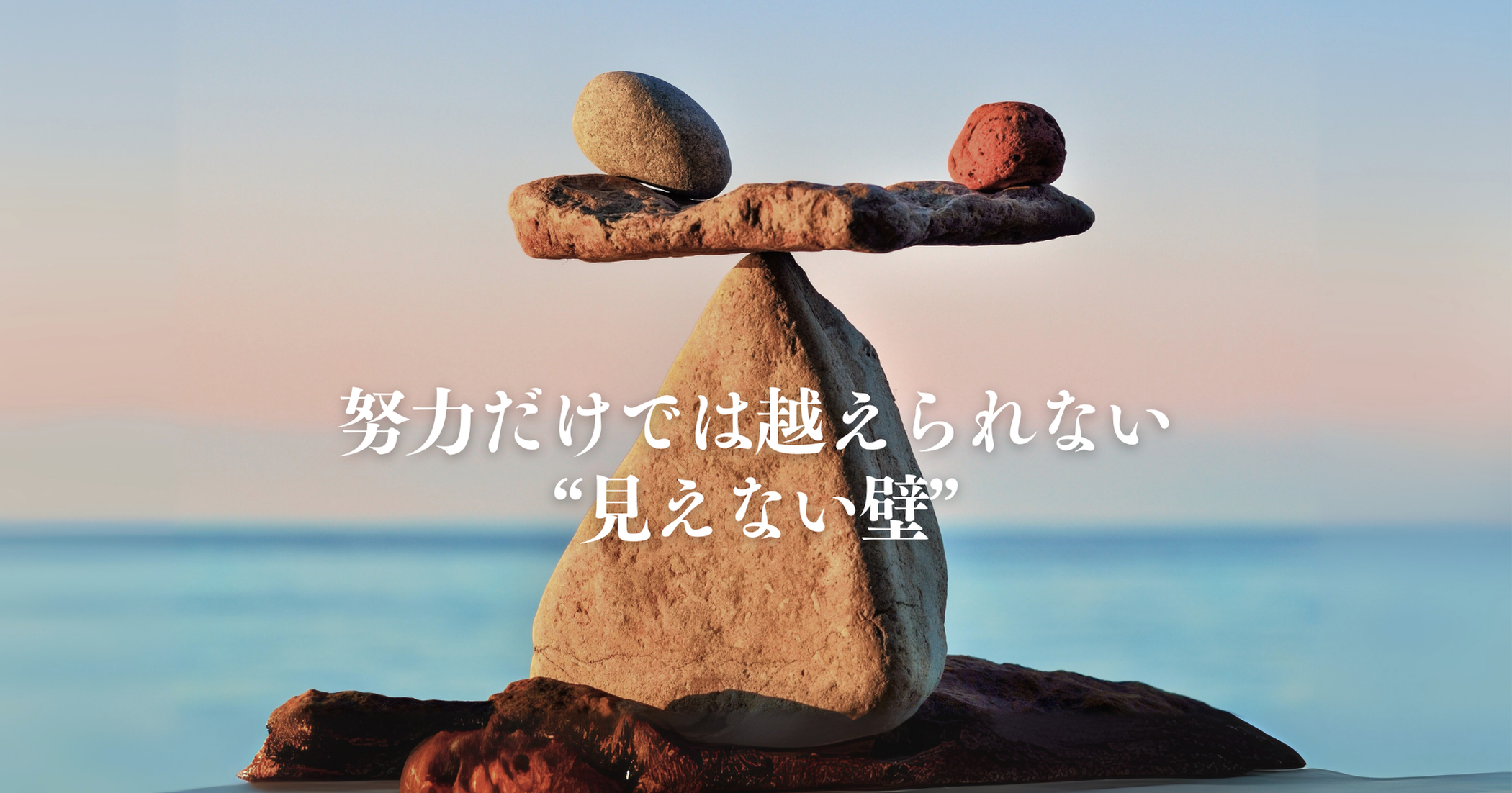
資本主義社会の負の部分である貧富の格差が生まれる要因が実は自由競争に思える社会が、持つものが初めから優位に立つ出来レースのような構造に陥っているのではないか?
しかし、ある意味これは今の社会の仕組み上、ある程度は仕方ないと私としては許容する部分もあるが、行き過ぎる点、または明らかにルール自体がおかしな点は是正していくべきであると考える
1.できる対応としては
➀「足ることを知る」生き方を知る
とにかく他者より豊かな生活をしなければいけない、金を稼がなくてはいけないとなりがちな風潮だが、自分なりの満足や価値観を追求することができれば、この過剰競争のレールに乗らなくても済む。ここでのキーワードは「バランス感覚」だと私は思う
②理不尽であったり間違ったルールであっても、それに乗り、利用する。魂を売るような形になるが「長いものには巻かれろ」という戦略を実行する
③「出る杭は打たれる」というが打つことができないくらい高く飛び抜ける。ここまでいくとルールを作る側になれるのではないか?不公平感のある競争の中で周りを制圧できる強さと運が必要だが
ESG投資に関しては体験談があり、ある企業の移動式エアコンを洗浄したが、かなり汚れていて綺麗になったのだが洗浄に新しく買い換えるより多額の費用がかかった
この企業に「買った方がよい」と話したが周りに洗浄して使うことをPRできるとのことだった。ありがたい話だし、物を大事に使うと言えば聞こえはよいが、なかなか余裕がある企業でないと、これはできないなと感じた
また、大企業は省エネを実現するための予算が多額についており、それを研究し、達成することが命題になっている部門がある
そこから環境改善や省エネの対策でエアコンを主とした空調設備の洗浄を頼まれるが
比較データをとり、提出するため、かなりの高額になる。ただ、そのデータこそが喜ばれるので受注につながるが、これも並の企業では払えない金額であると感じている
そもそもそこまで躍起になって省エネを進める必要があるのか?なんのために?という部分が忘れられていないか?
石油がなくなると40年前に言われたが、それはデマだった。地球温暖化は二酸化炭素のせいと言われるが、それだけが問題なのか?
都市化で土をアスファルトで覆い、いたるところに太陽光パネルを設置し、エアコンを使い、熱い空気を外に捨てる。温暖化する原因を二酸化炭素のせいにだけはできないはずなのにそれを削減することが命題にされている。そして日本でも本格的に排出権取引が開始されると聞いた。ルールがそもそも間違っていたり、誰かに巧妙に仕掛けられた金儲けの道具だったらどうか?
それらに盲目であると現代の奴隷として利用され続けることになると思う