問題提起:見慣れた日常に潜む、奇妙なズレ
「デジタルマップは瞬時に最適な経路を示し、数タップで航空券やホテルが手配できる。」
夜の帳が降りる頃、あなたはスマホの画面に目を落とし、明日の営業ルートを検索しているかもしれません。
あるいは、週末の旅行計画を練り、新幹線の座席を確保しているかもしれません。
私たちは「世界が手のひらにある」かのような、確かな「移動の自由」を謳歌している。
そう、信じて疑いません。
しかし、少し立ち止まって考えてみてください。
その自由は、本当に「誰にとっても」平等なものでしょうか?
先日、ある報道が私の目に留まりました。
地方のバス路線がまた一つ、廃止になったというニュースです。
「私には足がない。どうすればいいのか分からない。」
そこには、バス停で途方に暮れる高齢者の姿が映し出されていました。
スマホひとつで世界とつながる私たちの日常の片隅で、彼らは物理的な移動手段を失い取り残されている。
これは、たまたまその地域に起きた不運な出来事なのでしょうか?
それとも、私たちの社会全体に深く潜む、何か本質的なズレを示唆しているのでしょうか?
私たちは「どこへでも行ける」と思い込んでいる。
しかし、その“どこへでも”には、ある特定の条件が付いているとしたら?
例えば、あなたがもし今日、スマホを落として現金しか使えないとしたら、一体どれほどの移動が困難になるのか。
あるいは、もしあなたが住む地域の公共交通がすべて消滅したら、誰が最も困り、その困窮は、本当に「個人的な不便さ」で片付けられる問題なのでしょうか。
これは、単なる交通手段の話ではありません。
今、あなたの足元で、「移動の自由」という概念そのものが、静かに変容を遂げようとしています。
その変化は、我々の未来にどのような影響を与えるのでしょうか。
背景考察:進化の裏側で失われた、移動の「多様性」
「誰もが自由に移動できる国。日本人の大半がそう信じて疑っていないだろう。」
その認識は戦後の高度経済成長期に始まります。
まず私たちは、新幹線を「夢の超特急」と呼び、日本列島を高速道路で縦断する未来を描きました。
そして国産車メーカーが世界で台頭するのと時を同じくして、次第に一家に一台の自家用車が当たり前に。
テレビCMでは、家族が車で海へ山へと繰り出し、その笑顔は「豊かさ」の象徴として私たちの心に深く刻まれていきます。
やがて日本は、都市と地方を結ぶ高速交通網を整備し、地方の隅々まで路線バスが走り、自家用車が広く普及したのでした。
まるで漫画『美味しんぼ』で、山岡士郎が地方の食文化を訪ね歩くように、多様な移動手段が地域に息づきます。
これは、「国土の均衡ある発展」という理念のもと、地域間の格差を解消し、どこに住んでいても同じような利便性を享受できる社会を目指した結果でもあります。
ちなみに、1960年代にはわずか50万台だった日本の自家用車保有台数は、2020年には約6,200万台へと爆発的に増加しています。
そう、つまり、私たちの移動は、ある種計算通りに飛躍的にパーソナル化されたのでした。
しかし、この輝かしい物語の裏側で、静かに、そして着実に変化が起きていたことをご存知でしょうか?
例えば、かつては生活の足であった地方の路線バス。
実は1980年代をピークに、全国の路線バス事業者は減少し続け、バス路線そのものも大幅に縮小しています。
そう、実は、移動の自由を謳歌しているように見えて、自家用車という「単一の移動手段」への依存が始まっていたのでした。
それが顕著になったのが2020年代です。
皆さん、冒頭に挙げた高齢者を想像してみてください。
彼は、御子息からの助言もあり、長年連れ添った車を手放し、免許を返納していたのかもしれません。
彼にとって、公共交通の縮小は、文字通り「閉じ込められる」ことを意味していました。
かつてはバスで数十分で行けたスーパーや病院が、今や手の届かない場所に。
友人との茶飲み話も、病院の定期検診も、次第に遠のいていくことに心中穏やかとは言えない毎日です。
一度奪われた移動の自由をどうやって回復するべきなのか。
そこで、救済手段の1つとしてライドシェアなど新たな動きが見られます。
また、スマホアプリでバスの時刻を検索し、キャッシュレスでチケットを購入できるMaaS(Mobility as a Service)が登場しました。
しかし、ここに一つの奇妙な矛盾が潜んでいました。
「買い物難民や交通弱者を減らす術は本当にあるのだろうか?」
デジタル技術は「誰でも使える」と謳われる一方で、特定の層を「動けない」状況に追いやっていたのでした。
この物語には、「壁」と「見えない力」が深く埋め込まれています。
壁とは、「透明なガラスの壁」です。
私たちは移動は自由だと信じ、あたかも平坦な道を進んでいるかのように錯覚しています。
しかし実際には、特定の層だけが容易に通過できるガラスの壁が立ちはだかっています。
この壁は、特定の情報(例えば、複雑なMaaSアプリの操作方法)、経済力(LCCとグランクラスの間の埋めがたい価格差)、身体能力(駅の階段やバスの段差)がないと見えず、触れられないため、存在しないかのように振る舞われる。
その結果、壁の向こう側に行けない人々は、自らの努力不足や選択ミスを疑い、社会の構造的問題には目を向けられなくなっていく。
そして、この壁をより強固にしているのが、「見えない交通整理のパラドックス」。
つまり、「自己責任論」という見えない力です。
現代社会の交通システムは、一見すると効率的な交通整理を行っているように見えます。
高速道路、新幹線、航空路が、まるで高度に統制されたオーケストラのようです。
しかし、この「交通整理」は、実は暗黙のうちに特定のプレイヤー(自家用車所有者、高所得者、デジタルネイティブ)に優先権を与え、他のプレイヤー(自家用車を持たない地方の高齢者、低所得者、デジタル弱者)を迂回させ、遠回りさせ、あるいは最終的に「立ち止まらせる」方向に誘導している。
それは、明示的な差別ではなく、制度設計そのものが内包する「見えない選別」であり、効率の名の下に公平性が犠牲になっているのです。
そして、この「選別」の結果生じる不利益は、往々にして「個人の努力不足」として片付けられてしまう。
するとここで疑問が生じてきます。
インフラの整備やテクノロジーの進化が、かえって特定の層を「動けない」状況に追いやっているという矛盾。
なぜ、我々はその事実に深く向き合おうとしないのでしょうか。
結論:移動の「生態系」が告げる真実と、新たな社会契約
「これまで「当たり前」と信じてきた「移動の自由」は、実は極めて危ういバランスの上に成り立っている。」
私たちが享受する利便性の裏で、静かに、しかし確実に、排除されていく人々がいること。
そして、その排除が、特定の誰かの悪意ではなく、システムと経済、そして私たちの「認識」そのものが生み出している構造的な問題であること。
その意味で、私たちは今、大きな分岐点に立たされています。
「鉄道事業者やバス会社は、単なる輸送サービスを提供する企業ではなく、地域社会の「生命線」を維持する役割を担っている。」
「移動の自由」とは、高齢社会に直面する日本にとって、もはや「個人の選択」や「経済的な商品」ではありません。
私たちが「健康で文化的な最低限度の生活」を営み、社会に参画し、自己を実現するための、最も根源的な「公共財」と言えるでしょう。
あなたが今日、電車に乗るとき、バスを待つとき、あるいは車を運転するとき。
その一つ一つの移動が、多くの見えない要素に支えられています。
そして、多くの人々の「動けない」という現実と隣り合わせにある。
その事実を見つめ直すことが、より良い社会を築く第一歩なのかなと。
そんなことを考えさせられました。
用語解説
- 見せかけの移動平等(Appearance of Mobility Equality):表面上は誰もが自由に移動できる社会に見えるが、実際には経済力、身体能力、情報アクセスの有無によって移動の機会や質に大きな格差がある状態。
- MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス:Mobility as a Service):様々な交通手段(電車、バス、タクシー、シェアサイクルなど)をスマートフォンアプリなどで一元的に検索、予約、決済できるサービス。
- 買い物難民(Shopping Refugees):交通手段の不足や店舗の閉鎖により、食料品や日用品の買い物が困難になっている人々。
- デジタルデバイド(Digital Divide):情報通信技術(ICT)を利用できる者とできない者との間に生じる情報や機会の格差。
- 自己責任論(Self-Responsibility Theory):問題や困難が生じた際、それを社会や制度の問題とせず、個人の努力不足や選択ミスとして片付けてしまう考え方。
- 公共財(Public Goods):経済学の言葉で、非競合性(一人使っても他の人の利用を邪魔しない)と非排除性(対価を払わない人を排除するのが難しい)という特徴を持つ財やサービス。市場原理だけでは十分に提供されにくいとされる。

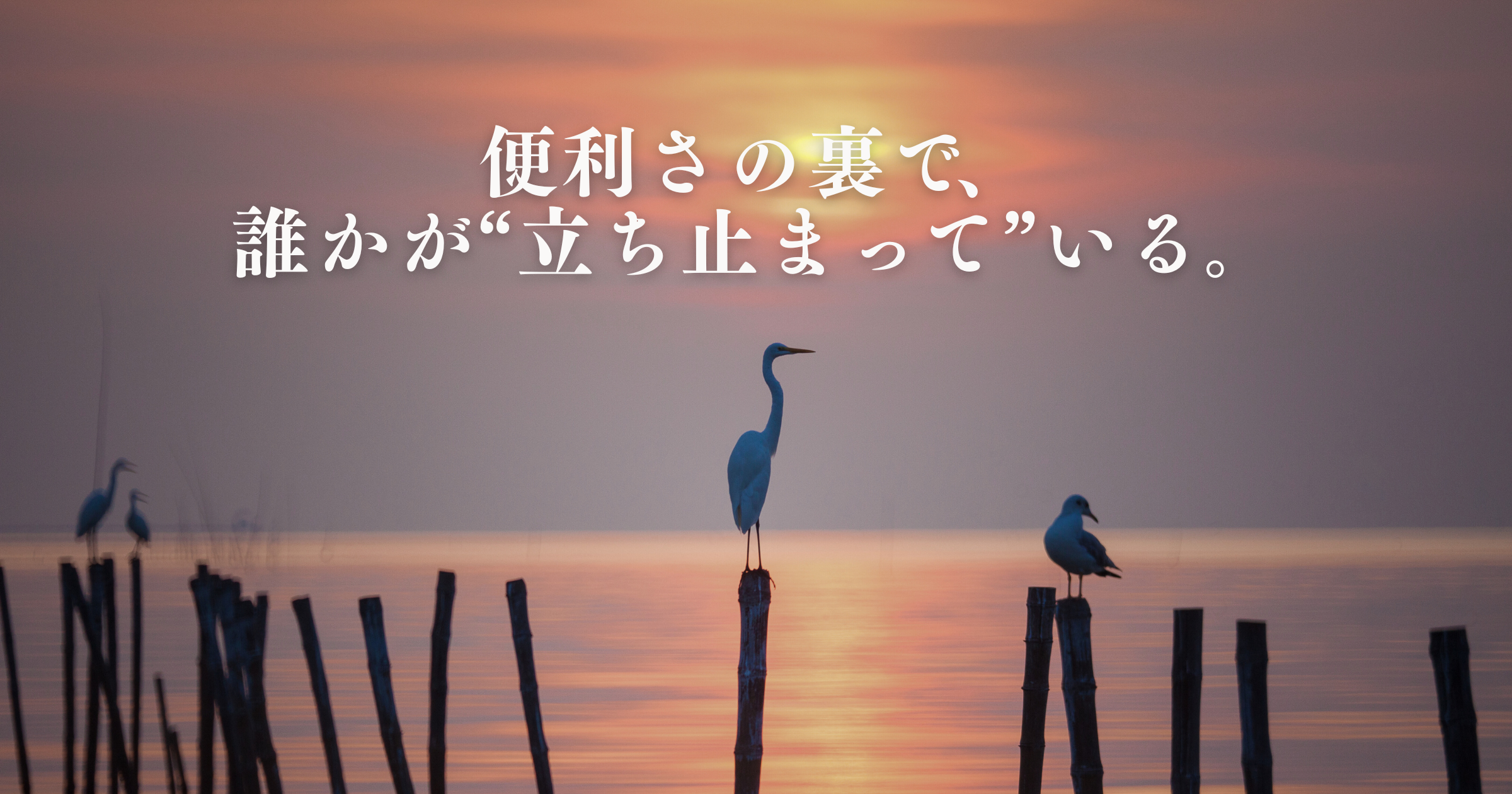
移動の自由の平等が平等でなくなる原因として
1.経済的非効率(採算悪化)によりバス、電車などの公共交通が減らされる、なくなる。タクシーなど民間のサービスも同様で
非効率になれば配車できなくなる
非効率になる原因としては利用者の減少
供給側の路線などの統廃合など
今後、予想より早く人口減少が進む日本ではこの流れはどんどん進むと予想される
2.経済格差による原因
お金さえあれば極端な話、お抱えの運転手を雇うことができ、移動の不自由は問題にならない。そこまで行かなくてもタクシーが利用できるエリアであれば、それを利用すれば費用はかかるが便利に移動はできる
地域によってはタクシー券を高齢者に配布し、補助をしている
お金があればより早く、より快適に移動できる。飛行機のビジネスクラス、ファーストクラス。新幹線のグリーン席など
お金があれば問題はないが、ないと移動に不利になる
3.スマホなどIT機器を使いこなす技術格差
我々の生活の中に深く入り込んだスマホ。これをある程度使いこなさないと移動にも大きな格差となる
タクシーGoアプリ、モバイルスイカや新幹線予約、ホテルの予約などスマホで完結する。AI を使えば旅行のプランもすぐにできる。グーグルマップを使えば行き先の建物や周囲の風景などもストリートビューで事前にチェックできる。それらが使えないと移動も不利になる。
解決策として
1に対しては何度かこの講座で提案しているが、一定の居住エリアを放棄し、他の場所に集中させる。計画的にすればできないことではないと考える。本人の希望もあるだろうが、一人では生きて行けないのであるから、ある程度受け入れてもらい、居住禁止エリアを作る
2.経済格差に対しては公共交通が本来は味方であるが、それも頼れないなら地域で乗合乗用車を作ったらどうか?車で出かけるときは一人ででかけずにかならず誰かをのせるようにする。特区で一般人の一般車にもタクシーのようなサービスを認めたらどうか?
3.最低限のスマホ使用ができるように教育をする
スマホが使いこなせれば案外、移動の不自由の解決策を自分で見つけられるかも
生きていく必需品として毛嫌いせずに学ぶ
そして健康で歩くことができるのであれば意識して健康維持に、つとめる
一番の敵は病気などで動けなくなることにある
医療費削減するための健康増進策として歩くと税金が減るシステムを作ったらどうか?
以上