問題提起
前編では、「アプリの消滅」から「主観なき人生」が訪れることで、人間の意思決定プロセスや幸福感にどのような影響が及ぶのかを見てきました。
そこでは、AIエージェントによるサービスの統合と感情最適化の進行が、私たちを「ただの受信者」にしてしまうリスクがありましたね。
しかし実際、この潮流を推し進めている主体は誰なのでしょうか。
或いは、その裏にはどのようなビジネスモデルの思惑や、テクノロジー企業間の競争原理が働いているのでしょうか。
今回は「AIエージェント産業」を取り巻く内実に焦点を当てて行きます。
具体的には、プラットフォーム寡占の進行によって、どの企業がどのような利益を得るのか。
そして、その過程でユーザーの感情や行動がどのように整理・制御されるのか。
もしAIエージェントが市場や生活空間を支配し、なおかつ個々人の幸福度まで操作可能な段階に至った場合。
果たして誰がその歯止め役となり、どのような規範や倫理が整備されるのでしょうか。
こうした現象は、未来の私たちにどのような影響を与えていくのでしょうか。
背景考察
1. AIプラットフォーム企業の思惑とAPI経済
前編でも述べたように、「アプリ消滅」を支える重要な要素は各企業の提供するAPIエコシステムです。
そう、AIプラットフォーム企業は、そのAPI経済を束ねるハブとしての立場を確立するという未来がまず想定出来ます。
すると、具体的には以下のような構図が浮かび上がってきます。
- ゲートキーパー化:
AIプラットフォーム企業は、複数のサービス・コンテンツを横断的に扱うAIエージェントを自社のコア技術として提供する。
開発者やサービス提供者に対して「自社のAPIを通じてしかユーザーにアクセスできない」という構図を作り出す。
これにより、アプリストアでの直接ダウンロードではなく、エージェント経由の利用が主流となるため、企業は“利用手数料”や“データ収集”で莫大な利益を上げることが可能となる。 - ユーザー行動のトータル解析:
従来、アプリを横断してユーザーデータを集めるには、大掛かりなトラッキングや広告ネットワークの仕組みが必要だった。
しかしAIエージェントという立場を確立すれば、ユーザーの生活全般(移動、購買、娯楽、学習など)に関するデータを一括取得できる。
「主観なき人生」の萌芽は、こうした日常行動の包括的管理の先にある。
2.感情解析スタートアップの勃興とコンセンサス形成
また、AIプラットフォームの裏には、感情解析スタートアップの躍進があると考えられます。
すでに脳波、脈拍、表情解析、音声解析など、多様なバイオメトリクス技術が発達しています。
そこに、深層学習(ディープラーニング)が組み合わさることで、個人の感情状態を極めて高い精度で推定できるようになると考えられます。
かつては映画のトレーラーやCM制作において「どの瞬間に視聴者が最も興味を抱くか?」などが分析されていました。
しかし、これからの時代はリアルタイムでの感情フィードバックがビジネス化されるのかもしれません。
さらに、これらスタートアップを取り込んだプラットフォーム企業は、「幸福度」を中心にしたアルゴリズム調整を行うでしょう。
なぜなら、ユーザーの最適な選択肢とは「幸福に至ること」だからです。
経済学的に言えば、「効用最大化」の概念を人間の感情領域に持ち込み、行動経済学の理論をリアルタイムで実装しているとも言えます。
しかし問題は、それがユーザー主体ではなく、エージェント側の(ひいてはその背後にいる企業の)利益や市場独占力を高める方向で行われるリスクが極めて大きいということです。
3.精神科医・臨床心理士が見る「主観崩壊」の症例
こうした「主観なき人生」の懸念は、精神科医や臨床心理士の立場からはより鮮烈に映ると考えられます。
なぜなら、「AIによる日常提案をすべて受け入れ続けることで、自己肯定感や自律性の喪失が進む。」という現象を目の当たりにするからです。
「日常の些細な選択(どの店で食事をするか、どんな道を通るか、何を学ぶか)すべてをAIチャットや自動レコメンドに任せていた‥」
例えば、AIエージェントに頼れない場面に遭遇した患者は、対人関係のトラブルに直面すると自力での判断ができなくなり、過度の不安症状を引き起こすと考えられます。
AIエージェントが提案する“最適なルート”や“最適なコミュニケーション手法”に従い続けることで、短期的にはストレスは軽減されます。
しかしこれが「幸福感の標準化」に拍車をかけ、個人の内面的な成長機会を奪っていくのではないでしょうか。
4.アナログ回帰運動の光と影
こうした混乱に対して、「アナログ回帰運動」が広がることは十分に考えられます。
具体的には、AIエージェントに頼らない生活スタイルを模索するコミュニティが登場し、“非最適化”をあえて楽しむようなカルチャーが生まれるかもしれません。
そこでは、人間固有の不合理性や不完全性を肯定し、あえて“遠回り”や“試行錯誤”といったプロセスを重視する動きが拡大するでしょう。
しかし一方で、この運動が行き過ぎれば、技術そのものを否定する過激な勢力や、社会からの孤立を深める小さな集落が乱立する危険性もあります。
「オフラインこそ至高」という観念が、やがては新たな排他意識や差別を生み出す可能性も否定できません。
「自由な意志を標榜する集団が、かえって外界からの影響をシャットアウトする“閉じた社会”を形成するという逆説が起こるだろう。」
それはまさに、イギリスの哲学者カール・ポパーが提唱する「開かれた社会とその敵」という理論そのものと言えるでしょう。
ではここで、これまで語られてきた内容を整理してみます。
【新たに生まれる個人の命題】
身近な例としては、「ネット通販が便利だけど、実店舗でのちょっとした衝動買いや店員との会話が新しい刺激になる」という現象があります。
さらに先の未来では、ライフステージ全体をAIが設計してくれる“オートマティック・ライフプラン”が登場するかもしれません。
すると「自分の人生を自分で切り拓く」という感覚がますます希薄化すると考えられます。
【新たに生まれる社会の命題】
例えば、芸術家や研究者にとって、幸福や安定だけが充足された世界は必ずしもプラスに働くわけではありません。
時に不安や不満、過ちや衝突からこそ飛び出す閃きが、イノベーションや文化的進歩をもたらしてくるのだと。
もし全員がAIエージェントの示す快適な道を進むだけの社会になれば、新しい価値観が発芽する余地が大幅に狭まる可能性があります。
「私たちは「主観なき人生」に漫然と流されるのではなく、あえてその主体性を取り戻す選択肢を探究する必要がある。」
極端な思想でデジタル技術と完全に決別する必要はありません。
しかし、いつでも“オフラインへの退路”を用意しておき、意図的に自分自身の意思決定能力や感性を鍛えておくことが、とても重要になります。
私たちが生きるこの時代は、テクノロジーが新たな黄金期をもたらすか、それとも画一化された世界へ導くのか、その瀬戸際に立たされています。
立ち止まって内省し、互いに思考をシェアすることで、膨大なアルゴリズムが仕掛ける落とし穴を想定しておくことが必要なのだなと。
そんなことを考えさせられました。

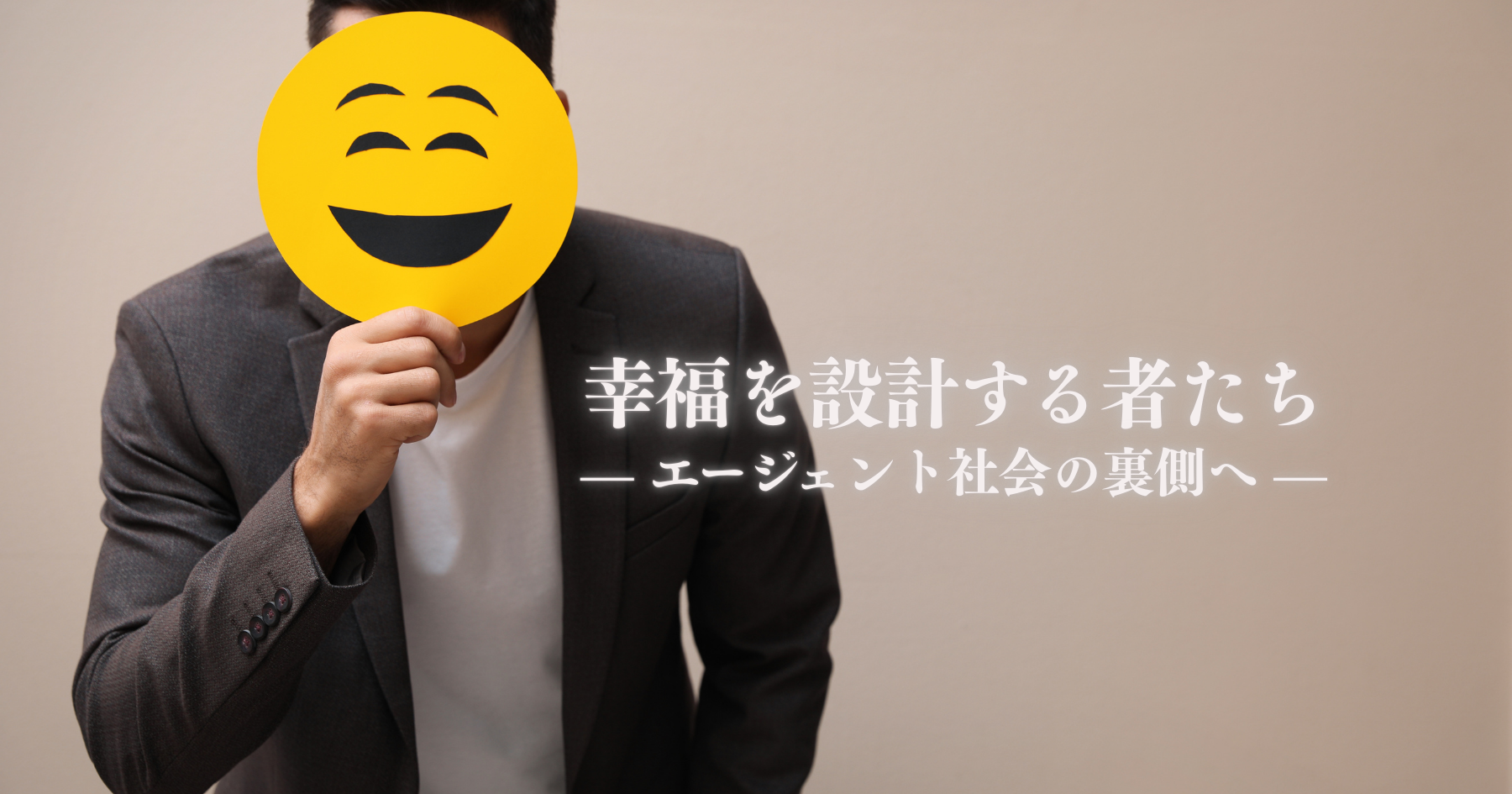

AIエージェントがアプリよりはるかに個人や人間の情報を収集、分析するようになることによる懸念を感じました
AIエージェントによりAIがさらに個人の「感情」「心」を分析できるようになることにより、将来、今まで理解できなかった「感情」「心」といった概念が完全にデジタル化できる可能性があるかもしれない
その時に人間はAIを使う側でいられるのだろうか?
今後20年で人口知能の発達により金魚の脳と人間の脳くらいの差ができる
(今の人間が金魚で人口知能が人間)
と孫正義は予測しているが、本当にそうなった時にどうなっているのか?
アナログ回帰やAIを使わないという選択肢が使えるようで使えないくらい、AIが我々の生活に入り込んでいるかもしれない
それがAIによる人間支配になってなければよいのだが、、、